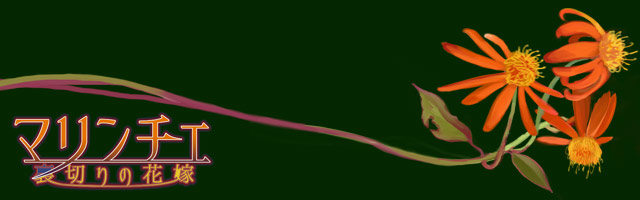Chapter1. 東の地より来たりしもの - 1
月のない夜だった。
春にしては冷たすぎる夜風が喧噪を運んできたとき、マリナリはそれがただ事ではないと直ぐに気がついた。咲いたばかりの花の香に混じり、むんと鼻をつく血の臭いを感じ取ったからだ。祭時でもないのに香って良いものではない。
マリナリは、寝具として与えられていた薄布を剥ぐと寝床から立ち上がった。ただ四角く開けられただけの窓からは冴えた輝きを放つ星が見えた。
「どうしたの、マリナリ」
友の声に、マリナリは短く息を吐いた。
「見に行くのよ」
「見に行くって……外に!?」
「ティルパお願い、静かにしてちょうだい」
マリナリは友の唇にそっと栗色の指を当てた。
奴隷であるマリナリたちには、満足な衣服は与えられていない。だが、こんな月のない夜はそれも味方した。自らの栗色の肌と黒髪は夜に紛れるのに最適である。
奴隷小屋を抜け出たマリナリは、闇を渡るように走り出した。タバスコの街はざわめいていた。家財道具を纏める人々や、起き出してきたばかりなのか、街の外を不安げに見つめる人々。その中に見知った顔を見つけてマリナリは声を上げた。
「トゥクスアウラ!」
「マリナリか。どうした」
トゥクスアウラは、以前はマリナリと同じくタバスコの首長の奴隷だった男だ。近くの富豪に売られた後は会っていなかった。やせ細ってはいるが、顔立ちの精悍さは前のままだ。
「どうしたもこうしたもないわ。何事なの」
「戦さ」
「〈花の戦争〉?」
「まさか」
ふん、とトゥクスアウラは鼻で笑った。花の戦争はこの辺りで一番大きな国、アステカの王モクテスマ二世の名の下に行われる儀礼的な戦争だ。生け贄のため捕虜を得るのが目的の戦争だが、そこには厳格なしきたりがある。
「モクテスマじゃあないな。あいつはいけすかねぇが、しきたりは守る。そうじゃねぇ。あんなえげつない戦い方は他のモンだ。気味の悪い化けモンにのって、見たこともねぇでけぇ筒を振り回す。そっから玉が吐き出されるんだが、その後は訳が判らないまま何人もが死ぬんだ」
「見たの」
「掠っただけでこの様さ」
自虐的に笑い、トゥクスアウラは背中をマリナリへと向けた。その背を見た瞬間、マリナリは顔をしかめた。
「酷い」
何かが背中の上で弾けたかのように、傷が点在していた。一つ一つの傷はそう深くはなさそうだが、こんな夜の中でさえはっきりと判るほど、痛々しげではある。
「逃げてきたのね」
「馬鹿言うな。急を知らせにきたのさ。我が主どのへな」
皮肉めいた物言いに、思わずマリナリもにやりと笑みを浮かべてしまう。それから二、三軽く言葉を交わし、マリナリはまた駆けだした。海岸側が戦の場だという。やがて潮の香りと共に、血の臭いと何かが燃えたような臭いが押し寄せてきた。篝火が燃えていて、喧々囂々とした声がひっきりなしに轟いている。戦場だ。
さすがに正面から回る気はない。
辺りを見渡し、少し離れた場所を選んだ。丘とまではいかないが、他より少しばかり土地が隆起していて、あそこにある樹の上からならよく見渡せそうだ。
影から影へと渡り、息を詰めたまま樹へと上る。はっと短く息を吐いて呼吸を整えた。目を細め、見やる。黒々とした海に、何か大きなものが見えた。まるで海の上の山のようだ。
さらに視線をずらすと、小さく動く人々が見えた。タバスコ軍は見慣れている。タバスコの首長は朱を集都の色にしたいらしく、マリナリの手足につけられた枷も、軍人の頭から生えている羽も朱色だ。炎に照らされてなお赤く見える。
(それにしても夜に戦なんて)
卑怯なことを、とマリナリは臍を噛んだ。夜討ちは、〈花の戦争〉では厳禁とされている。
(相手は何者なのかしら。モクテスマでなければ、わざわざタバスコに手を出す者なんていたかしら)
考えあぐね、視線を左右へと走らせる。それにしても随分と大きい人間のようだ。タバスコ軍が小さく見える。――否。
(違うわ。あれはなに。大きい……獣? 化け物に乗っているの!?)
見たこともない動物に息を呑む。
刹那、雷鳴を思わせる轟音が戦場に響きわたる。
「きゃっ……!」
腹の底に響く重低音だった。同時に、視界が真っ赤に焼ける錯覚に陥る。
驚きで思わず木の枝を掴んでいた手が滑った。体勢を崩し、落ちかけたところへ、鋭い怒声がふりかかる。
「何者だ!」
答える間などない。そのまま樹から滑り落ちたマリナリに出来たのは、ただ悲鳴を必死に呑み込むことだけだった。強い衝撃を覚悟したが、意外にもそれほどの衝撃はなかった。我知らず閉じていた目を開け、マリナリはたまらず悲鳴を上げて身を捩る。だが、振り払おうとした手を強く握られた。混乱に陥りながら、マリナリはその手の主を見上げた。
「落ち着け」
人――なのだろうか。マリナリたちと違い、異常に白い肌をしている。髪の色も薄く、目に至ってはどこを見ているのか判断も付けられないような曖昧な色をしている。強いて言うなら、晴れた日の空の色に近かった。マリナリはこんな生き物を見たことがなかった。姿形は確かに人だろうと思えたが、しかし、こんな色はあるのだろうか。
「まったく、人の頭上に降ってきておきながら悲鳴を上げるとは、随分勝手だな」
低く、落ち着いた声音でその生物が喋ったので、マリナリはまたも目を見開くしかなかった。
「マヤ語……なの? 貴方、言葉が判るの? 人間なの?」
「当たり前だ。マヤ語が通じて良かった。私はエスパニャの人間だ。お前はここの民か?」
「エスパニャ?」
「海の向こうだ。――それはそうとして、お前は何故一人でこんなところにきた。ここは戦場だ。女子供の来るところではない」
「あ……私はタバスコの首長の奴隷よ。でも、奴隷にも、何が起きているのか見定める権利はあるわ。私はそれを確認しにきたの、この目で」
未だ速打つ胸元を押さえながら、マリナリは何とか立ち上がった。じりっと下がりながら、その男を見据える。
陽色の髪が、夜の中篝火に反射する。首から下は黒い服なのか、闇に溶けていた。
「これは随分と剛毅な女奴隷だ」
男は声を立てて笑った。笑うと直ぐ、ぐっとマリナリの顎を持ち上げた。存外強い力に、逆らえない。
「――遊びはおしまいだ。帰りなさい。ここは戦場だ」
きつい眼差しで睨まれ、次の瞬間には手を乱暴に払われていた。そのまま、背を向けて去っていく。
「っ……!」
胸中に爆発的に膨れ上がる恥ずかしさや、怒りや、疑念や――そういった何かがない交ぜになった感情を抱え、けれど叫び出すことすらかなわず、マリナリは去っていくその背を睨みつけた。
背中は遠くなっていく。やがて見えなくなったところでマリナリは走り出した。
戦場に背を向け、裸足で大地を蹴ることしかできなかった。
◇
一の葦の年、春。
その日、ユカタン半島にある小さな街、タバスコは戦に負けた。
春にしては冷たすぎる夜風が喧噪を運んできたとき、マリナリはそれがただ事ではないと直ぐに気がついた。咲いたばかりの花の香に混じり、むんと鼻をつく血の臭いを感じ取ったからだ。祭時でもないのに香って良いものではない。
マリナリは、寝具として与えられていた薄布を剥ぐと寝床から立ち上がった。ただ四角く開けられただけの窓からは冴えた輝きを放つ星が見えた。
「どうしたの、マリナリ」
友の声に、マリナリは短く息を吐いた。
「見に行くのよ」
「見に行くって……外に!?」
「ティルパお願い、静かにしてちょうだい」
マリナリは友の唇にそっと栗色の指を当てた。
奴隷であるマリナリたちには、満足な衣服は与えられていない。だが、こんな月のない夜はそれも味方した。自らの栗色の肌と黒髪は夜に紛れるのに最適である。
奴隷小屋を抜け出たマリナリは、闇を渡るように走り出した。タバスコの街はざわめいていた。家財道具を纏める人々や、起き出してきたばかりなのか、街の外を不安げに見つめる人々。その中に見知った顔を見つけてマリナリは声を上げた。
「トゥクスアウラ!」
「マリナリか。どうした」
トゥクスアウラは、以前はマリナリと同じくタバスコの首長の奴隷だった男だ。近くの富豪に売られた後は会っていなかった。やせ細ってはいるが、顔立ちの精悍さは前のままだ。
「どうしたもこうしたもないわ。何事なの」
「戦さ」
「〈花の戦争〉?」
「まさか」
ふん、とトゥクスアウラは鼻で笑った。花の戦争はこの辺りで一番大きな国、アステカの王モクテスマ二世の名の下に行われる儀礼的な戦争だ。生け贄のため捕虜を得るのが目的の戦争だが、そこには厳格なしきたりがある。
「モクテスマじゃあないな。あいつはいけすかねぇが、しきたりは守る。そうじゃねぇ。あんなえげつない戦い方は他のモンだ。気味の悪い化けモンにのって、見たこともねぇでけぇ筒を振り回す。そっから玉が吐き出されるんだが、その後は訳が判らないまま何人もが死ぬんだ」
「見たの」
「掠っただけでこの様さ」
自虐的に笑い、トゥクスアウラは背中をマリナリへと向けた。その背を見た瞬間、マリナリは顔をしかめた。
「酷い」
何かが背中の上で弾けたかのように、傷が点在していた。一つ一つの傷はそう深くはなさそうだが、こんな夜の中でさえはっきりと判るほど、痛々しげではある。
「逃げてきたのね」
「馬鹿言うな。急を知らせにきたのさ。我が主どのへな」
皮肉めいた物言いに、思わずマリナリもにやりと笑みを浮かべてしまう。それから二、三軽く言葉を交わし、マリナリはまた駆けだした。海岸側が戦の場だという。やがて潮の香りと共に、血の臭いと何かが燃えたような臭いが押し寄せてきた。篝火が燃えていて、喧々囂々とした声がひっきりなしに轟いている。戦場だ。
さすがに正面から回る気はない。
辺りを見渡し、少し離れた場所を選んだ。丘とまではいかないが、他より少しばかり土地が隆起していて、あそこにある樹の上からならよく見渡せそうだ。
影から影へと渡り、息を詰めたまま樹へと上る。はっと短く息を吐いて呼吸を整えた。目を細め、見やる。黒々とした海に、何か大きなものが見えた。まるで海の上の山のようだ。
さらに視線をずらすと、小さく動く人々が見えた。タバスコ軍は見慣れている。タバスコの首長は朱を集都の色にしたいらしく、マリナリの手足につけられた枷も、軍人の頭から生えている羽も朱色だ。炎に照らされてなお赤く見える。
(それにしても夜に戦なんて)
卑怯なことを、とマリナリは臍を噛んだ。夜討ちは、〈花の戦争〉では厳禁とされている。
(相手は何者なのかしら。モクテスマでなければ、わざわざタバスコに手を出す者なんていたかしら)
考えあぐね、視線を左右へと走らせる。それにしても随分と大きい人間のようだ。タバスコ軍が小さく見える。――否。
(違うわ。あれはなに。大きい……獣? 化け物に乗っているの!?)
見たこともない動物に息を呑む。
刹那、雷鳴を思わせる轟音が戦場に響きわたる。
「きゃっ……!」
腹の底に響く重低音だった。同時に、視界が真っ赤に焼ける錯覚に陥る。
驚きで思わず木の枝を掴んでいた手が滑った。体勢を崩し、落ちかけたところへ、鋭い怒声がふりかかる。
「何者だ!」
答える間などない。そのまま樹から滑り落ちたマリナリに出来たのは、ただ悲鳴を必死に呑み込むことだけだった。強い衝撃を覚悟したが、意外にもそれほどの衝撃はなかった。我知らず閉じていた目を開け、マリナリはたまらず悲鳴を上げて身を捩る。だが、振り払おうとした手を強く握られた。混乱に陥りながら、マリナリはその手の主を見上げた。
「落ち着け」
人――なのだろうか。マリナリたちと違い、異常に白い肌をしている。髪の色も薄く、目に至ってはどこを見ているのか判断も付けられないような曖昧な色をしている。強いて言うなら、晴れた日の空の色に近かった。マリナリはこんな生き物を見たことがなかった。姿形は確かに人だろうと思えたが、しかし、こんな色はあるのだろうか。
「まったく、人の頭上に降ってきておきながら悲鳴を上げるとは、随分勝手だな」
低く、落ち着いた声音でその生物が喋ったので、マリナリはまたも目を見開くしかなかった。
「マヤ語……なの? 貴方、言葉が判るの? 人間なの?」
「当たり前だ。マヤ語が通じて良かった。私はエスパニャの人間だ。お前はここの民か?」
「エスパニャ?」
「海の向こうだ。――それはそうとして、お前は何故一人でこんなところにきた。ここは戦場だ。女子供の来るところではない」
「あ……私はタバスコの首長の奴隷よ。でも、奴隷にも、何が起きているのか見定める権利はあるわ。私はそれを確認しにきたの、この目で」
未だ速打つ胸元を押さえながら、マリナリは何とか立ち上がった。じりっと下がりながら、その男を見据える。
陽色の髪が、夜の中篝火に反射する。首から下は黒い服なのか、闇に溶けていた。
「これは随分と剛毅な女奴隷だ」
男は声を立てて笑った。笑うと直ぐ、ぐっとマリナリの顎を持ち上げた。存外強い力に、逆らえない。
「――遊びはおしまいだ。帰りなさい。ここは戦場だ」
きつい眼差しで睨まれ、次の瞬間には手を乱暴に払われていた。そのまま、背を向けて去っていく。
「っ……!」
胸中に爆発的に膨れ上がる恥ずかしさや、怒りや、疑念や――そういった何かがない交ぜになった感情を抱え、けれど叫び出すことすらかなわず、マリナリは去っていくその背を睨みつけた。
背中は遠くなっていく。やがて見えなくなったところでマリナリは走り出した。
戦場に背を向け、裸足で大地を蹴ることしかできなかった。
◇
一の葦の年、春。
その日、ユカタン半島にある小さな街、タバスコは戦に負けた。