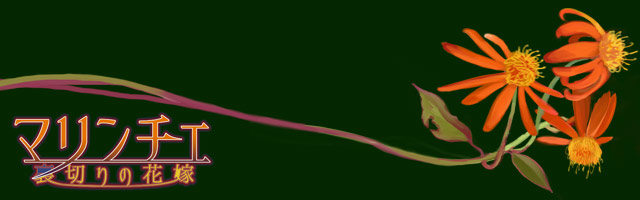Chapter1. 東の地より来たりしもの - 3
◇
陽が傾き始め、空と大地が橙に染まり始めた頃、タバスコの街側から微かなざわめきが流れてきた。
隊の引き上げを準備していたこの軍――エスパニャのコルテス軍とマヤ語の男は言っていた――の男どもが怪訝な顔をしてそちらを見やる。マリナリはティルパと顔を見合わせ、何も言わずに空を見上げた。どう、ということもない。ただ単純に、今日という日が終わるだけだ。
「あのざわめきが何か、知っているのか」
声をかけられ、マリナリは面倒くさそうに顔をしかめた。
「今日という日が終わるだけよ」
「それであれほどのざわめきが?」
「儀式なんだから仕方ないでしょう。当たり前のことを訊かないで」
切り捨てるようなマリナリとは裏腹に、ティルパは丸い目をくるんとまわして首を傾げる。
「まさか、儀式を知らなかったりするのかな」
「やめてよティルパ。そんなわけないでしょう」
「だってぇ」
「知らぬ」
断言に、マリナリは眉根を寄せる。
「知らない?」
「知らぬ。儀式とは? 何が起きようとしている」
そういう割に、マヤ語の男の口調は堅かった。表情もだ。
「別に……普通のことよ。朝を呼ぶための儀式。まぁ、こんなとこでやらなくてもモクテスマがテノチティトランでやってるんだけど」
「でもここ、遠いからね」
「そうね」
遠くても、特に朝がくることに対して不便があるわけでもないだろうがタバスコの首長は不思議とアステカの首都テノチティトラン――しいてはモクテスマに対抗心を抱いている。そして何より、こういった敗戦などという不安なことの後は『目に見える安心』を人は欲するものだ。彼はそういった人心掌握術に長けていた。
「……何硬い顔しているの」
マリナリは膝を叩きながら立ち上がった。
「気になるなら、見に行けばいいじゃない。場所が判らないのなら案内するわ」
◇
ついてきたのは、マヤ語を話す金髪の男と、黒髪の神経質そうな顔をした男、それからあの粗野なコルテスだった。それ以外の者たちは一足先に船に戻るという。
不満がないわけではないが、言ったところでどうなるものでもない。マリナリとティルパはそろって道案内に借り出された。男どもは、外套衣を頭からかぶっている。怪しいことこの上ないが、確かにこうすれば容貌は見えないだろう。
タバスコの街に入り、広場まで進んでいく。近づくにつれ、むんと噎せるような臭いが強まっていった。
「――」
神経質そうな男が、きりきりと歯をならしながら何かを言っている。大方、何の臭いだとか言い出しているのだろうが、答えを見るために来ているのに口に出して言ってやる理由もない。
すぐに、視界が開けた。柔らかな夕陽の中に、三角形の神殿が立っている。精密な石の重なりが階段状になってる。その神殿の上には神官たちの姿が見えた。
この血の臭いの元だ。
「儀式よ」
短く告げたが、男どもは誰一人として聞いていないようだった。見ると、コルテス以外の二人は白い顔をさらに白くさせて、見上げている。コルテスはどこか皮肉気な笑みを崩してはいなかった。
周りでは住民が興奮した声を上げている。
神殿の上には神官が五人いた。そして、生け贄がひとり。今日の生け贄は若い男のようだった。上半身は裸で、台の上で仰向けになっている。
高位神官が口上を述べている。さすがに距離があって聞こえないが、神への言葉だろう。そして周りにいた神官たちが、贄の両手足を押さえ込んだ。フリントのナイフが夕陽に煌めく。
そしてそれは、生贄の胸へと突きたった。
「……っ!」
金髪の男が一歩前に出る。しかしコルテスが腕を伸ばして遮った。その様子をちらりと見てから、マリナリはまた神殿へと目を向けた。
男の胸に突きたったナイフはそのまま肉を切り裂いていく。生きたまま身を裂かれ、生贄は断末魔の叫びを上げる。血の臭いが、いっそう濃くなった。
ややもしないうちに、高位神官がぐっと手を挙げた。空にまっすぐ伸びた手の中には湯気の立つ、まだぴくぴくと動く心臓が握られていた。血塗れた赤い心臓は、鮮やかだ。夕陽そのものにさえ見える。高位神官はその生きたままの心臓を壁へと投げつけた。血が飛び散り、群衆の歓声が沸きあがる。
「何故……こんな馬鹿な真似を……」
「貴方、本当に知らないの?」
呻く金髪の男に呆れて、マリナリは嘆息した。
「戦の神ウィツィロポチトリは太陽神よね」
「お前たちの神か」
妙な言い回しだとは思ったが、マリナリは素直に頷いた。
「ウィツィロポチトリは太陽よ。でも、太陽が沈んでいる間は夜の神テスカトリポカの世界。太陽神と夜の神は戦っているし、太陽神は毎日勝っている。だから、朝がくるわ。でも、負けたらどうなる?」
「負ける?」
「戦いには勝敗があるでしょう。負ければ朝が来なくなるわ。だから、勝つために力を送るの。それが、あれよ」
マリナリは視線で叩きつけられた力の源を示した。
「心臓、か」
「正しくは生きた心臓。あるいは聖なる水……血のことね。最も貴いものを差し出してこそ、ウィツィロポチトリは勝って――ちょっと」
マリナリの言葉を最後まで聞かず、金髪の男はきびすを返した。
「船へ戻る。お前たちに正しい神の話をしよう」
「ただしい……神様?」
ティルパがきょとんと首を傾げたが、マリナリはふんと鼻を鳴らすしかなかった。
◇
ヘロニモ・デ・アギラールは与えられた船室の中、短く息を吐いた。頼りなげに揺れる洋燈に照らされた聖書を閉じる。座っていた椅子の背もたれに体重を預けると、ぎし、と軽く音がした。
「……くそ」
思わず汚い言葉が口から漏れて、アギラールは自身の金色の頭をかいた。いくら聖書を読んでも、今夜はなかなか心が鎮まらない。
脳裏に浮かぶのは、マリナリと名乗ったあの奴隷の娘の、突き刺すような黒瞳。そしてなにより、血なまぐさいあの儀式とやらだ。
実際のところ、この辺りにすむ褐色肌の人々の間に生け贄の風習があることは知っていた。しかしまさか、あんな大層な理由をつけて毎日行っているとは思っていなかった。彼らの神は、随分と我儘なようだ。
明日には洗礼を行うことになっている。その為に、二十名の奴隷の娘たちにはキリストの教えを語ってみたのだが、どうにも手応えがなかった。それどころかあのマリナリに至っては、ありありと信じないと言ったまなざしを向けていた。昨夜、あの戦場に単身で現れたことを考えてみても、どうにも気が強すぎるきらいがあるようだ。
「おーい。部下一」
あけすけな軽い声と同時に、船室の扉が開かれた。この船の中でそんな物言いをするのは一人しかいない。アギラールは嘆息を飲み込みながら振り返った。
「アギラール、です。……何かご用ですか」
振り返った視線の先、コルテスが太い笑みを浮かべて立っていた。
その頬がやや赤く腫れているのを見つけ、アギラールは顔をしかめた。
「何やったんですか」
「ナニをやろうかとなー」
「……また殴られ」
「ました」
「でしょうね」
短く嘆息し、アギラールは椅子から立ち上がった。並んでみると、コルテスはさほど上背はない。しかし、その身に纏う気配のようなものが彼自身を大きく見せていた。
「だが、大事だぜ。ナニってのは」
「何寝ぼけてんですか」
「失敬だな、部下一くん」
「アギラールです」
再度繰り返すが、コルテスは気にもとめない。だが、名前を覚えていないわけではないだろう。彼なりのお遊びだ。
コルテスは太い指で自身の髭をさわりながら目を細める。
「部下どもにすれば、国から離れて、こんな異人の世界に放り出されたようなもんだ。しかも隊長が俺のような人間じゃあストレスも溜まるってぇもんだ」
「……はぁ」
「しかもまぁ、男臭い船内だしな。そこに異人とはいえなかなかの美女ばかり二十人やってきた。肌を求めることに不思議はない。そんなわけでちぃと、目立った功績のあるものたちに女どもをあてがったんだが」
「分配をされたのですね」
「ああ。ほとんどの女は自分の立場を理解して受け入れたが、たったひとり、こういう奴がいた、と」
微かに笑いながら、コルテスは己の頬を指した。ひとり、と言われアギラールは軽く頭を抱えた。
「野蛮ですね。異教の民は」
「そうかぁ? 宗教関係なく女てぇのはままああいうのがいる。刃物持ち出さないだけましだろう」
「……持ち出されたことがあるんですね」
「スパッと」
けろっと言われ、アギラールはそれ以上深入りしないことにした。
陽が傾き始め、空と大地が橙に染まり始めた頃、タバスコの街側から微かなざわめきが流れてきた。
隊の引き上げを準備していたこの軍――エスパニャのコルテス軍とマヤ語の男は言っていた――の男どもが怪訝な顔をしてそちらを見やる。マリナリはティルパと顔を見合わせ、何も言わずに空を見上げた。どう、ということもない。ただ単純に、今日という日が終わるだけだ。
「あのざわめきが何か、知っているのか」
声をかけられ、マリナリは面倒くさそうに顔をしかめた。
「今日という日が終わるだけよ」
「それであれほどのざわめきが?」
「儀式なんだから仕方ないでしょう。当たり前のことを訊かないで」
切り捨てるようなマリナリとは裏腹に、ティルパは丸い目をくるんとまわして首を傾げる。
「まさか、儀式を知らなかったりするのかな」
「やめてよティルパ。そんなわけないでしょう」
「だってぇ」
「知らぬ」
断言に、マリナリは眉根を寄せる。
「知らない?」
「知らぬ。儀式とは? 何が起きようとしている」
そういう割に、マヤ語の男の口調は堅かった。表情もだ。
「別に……普通のことよ。朝を呼ぶための儀式。まぁ、こんなとこでやらなくてもモクテスマがテノチティトランでやってるんだけど」
「でもここ、遠いからね」
「そうね」
遠くても、特に朝がくることに対して不便があるわけでもないだろうがタバスコの首長は不思議とアステカの首都テノチティトラン――しいてはモクテスマに対抗心を抱いている。そして何より、こういった敗戦などという不安なことの後は『目に見える安心』を人は欲するものだ。彼はそういった人心掌握術に長けていた。
「……何硬い顔しているの」
マリナリは膝を叩きながら立ち上がった。
「気になるなら、見に行けばいいじゃない。場所が判らないのなら案内するわ」
◇
ついてきたのは、マヤ語を話す金髪の男と、黒髪の神経質そうな顔をした男、それからあの粗野なコルテスだった。それ以外の者たちは一足先に船に戻るという。
不満がないわけではないが、言ったところでどうなるものでもない。マリナリとティルパはそろって道案内に借り出された。男どもは、外套衣を頭からかぶっている。怪しいことこの上ないが、確かにこうすれば容貌は見えないだろう。
タバスコの街に入り、広場まで進んでいく。近づくにつれ、むんと噎せるような臭いが強まっていった。
「――」
神経質そうな男が、きりきりと歯をならしながら何かを言っている。大方、何の臭いだとか言い出しているのだろうが、答えを見るために来ているのに口に出して言ってやる理由もない。
すぐに、視界が開けた。柔らかな夕陽の中に、三角形の神殿が立っている。精密な石の重なりが階段状になってる。その神殿の上には神官たちの姿が見えた。
この血の臭いの元だ。
「儀式よ」
短く告げたが、男どもは誰一人として聞いていないようだった。見ると、コルテス以外の二人は白い顔をさらに白くさせて、見上げている。コルテスはどこか皮肉気な笑みを崩してはいなかった。
周りでは住民が興奮した声を上げている。
神殿の上には神官が五人いた。そして、生け贄がひとり。今日の生け贄は若い男のようだった。上半身は裸で、台の上で仰向けになっている。
高位神官が口上を述べている。さすがに距離があって聞こえないが、神への言葉だろう。そして周りにいた神官たちが、贄の両手足を押さえ込んだ。フリントのナイフが夕陽に煌めく。
そしてそれは、生贄の胸へと突きたった。
「……っ!」
金髪の男が一歩前に出る。しかしコルテスが腕を伸ばして遮った。その様子をちらりと見てから、マリナリはまた神殿へと目を向けた。
男の胸に突きたったナイフはそのまま肉を切り裂いていく。生きたまま身を裂かれ、生贄は断末魔の叫びを上げる。血の臭いが、いっそう濃くなった。
ややもしないうちに、高位神官がぐっと手を挙げた。空にまっすぐ伸びた手の中には湯気の立つ、まだぴくぴくと動く心臓が握られていた。血塗れた赤い心臓は、鮮やかだ。夕陽そのものにさえ見える。高位神官はその生きたままの心臓を壁へと投げつけた。血が飛び散り、群衆の歓声が沸きあがる。
「何故……こんな馬鹿な真似を……」
「貴方、本当に知らないの?」
呻く金髪の男に呆れて、マリナリは嘆息した。
「戦の神ウィツィロポチトリは太陽神よね」
「お前たちの神か」
妙な言い回しだとは思ったが、マリナリは素直に頷いた。
「ウィツィロポチトリは太陽よ。でも、太陽が沈んでいる間は夜の神テスカトリポカの世界。太陽神と夜の神は戦っているし、太陽神は毎日勝っている。だから、朝がくるわ。でも、負けたらどうなる?」
「負ける?」
「戦いには勝敗があるでしょう。負ければ朝が来なくなるわ。だから、勝つために力を送るの。それが、あれよ」
マリナリは視線で叩きつけられた力の源を示した。
「心臓、か」
「正しくは生きた心臓。あるいは聖なる水……血のことね。最も貴いものを差し出してこそ、ウィツィロポチトリは勝って――ちょっと」
マリナリの言葉を最後まで聞かず、金髪の男はきびすを返した。
「船へ戻る。お前たちに正しい神の話をしよう」
「ただしい……神様?」
ティルパがきょとんと首を傾げたが、マリナリはふんと鼻を鳴らすしかなかった。
◇
ヘロニモ・デ・アギラールは与えられた船室の中、短く息を吐いた。頼りなげに揺れる洋燈に照らされた聖書を閉じる。座っていた椅子の背もたれに体重を預けると、ぎし、と軽く音がした。
「……くそ」
思わず汚い言葉が口から漏れて、アギラールは自身の金色の頭をかいた。いくら聖書を読んでも、今夜はなかなか心が鎮まらない。
脳裏に浮かぶのは、マリナリと名乗ったあの奴隷の娘の、突き刺すような黒瞳。そしてなにより、血なまぐさいあの儀式とやらだ。
実際のところ、この辺りにすむ褐色肌の人々の間に生け贄の風習があることは知っていた。しかしまさか、あんな大層な理由をつけて毎日行っているとは思っていなかった。彼らの神は、随分と我儘なようだ。
明日には洗礼を行うことになっている。その為に、二十名の奴隷の娘たちにはキリストの教えを語ってみたのだが、どうにも手応えがなかった。それどころかあのマリナリに至っては、ありありと信じないと言ったまなざしを向けていた。昨夜、あの戦場に単身で現れたことを考えてみても、どうにも気が強すぎるきらいがあるようだ。
「おーい。部下一」
あけすけな軽い声と同時に、船室の扉が開かれた。この船の中でそんな物言いをするのは一人しかいない。アギラールは嘆息を飲み込みながら振り返った。
「アギラール、です。……何かご用ですか」
振り返った視線の先、コルテスが太い笑みを浮かべて立っていた。
その頬がやや赤く腫れているのを見つけ、アギラールは顔をしかめた。
「何やったんですか」
「ナニをやろうかとなー」
「……また殴られ」
「ました」
「でしょうね」
短く嘆息し、アギラールは椅子から立ち上がった。並んでみると、コルテスはさほど上背はない。しかし、その身に纏う気配のようなものが彼自身を大きく見せていた。
「だが、大事だぜ。ナニってのは」
「何寝ぼけてんですか」
「失敬だな、部下一くん」
「アギラールです」
再度繰り返すが、コルテスは気にもとめない。だが、名前を覚えていないわけではないだろう。彼なりのお遊びだ。
コルテスは太い指で自身の髭をさわりながら目を細める。
「部下どもにすれば、国から離れて、こんな異人の世界に放り出されたようなもんだ。しかも隊長が俺のような人間じゃあストレスも溜まるってぇもんだ」
「……はぁ」
「しかもまぁ、男臭い船内だしな。そこに異人とはいえなかなかの美女ばかり二十人やってきた。肌を求めることに不思議はない。そんなわけでちぃと、目立った功績のあるものたちに女どもをあてがったんだが」
「分配をされたのですね」
「ああ。ほとんどの女は自分の立場を理解して受け入れたが、たったひとり、こういう奴がいた、と」
微かに笑いながら、コルテスは己の頬を指した。ひとり、と言われアギラールは軽く頭を抱えた。
「野蛮ですね。異教の民は」
「そうかぁ? 宗教関係なく女てぇのはままああいうのがいる。刃物持ち出さないだけましだろう」
「……持ち出されたことがあるんですね」
「スパッと」
けろっと言われ、アギラールはそれ以上深入りしないことにした。