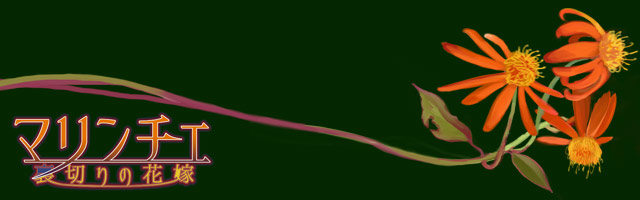Chapter1. 東の地より来たりしもの - 4
「それで、あの娘は?」
アギラールが問うたと同時に、船室の扉が叩かれた。コルテスが許可の声を上げると、静かに扉が開かれ、ひとりの男が顔を出した。体格のいい、だが温和な雰囲気さえある男だ。鎧を脱ぐと、兵士にはあまり見えない。
「アロンソ殿」
アロンソ・ヘルナンデス・プエルトカレーロ。この隊の中でもコルテスと仲が良い一人だ。
「これは、アギラール殿もいらしたのですか。失礼しました」
「かまわん。報告か?」
コルテスの言葉にアロンソは短く頷いて、簡単に状況を報告した。隊員の様子――負傷者や体調不良者の数――、食糧の状況、貢物の計算も終えたようだった。定期報告だろう。
コルテスは無造作に頷き、ふと思い出したようにアギラールに目をやった。
「ああ。さっきの質問だが」
「はい?」
「あの娘だ。とりあえずアロンソに渡してみた」
軽い言葉に、一瞬アギラールは度肝を抜かれた。アロンソに視線をやる。それから、深い溜息が口をついた。心の中に浮かぶ感情はただひとつ、哀れさだった。
「また酷な真似を」
文武に猛る割に物腰の穏やかな彼には、あの娘は持て余すだろうとしか思えなかった。コルテスも判っているのだろう。ひょい、と肩をすくめるだけだった。当の本人は、軽く苦笑している。
「褒美、という話でしたが、褒美を頂戴するほど何かをしたわけではありませんので」
「いつもの礼とでも思っておけ」
コルテスが髭をいじる。アギラールはアロンソに哀れみの目を向けた。
「大変ですね」
「元気の良い方でしたね。私は嫌いではありませんが」
「……はぁ」
アロンソの趣味はアギラールには到底理解出来そうになかった。コルテスが笑う。
「ま、今夜は様子見だな。明日には洗礼を受けさせて、暫くしたら出発だ」
「はい」
「アギラール」
ふいに、コルテスは声を低くした。
「もしアロンソがあれを持て余すとしたら、お前いるか?」
「冗談でしょう」
間髪入れず、アギラールは吐き捨てた。
「あれは異教の女です。そもそも、私は神に仕える身です」
「だが、ゲレロはマヤの女に下っただろう」
「……っ」
反射的に何かを叫びかけ、しかしそれは言葉にならなかった。アギラールのその反応を楽しむように、コルテスは深い笑みを顔に刻んだ後ゆっくりと背を向けた。
「未来の事は誰にも判らんさ、アギラール。思い込みはおかしな事態を招く。今その場にあるものを、そのまま見るんだな」
コルテスが部屋を出ていってから、アギラールは目を閉じた。瞼の向こうの闇の中、ゆらゆらと何かが揺れている。
小さく、身体が震えた。嵐の中揺れる舟。天地も判らなくなる感覚。そして、辛酸をなめたあの日々。
閉ざしたい記憶は遠いものではない。つい先日まで、確かに身に降りかかっていた火の粉だ。今こうしてエスパニャの言葉でコルテスと話せることも聖書を読むことも、奇跡と言っていい。
ただ、ゲレロは――かつての友は、その奇跡を自ら手放した。それだけだ。
「アギラール殿」
アロンソの控えめな声が、闇を割ってきた。目を開ける。柔らかな笑みがそこにあった。
「あまり、思いつめなさらぬよう」
それ以上は何も言わず、アロンソも部屋を後にした。二人がいなくなった部屋の中に、まだあの悍ましい記憶が漂っているようでアギラールは再び目を閉じた。
「神よ。貴方は私に何をお望みか」
呟きは、誰にも届かずに消えた。
◇
マリナリは憤っていた。
これからお前たちは奴隷という立場ではない。確かにあの男はマヤ語でそう言ったはずだった。だがその彼が離れると、コルテスが幾人かの男たちを呼びつけた。そしてマリナリたちと男たちを交互に見ながら、男たちに女を渡し始めたのだ。
(あれじゃまるきり家畜と同じじゃない!)
確かにどの男も、奴隷に対する扱いというよりは一人の女性に対する扱いをしてくれているようだった。それはティルパやほかの仲間たちの表情からも判った。しかし、問題はそこではない。選び、配分し、女たちの意思は聞かずに受け渡す。その行為自体が我慢ならなかった。
たまらず一発見舞ってしまったのだが、コルテスは意にも介さなかったようだ。結局マリナリも、穏和そうな男につれられて部屋に入るしかなかった。
今マリナリたちがいるのは、船の中だという。だが、マリナリの知識の中ではこれほど大きな船など、存在していなかった。昨晩、戦の中で見かけた海の上に浮く山はこの船らしかった。
部屋の中、ひとり憤慨し続けるマリナリを余所に、コルテスがあてがった穏和な男は黙々と本を読んでいる。
肩幅が広く、上背もある。戦士なのだろう――腕も脚も太く、しっかりしている。だが、威圧感は殆ど無い男だった。少しばかり目が垂れ気味なせいかもしれない。穏やかに本を読む様子は、軟弱に見えてどうにも気に食わない。マリナリは甲板に出ることにした。男も止めはしなかった。部屋を出るときに少し顔を上げ、曖昧に笑むだけだった。
甲板に出ると、夜風がマリナリを殴りつけた。ふっと、短く息を吐く。肌寒い風だが、それが火照った頭には心地よかった。
ふと、甲板の先に人影があるのを見つけ、マリナリは歩み寄る。そしてあからさまにがっかりした体で呟いて見せた。
「何だ、貴方なの」
「マリナリか」
そこにいたのは金髪の男だった。マヤ語が返ってきて、会話が出来そうなことに悔しいながらも安堵する。
「よく私がいると気付いたな。暗くて見えないと思ったが」
「目はいい方なの」
「そうか」
短い返事の後、男はマリナリから目をそらした。陸の方を見ている。何となくマリナリも隣に並んだ。港の篝火が赤々と燃えている。
「不公平よね」
「何がだ」
マリナリの突然の言葉に、男は陸を見据えたまま答える。
「名前。私貴方の名前も知らないわ。貴方は私を勝手に呼ぶけれど」
「名乗ったのはお前だろう。……まあいい。私はアギラールだ。ヘロニモ・デ・アギラール。アギラールでいい」
「アギラール、ね。変な名前だわ」
短く答える。たとえそれが気に食わない男の名前であったとしても、何も判らないよりはいいだろう。
ふと、マリナリは目を瞠った。視線の先、陸側に揺れる影を見つけたのだ。慌ててきびすを返して走り出す。すぐに、アギラールも追ってきた。
「何事だ。どこへ行く」
「すぐ戻るわよ」
言ったが、アギラールは離れなかった。少々鬱陶しく思いながら、船内を駆けていく。すぐ、外に出た。揺れない足下にほっとする間もなく、マリナリは声をあげた。
「トゥクスアウラ!」
篝火に照らされた人影に走りよる。友は驚きの顔で迎えてくれた。
「マリナリ」
「どうしたの、こんなところに来て」
トゥクスアウラは精悍な顔を緩ませて笑った。マリナリの肩に手を乗せ、眼を覗きこんでくる。
「別れを言いに来た」
「別れ……って、私がここを離れるから? わざわざ?」
マリナリは怪訝に思ってトゥクスアウラを見上げた。
マリナリもトゥクスアウラも、己の立場は理解しているつもりだ。友ではある。だが、いつ互いにどこに連れて行かれ、連絡が取れなくなっても当然だと思っていた。生きていれば、またどこかで遭うこともあるだろう。それがある限り、別れではない。
そこまで考えてから、マリナリは背筋が凍るのを感じた。唇が乾いていく。
「まさか」
生きている限り、別れは言わない。ならば、わざわざ別れを告げに来たのはその逆だということだ。自身の肩に掛けられた手を握り返す。
「トゥクスアウラ!」
「明日、俺の心臓は神に捧げられる」
静かに告げられた言葉が、全身を毒のように駆け巡っていくのが判った。
アギラールが問うたと同時に、船室の扉が叩かれた。コルテスが許可の声を上げると、静かに扉が開かれ、ひとりの男が顔を出した。体格のいい、だが温和な雰囲気さえある男だ。鎧を脱ぐと、兵士にはあまり見えない。
「アロンソ殿」
アロンソ・ヘルナンデス・プエルトカレーロ。この隊の中でもコルテスと仲が良い一人だ。
「これは、アギラール殿もいらしたのですか。失礼しました」
「かまわん。報告か?」
コルテスの言葉にアロンソは短く頷いて、簡単に状況を報告した。隊員の様子――負傷者や体調不良者の数――、食糧の状況、貢物の計算も終えたようだった。定期報告だろう。
コルテスは無造作に頷き、ふと思い出したようにアギラールに目をやった。
「ああ。さっきの質問だが」
「はい?」
「あの娘だ。とりあえずアロンソに渡してみた」
軽い言葉に、一瞬アギラールは度肝を抜かれた。アロンソに視線をやる。それから、深い溜息が口をついた。心の中に浮かぶ感情はただひとつ、哀れさだった。
「また酷な真似を」
文武に猛る割に物腰の穏やかな彼には、あの娘は持て余すだろうとしか思えなかった。コルテスも判っているのだろう。ひょい、と肩をすくめるだけだった。当の本人は、軽く苦笑している。
「褒美、という話でしたが、褒美を頂戴するほど何かをしたわけではありませんので」
「いつもの礼とでも思っておけ」
コルテスが髭をいじる。アギラールはアロンソに哀れみの目を向けた。
「大変ですね」
「元気の良い方でしたね。私は嫌いではありませんが」
「……はぁ」
アロンソの趣味はアギラールには到底理解出来そうになかった。コルテスが笑う。
「ま、今夜は様子見だな。明日には洗礼を受けさせて、暫くしたら出発だ」
「はい」
「アギラール」
ふいに、コルテスは声を低くした。
「もしアロンソがあれを持て余すとしたら、お前いるか?」
「冗談でしょう」
間髪入れず、アギラールは吐き捨てた。
「あれは異教の女です。そもそも、私は神に仕える身です」
「だが、ゲレロはマヤの女に下っただろう」
「……っ」
反射的に何かを叫びかけ、しかしそれは言葉にならなかった。アギラールのその反応を楽しむように、コルテスは深い笑みを顔に刻んだ後ゆっくりと背を向けた。
「未来の事は誰にも判らんさ、アギラール。思い込みはおかしな事態を招く。今その場にあるものを、そのまま見るんだな」
コルテスが部屋を出ていってから、アギラールは目を閉じた。瞼の向こうの闇の中、ゆらゆらと何かが揺れている。
小さく、身体が震えた。嵐の中揺れる舟。天地も判らなくなる感覚。そして、辛酸をなめたあの日々。
閉ざしたい記憶は遠いものではない。つい先日まで、確かに身に降りかかっていた火の粉だ。今こうしてエスパニャの言葉でコルテスと話せることも聖書を読むことも、奇跡と言っていい。
ただ、ゲレロは――かつての友は、その奇跡を自ら手放した。それだけだ。
「アギラール殿」
アロンソの控えめな声が、闇を割ってきた。目を開ける。柔らかな笑みがそこにあった。
「あまり、思いつめなさらぬよう」
それ以上は何も言わず、アロンソも部屋を後にした。二人がいなくなった部屋の中に、まだあの悍ましい記憶が漂っているようでアギラールは再び目を閉じた。
「神よ。貴方は私に何をお望みか」
呟きは、誰にも届かずに消えた。
◇
マリナリは憤っていた。
これからお前たちは奴隷という立場ではない。確かにあの男はマヤ語でそう言ったはずだった。だがその彼が離れると、コルテスが幾人かの男たちを呼びつけた。そしてマリナリたちと男たちを交互に見ながら、男たちに女を渡し始めたのだ。
(あれじゃまるきり家畜と同じじゃない!)
確かにどの男も、奴隷に対する扱いというよりは一人の女性に対する扱いをしてくれているようだった。それはティルパやほかの仲間たちの表情からも判った。しかし、問題はそこではない。選び、配分し、女たちの意思は聞かずに受け渡す。その行為自体が我慢ならなかった。
たまらず一発見舞ってしまったのだが、コルテスは意にも介さなかったようだ。結局マリナリも、穏和そうな男につれられて部屋に入るしかなかった。
今マリナリたちがいるのは、船の中だという。だが、マリナリの知識の中ではこれほど大きな船など、存在していなかった。昨晩、戦の中で見かけた海の上に浮く山はこの船らしかった。
部屋の中、ひとり憤慨し続けるマリナリを余所に、コルテスがあてがった穏和な男は黙々と本を読んでいる。
肩幅が広く、上背もある。戦士なのだろう――腕も脚も太く、しっかりしている。だが、威圧感は殆ど無い男だった。少しばかり目が垂れ気味なせいかもしれない。穏やかに本を読む様子は、軟弱に見えてどうにも気に食わない。マリナリは甲板に出ることにした。男も止めはしなかった。部屋を出るときに少し顔を上げ、曖昧に笑むだけだった。
甲板に出ると、夜風がマリナリを殴りつけた。ふっと、短く息を吐く。肌寒い風だが、それが火照った頭には心地よかった。
ふと、甲板の先に人影があるのを見つけ、マリナリは歩み寄る。そしてあからさまにがっかりした体で呟いて見せた。
「何だ、貴方なの」
「マリナリか」
そこにいたのは金髪の男だった。マヤ語が返ってきて、会話が出来そうなことに悔しいながらも安堵する。
「よく私がいると気付いたな。暗くて見えないと思ったが」
「目はいい方なの」
「そうか」
短い返事の後、男はマリナリから目をそらした。陸の方を見ている。何となくマリナリも隣に並んだ。港の篝火が赤々と燃えている。
「不公平よね」
「何がだ」
マリナリの突然の言葉に、男は陸を見据えたまま答える。
「名前。私貴方の名前も知らないわ。貴方は私を勝手に呼ぶけれど」
「名乗ったのはお前だろう。……まあいい。私はアギラールだ。ヘロニモ・デ・アギラール。アギラールでいい」
「アギラール、ね。変な名前だわ」
短く答える。たとえそれが気に食わない男の名前であったとしても、何も判らないよりはいいだろう。
ふと、マリナリは目を瞠った。視線の先、陸側に揺れる影を見つけたのだ。慌ててきびすを返して走り出す。すぐに、アギラールも追ってきた。
「何事だ。どこへ行く」
「すぐ戻るわよ」
言ったが、アギラールは離れなかった。少々鬱陶しく思いながら、船内を駆けていく。すぐ、外に出た。揺れない足下にほっとする間もなく、マリナリは声をあげた。
「トゥクスアウラ!」
篝火に照らされた人影に走りよる。友は驚きの顔で迎えてくれた。
「マリナリ」
「どうしたの、こんなところに来て」
トゥクスアウラは精悍な顔を緩ませて笑った。マリナリの肩に手を乗せ、眼を覗きこんでくる。
「別れを言いに来た」
「別れ……って、私がここを離れるから? わざわざ?」
マリナリは怪訝に思ってトゥクスアウラを見上げた。
マリナリもトゥクスアウラも、己の立場は理解しているつもりだ。友ではある。だが、いつ互いにどこに連れて行かれ、連絡が取れなくなっても当然だと思っていた。生きていれば、またどこかで遭うこともあるだろう。それがある限り、別れではない。
そこまで考えてから、マリナリは背筋が凍るのを感じた。唇が乾いていく。
「まさか」
生きている限り、別れは言わない。ならば、わざわざ別れを告げに来たのはその逆だということだ。自身の肩に掛けられた手を握り返す。
「トゥクスアウラ!」
「明日、俺の心臓は神に捧げられる」
静かに告げられた言葉が、全身を毒のように駆け巡っていくのが判った。