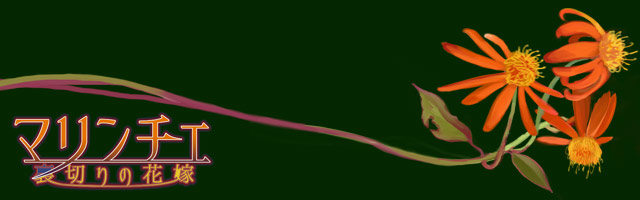Chapter2. 昇る生命 - 3
「貴方たちは……コルテスは本当に、ケツァルコアトルだったのよね」
マリナリの言葉に、アギラールは葡萄酒を傾ける手を止めた。
「何故そう思う」
「何故って……だって貴方、さっき」
神殿の上で確かに朗々と告げたではないか!
早口でマリナリが抗議すると、アギラールは「ああ」と合点がいったというように呟いた。杯を、食卓に置く。
「勘違いしてもらっては困る。私もコルテス殿も、一言もケツァルコアトルだなんて言っていない。我らの神は唯一キリストのみだ」
「なっ……」
思わずマリナリは椅子を蹴って立ち上がった。
「騙したというの!」
「私たちは一言も嘘は告げていない。何も詐称はしていない。あそこの民たちが、勝手に解釈したまでだ」
「ふざけないで……!」
叫ぶ声が、我知らず震えていた。
ふいに、食堂の入口から声がかかった。見ると、コルテスが下卑た笑みを浮かべている。
「――、――」
「――」
コルテスとアギラールが何かを話している。
「貴方はただの人間なの、神なの、何を目的にやってきたというの!」
マヤ語で問いかけたが、コルテスは面倒くさそうに顔をしかめるだけだった。
「この方はお人だ。キューバの総督ベラスケス殿に命じられ、エスパニャよりこの地に来た。この地に、キリストの教えを広めるためだ」
「ただの人間だと、そういうのね。なら、何故あの儀式を潰したの!」
「野蛮な真似だった。それともドニャ・マリーナは友が生贄に捧げられるのを見たかったというのか」
「違う!」
自分でも何を言っているのか、マリナリにはもはや判らなかった。ただ、感情が悲鳴を上げていた。最初から、儀式の始まる前から、コルテスがただの人だと判っていればそもそも儀式は行われなかったかもしれない。それなら、トゥクスアウラは生贄に捧げられなかった。しかし、儀式は始まった。今まさに太陽神ウィツィロポチトリに命が捧げられるところだった。それを、潰したのだ。太陽神は得られるはずのものを目の前で踏み潰された。
コルテスが確かにケツァルコアトルであり、夜の神テスカトリポカと戦うというのであれば、ウィツィロポチトリも許してくれたかもしれない。だが、彼は言ったのだ。
コルテスはケツァルコアトルなどではなく、ただの人である、と。
そうなれば、今晩の神々の戦いは様相を変える。目の前で生贄を取り上げられた太陽神ウィツィロポチトリと、夜の神テスカトリポカの戦いになる。途中まで呼び出しておきながら、生贄を捧げなかった人の行いを、ウィツィロポチトリが、もし、人の裏切りと感じたら。
戦いはテスカトリポカに有利に働くのではないか。
ぞく、と背中に悪寒が走る。マリナリは震える声で呟いた。
「朝が来ない」
「何を言っている」
「朝が来ないかもしれない! 世界は永遠に夜のままになるかもしれないわ!」
不意に、大きな溜息が聞こえた。コルテスだった。相変わらず面倒くさそうな顔で、アギラールにものを告げている。アギラールはアギラールで、早口でコルテスに抗議しているようだ。だが、コルテスが行動に出た。すたすたとマリナリの元へ寄ってきて、腕を取った。そのまま、アギラールの腕もとり、食堂から引きずっていく。抵抗もできないままいると、コルテスは二人を船外へと放り投げた。快活な笑顔で手を振り、船内への扉を閉ざしてしまう。
「な……なんなの、あの男は!」
隣ではアギラールが頭を抱えていた。呻いている。
「な、なによ。どこか傷めたの?」
「……頭が痛いだけだ。まぁ、いい。こい、ドニャ・マリーナ」
アギラールが歩き出した。手近なところで座り、木切れを集めて火を熾し始める。その手つきは慣れているようで、マリナリはなんとなく意外に感じた。
「どうせあの様子ではコルテス殿は朝が来るまで船内へ入れてはくれまい。夜は冷える。近くに寄れ」
確かに、空気は冷たい。ぶるりと身を震わせ、マリナリは自身の肩を抱いた。火はなくとも死にはしないだろうが、寒いのは確かだった。マリナリは渋々、アギラールの起こした火の傍に寄った。
ゆらゆらと揺れる火の熱さを感じながら、マリナリは薄く口を開いた。
「……朝が来るまで、と言ったわね」
「ああ」
「朝は来るの?」
唇から零れた音が、あまりに弱気に聞こえてマリナリ自身驚いてしまった。アギラールもさすがに驚いたのか、空色の目を瞬かせている。
「不安か」
「……だって、あんな」
「安心しろ。朝は来る。寝ていてもいいが」
「眠れないわよ」
「だろうな」
アギラールは軽く頷いた。空を見上げる。月は細い爪のようなものが浮かんでいた。宝玉をばら撒いたかのように星は瞬いている。
「――ここの空気は澄んでいるのだな。星が美しい」
「貴方達の国ではこうではないの?」
「街並みは美しい。だが、そうだな、こういった景色は失われつつあったかもしれない。私は久しく目にしていないが」
ぱちっ、と木が爆ぜた。赤い炎に照らされるアギラールを見やりながら、マリナリは軽く首を傾げた。
「何故?」
「八年前になるか」
ふ、とアギラールが口元を緩めた。
「私たちは船に乗っていた。だが、酷い嵐に見舞われた。船は難破し、ここにたどり着いた」
「では、貴方はコルテスと一緒に来たのではないの?」
「彼より随分先に来ているさ。でなければドニャ・マリーナ。こんな風にお前と話せもしないだろう」
流暢なマヤ語で言われ、マリナリとしては納得するしかなかった。
「岸にたどり着いたときは二十人ほど仲間がいた。だが、私たちは捕まった。マヤの民にな」
「捕虜ね」
「ああ。だから知ってはいたんだ。生贄の風習があることは。マヤのはな」
マリナリは頷いた。このあたりは一般的にマヤ族の支配する土地だ。タバスコは前述した通り首長がアステカ帝国の王、モクテスマ二世に不思議と対抗心を燃やしているせいで、マヤの風習よりアステカの風習のほうが色濃く根付いている。だが、マヤとアステカの生贄の儀式は違いがある。マヤの生贄の儀式を知っていたとしても、アステカの風習としての生贄の儀式は、アギラールは知らなかったのだろう。
「捕まっている間、ずっとキリストの暦を数えていた。ひとりひとり、仲間たちは生贄に捧げられていった。諦めるものもいた。だが、いつかエスパニャからの救いが来ると信じていた。その願いを、暦を数えることに託していたんだ」
「そっちの暦では、今は何年になるの。何か予言はあるの」
「予言はないな。今年は一五一九年。今は三月だ。間もなく四月になる。私がコルテス殿と合流したのは二月の水曜日だった」
「よく判らない」
「まぁ、そうだろうな。私たちは暦に祈りを重ねていた。残った仲間は私ともう一人だった。私はエスパニャの使いが来たと聞いて、命からがら逃げ出し、この軍と合流したんだ」
「もう一人は?」
アギラールは答えなかった。ただ、火を見つめている。マリナリは肩をすくめてやり過ごした。無理やり聞き出そうとも思わない。
「昼に言っていた、コルテスが恩人とはそういうこと? 貴方をマヤの民から救ったから?」
「ああ。私が生贄にならずにすんだのは、奴隷として働いていたからだった。ドニャ・マリーナ。お前の立場と同じだ。コルテス殿に、普通の人間としての尊厳を与えて貰った」
今度はマリナリが答えなかった。奴隷であったとしても、尊厳はあっていい。マリナリの思考とアギラールの思考には隔たりがあるように思えたからだ。
「――朝は来る」
マリナリの沈黙を、アギラールは不安と受け取ったようだった。突然そう断言すると、彼はぎこちなく笑みを浮かべた。
「必ず来る。コルテス殿が私たちを外に出したのは、それを見させるためだ。ドニャ・マリーナ。お前にも朝は来るんだ」
マリナリの言葉に、アギラールは葡萄酒を傾ける手を止めた。
「何故そう思う」
「何故って……だって貴方、さっき」
神殿の上で確かに朗々と告げたではないか!
早口でマリナリが抗議すると、アギラールは「ああ」と合点がいったというように呟いた。杯を、食卓に置く。
「勘違いしてもらっては困る。私もコルテス殿も、一言もケツァルコアトルだなんて言っていない。我らの神は唯一キリストのみだ」
「なっ……」
思わずマリナリは椅子を蹴って立ち上がった。
「騙したというの!」
「私たちは一言も嘘は告げていない。何も詐称はしていない。あそこの民たちが、勝手に解釈したまでだ」
「ふざけないで……!」
叫ぶ声が、我知らず震えていた。
ふいに、食堂の入口から声がかかった。見ると、コルテスが下卑た笑みを浮かべている。
「――、――」
「――」
コルテスとアギラールが何かを話している。
「貴方はただの人間なの、神なの、何を目的にやってきたというの!」
マヤ語で問いかけたが、コルテスは面倒くさそうに顔をしかめるだけだった。
「この方はお人だ。キューバの総督ベラスケス殿に命じられ、エスパニャよりこの地に来た。この地に、キリストの教えを広めるためだ」
「ただの人間だと、そういうのね。なら、何故あの儀式を潰したの!」
「野蛮な真似だった。それともドニャ・マリーナは友が生贄に捧げられるのを見たかったというのか」
「違う!」
自分でも何を言っているのか、マリナリにはもはや判らなかった。ただ、感情が悲鳴を上げていた。最初から、儀式の始まる前から、コルテスがただの人だと判っていればそもそも儀式は行われなかったかもしれない。それなら、トゥクスアウラは生贄に捧げられなかった。しかし、儀式は始まった。今まさに太陽神ウィツィロポチトリに命が捧げられるところだった。それを、潰したのだ。太陽神は得られるはずのものを目の前で踏み潰された。
コルテスが確かにケツァルコアトルであり、夜の神テスカトリポカと戦うというのであれば、ウィツィロポチトリも許してくれたかもしれない。だが、彼は言ったのだ。
コルテスはケツァルコアトルなどではなく、ただの人である、と。
そうなれば、今晩の神々の戦いは様相を変える。目の前で生贄を取り上げられた太陽神ウィツィロポチトリと、夜の神テスカトリポカの戦いになる。途中まで呼び出しておきながら、生贄を捧げなかった人の行いを、ウィツィロポチトリが、もし、人の裏切りと感じたら。
戦いはテスカトリポカに有利に働くのではないか。
ぞく、と背中に悪寒が走る。マリナリは震える声で呟いた。
「朝が来ない」
「何を言っている」
「朝が来ないかもしれない! 世界は永遠に夜のままになるかもしれないわ!」
不意に、大きな溜息が聞こえた。コルテスだった。相変わらず面倒くさそうな顔で、アギラールにものを告げている。アギラールはアギラールで、早口でコルテスに抗議しているようだ。だが、コルテスが行動に出た。すたすたとマリナリの元へ寄ってきて、腕を取った。そのまま、アギラールの腕もとり、食堂から引きずっていく。抵抗もできないままいると、コルテスは二人を船外へと放り投げた。快活な笑顔で手を振り、船内への扉を閉ざしてしまう。
「な……なんなの、あの男は!」
隣ではアギラールが頭を抱えていた。呻いている。
「な、なによ。どこか傷めたの?」
「……頭が痛いだけだ。まぁ、いい。こい、ドニャ・マリーナ」
アギラールが歩き出した。手近なところで座り、木切れを集めて火を熾し始める。その手つきは慣れているようで、マリナリはなんとなく意外に感じた。
「どうせあの様子ではコルテス殿は朝が来るまで船内へ入れてはくれまい。夜は冷える。近くに寄れ」
確かに、空気は冷たい。ぶるりと身を震わせ、マリナリは自身の肩を抱いた。火はなくとも死にはしないだろうが、寒いのは確かだった。マリナリは渋々、アギラールの起こした火の傍に寄った。
ゆらゆらと揺れる火の熱さを感じながら、マリナリは薄く口を開いた。
「……朝が来るまで、と言ったわね」
「ああ」
「朝は来るの?」
唇から零れた音が、あまりに弱気に聞こえてマリナリ自身驚いてしまった。アギラールもさすがに驚いたのか、空色の目を瞬かせている。
「不安か」
「……だって、あんな」
「安心しろ。朝は来る。寝ていてもいいが」
「眠れないわよ」
「だろうな」
アギラールは軽く頷いた。空を見上げる。月は細い爪のようなものが浮かんでいた。宝玉をばら撒いたかのように星は瞬いている。
「――ここの空気は澄んでいるのだな。星が美しい」
「貴方達の国ではこうではないの?」
「街並みは美しい。だが、そうだな、こういった景色は失われつつあったかもしれない。私は久しく目にしていないが」
ぱちっ、と木が爆ぜた。赤い炎に照らされるアギラールを見やりながら、マリナリは軽く首を傾げた。
「何故?」
「八年前になるか」
ふ、とアギラールが口元を緩めた。
「私たちは船に乗っていた。だが、酷い嵐に見舞われた。船は難破し、ここにたどり着いた」
「では、貴方はコルテスと一緒に来たのではないの?」
「彼より随分先に来ているさ。でなければドニャ・マリーナ。こんな風にお前と話せもしないだろう」
流暢なマヤ語で言われ、マリナリとしては納得するしかなかった。
「岸にたどり着いたときは二十人ほど仲間がいた。だが、私たちは捕まった。マヤの民にな」
「捕虜ね」
「ああ。だから知ってはいたんだ。生贄の風習があることは。マヤのはな」
マリナリは頷いた。このあたりは一般的にマヤ族の支配する土地だ。タバスコは前述した通り首長がアステカ帝国の王、モクテスマ二世に不思議と対抗心を燃やしているせいで、マヤの風習よりアステカの風習のほうが色濃く根付いている。だが、マヤとアステカの生贄の儀式は違いがある。マヤの生贄の儀式を知っていたとしても、アステカの風習としての生贄の儀式は、アギラールは知らなかったのだろう。
「捕まっている間、ずっとキリストの暦を数えていた。ひとりひとり、仲間たちは生贄に捧げられていった。諦めるものもいた。だが、いつかエスパニャからの救いが来ると信じていた。その願いを、暦を数えることに託していたんだ」
「そっちの暦では、今は何年になるの。何か予言はあるの」
「予言はないな。今年は一五一九年。今は三月だ。間もなく四月になる。私がコルテス殿と合流したのは二月の水曜日だった」
「よく判らない」
「まぁ、そうだろうな。私たちは暦に祈りを重ねていた。残った仲間は私ともう一人だった。私はエスパニャの使いが来たと聞いて、命からがら逃げ出し、この軍と合流したんだ」
「もう一人は?」
アギラールは答えなかった。ただ、火を見つめている。マリナリは肩をすくめてやり過ごした。無理やり聞き出そうとも思わない。
「昼に言っていた、コルテスが恩人とはそういうこと? 貴方をマヤの民から救ったから?」
「ああ。私が生贄にならずにすんだのは、奴隷として働いていたからだった。ドニャ・マリーナ。お前の立場と同じだ。コルテス殿に、普通の人間としての尊厳を与えて貰った」
今度はマリナリが答えなかった。奴隷であったとしても、尊厳はあっていい。マリナリの思考とアギラールの思考には隔たりがあるように思えたからだ。
「――朝は来る」
マリナリの沈黙を、アギラールは不安と受け取ったようだった。突然そう断言すると、彼はぎこちなく笑みを浮かべた。
「必ず来る。コルテス殿が私たちを外に出したのは、それを見させるためだ。ドニャ・マリーナ。お前にも朝は来るんだ」