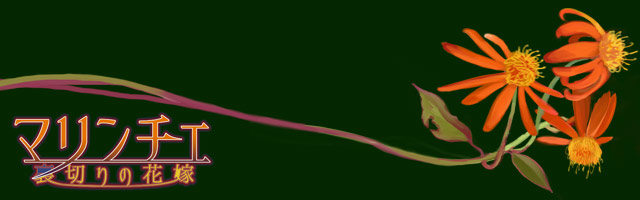Chapter2. 昇る生命 - 4
◇
小舟が滑るように海を進んだ。冷気を放つ水面は明けの前には静かだった。時折波が来る程度で、小舟を拒もうとはしない。顔を上げると白々とした星が輝いていた。まだ天蓋は濃く深い夜の色を宿している。ある程度まで沖に出ると、アギラールはその場で小舟を留めた。ふっと、短く息を吐く。ここで待つということだろう。問わずとも判った。凍える指先に息を当てながら、マリナリは静かに時を待った。船をここまで漕いできたアギラールも、ただ黙ってその時を待っている。
あの海の向こう、見えない場所で神々は戦を行っている。
神々の戦は、もう終わっただろうか。
微かな波に、小舟が揺れている。ふわり、ふわりと揺れる感覚が、まるで夢の中のようにマリナリは感じた。
ふと、思い出す。いつだったかこんな風に朝を待ったことがある。いつだっただろうか――と考えて、思い出す。生まれ育った街を出ることになったあの日だ。
あの日。マリナリが、死んだ日。
自らの胸中に浮かんだ言葉に、マリナリはアギラールに見つからない程度に笑んだ。あの時は、朝が来るのが怖かった。朝が来れば、全てを失うと思っていたからだ。ウィツィロポチトリの負けを祈りさえした。
でも、朝は来た。
あの日、朝は来たのだ。
息を吐く。吐息さえ冷たくなっている。けれど、マリナリはただ待った。
静かだった。ときどきぱしゃんと船べりに水音がはねる。ちちち、と甲高い鳥の声がした。水の匂いが鼻に痛い。
理屈ではなく、ただアギラールは断言した。朝は来る。その言葉を信じ切れたわけでもない。だが、すがるしかなかった。
風が吹いた。水の向こうから、陸へ。まるでその風を追うように空が徐々に色を取り戻していく。黒は藍へ。藍は青へ。
闇を追い出し、光が世界を満たしていく。熱を感じた。それは、ぬくもりだ。凍えきっていた指先がじんとしびれていく。
マリナリは息を止めていた。目を瞠る。
夜。朝。神々。テスカトリポカ。ウィツィロポチトリ。ケツァルコアトル。色々な単語が脳内を駆け巡った。鼓動が一層、早くなる。
「見ろ、ドニャ・マリーナ」
アギラールがマリナリの顎に手をかけ、東の果て、海の向こうへと顔を向けさせた。
「夜明けだ」
それはまるで、心臓のようだった。
赤く燃える心臓が、海の向こうから昇ってくる。やがてそれは命の熱を世界へと渡らせていく。空が色を変えた。世界が息づき始める。鳥の声がした。水の音がした。風の音がした。生き物の声がした。燃え上がる空が、眩く光りだす。
「ああ……」
思わず、声が出た。同時に涙もこぼれていた。安堵なのか、それ以外の何かなのか、マリナリは自分でも判らなかった。ただ、夜明けが来た事実だけがそこにあった。
「誰の犠牲もなくても、陽は平等に誰の頭上にも昇る」
――誰の犠牲もなくても。
アギラールのその言葉が、朝焼けの中でただ残り続けた。
◇
朝だった。雲ひとつ無く晴れ渡った春の空を映し、海もまた煌めいている。出航の準備に、人々はざわめいていた。指示を出す声、答える声、時々は怒声さえ聞こえてくる。遠く、タバスコの街の活気も潮風に乗って感じ取れた。
眼下では戦士たちが、忙しそうに荷を運んでいる。甲板の上、マリナリはじっとその光景を見つめていた。
「ドニャ・マリーナ。何をしている」
アギラールの声に、マリナリは振り返った。彼もまた準備をしていたのだろう。いくつか、大きな巻物を抱えていた。少し重そうだ。
吹き付ける潮風に煩わしそうに顔を顰め、アギラールは口を開く。
「ディアナが探していたぞ」
ディアナ、とはティルパの新しい名だ。なんでもないと答えようとして、ふとマリナリは違和感を覚えた。
「ねぇ、アギラール。訊いてもいいかしら」
「なんだ」
アギラールはあからさまに迷惑そうな顔をした。マリナリはその表情に気が付かないことにした。しれっと、続ける。
「ティルパはディアナ、だけなの? 何故私はドニャ・マリーナ? ドニャって何?」
問いかけにアギラールが少し顔をしかめた。
「コルテス殿の提案だ。お前は随分と自尊心の高い女のようだから、とな」
「どういう意味?」
「ドニャは敬称だ」
アギラールはあまり気に入っていないのか、少し不貞腐れた様子ではあった。そのまま、背を向けて歩き出す。マリナリは、その様子が何となくおかしかった。思わず口元が緩んでしまう。
「ねぇ、アギラール」
歩き去ろうとする背に呼びかける。
「私は私の意思で、貴方達についていくわ」
アギラールの足が止まった。金色の髪が揺れて振り返る。
「何の話だ?」
「貴方が言う自尊心の話よ。それに貴方が言ったのよ。もう奴隷ではないって。望むものは欲していいって」
風が吹く。潮の匂いが心地よかった。
とんっ、と一歩、足を前に踏み出す。甲板の木の冷たい感触が心地よい。
「だから私は、私の意思で貴方達についていくことを今決めたの。貴方達のものだからじゃない。私は知りたいのよ。今日朝が来たのは偶然なのかもしれない。異例な出来事なのかもしれない。本当に、誰の犠牲もなくても、朝は来るのか確かめたいの。貴方達に付いて行けば、判るのでしょう」
「――ああ」
マリナリは満足気に微笑んでみせた。
「それが、私の最初の望むもの。それから、名前ね」
ぐっと空に手を伸ばした。どこまでも高く青い。船出日和だった。その空を見上げながら、告げる。
「マリナリって名前、故郷の言葉で炭の草って意味なの」
「炭の草?」
空に手を伸ばしながら、アギラールに背を向けた。陸が見える。空、大地、それから、海。全てが繋がっていることが、今はなんとなく不思議で楽しかった。
「生まれが良くないんですって。贖罪の意味もあるらしいわ。だからね、正直あまり好いてはいなかったの。でもね、マリーナ? そんな風に勝手に名付けられたのも気に入らないわ」
「我儘だな」
「ええ。我儘になることにするの」
不思議と、心が弾んでいるのをマリナリは感じていた。ぐっと、空に向かって伸ばしていた手を拳に握った。何かを、手に出来た気がした。振り返る。
「――マリンチェ」
「マリンチェ?」
「私の故郷の言葉で、ドニャ・マリーナはそうなるのよ。マリンチェ。素敵だと思わない?」
潮風が、黒髪を揺らしていく。
「私は今日からマリンチェになる。そして、私は私の意思で貴方達についていく。そう決めたのよ」
船員が声を張り上げはじめた。カーン、カーンと甲高い鐘の音が鳴り響き、船が港を離れ始める。
アギラールは少しの間あっけにとられたかのように呆然としていたが、ややあってから相好を崩した。
「いいだろう。――マリンチェ」
頷く。
「出航だ」
一の葦の年、春。
奴隷の娘マリナリは――否、マリンチェは、甲板の上で大きく笑った。
小舟が滑るように海を進んだ。冷気を放つ水面は明けの前には静かだった。時折波が来る程度で、小舟を拒もうとはしない。顔を上げると白々とした星が輝いていた。まだ天蓋は濃く深い夜の色を宿している。ある程度まで沖に出ると、アギラールはその場で小舟を留めた。ふっと、短く息を吐く。ここで待つということだろう。問わずとも判った。凍える指先に息を当てながら、マリナリは静かに時を待った。船をここまで漕いできたアギラールも、ただ黙ってその時を待っている。
あの海の向こう、見えない場所で神々は戦を行っている。
神々の戦は、もう終わっただろうか。
微かな波に、小舟が揺れている。ふわり、ふわりと揺れる感覚が、まるで夢の中のようにマリナリは感じた。
ふと、思い出す。いつだったかこんな風に朝を待ったことがある。いつだっただろうか――と考えて、思い出す。生まれ育った街を出ることになったあの日だ。
あの日。マリナリが、死んだ日。
自らの胸中に浮かんだ言葉に、マリナリはアギラールに見つからない程度に笑んだ。あの時は、朝が来るのが怖かった。朝が来れば、全てを失うと思っていたからだ。ウィツィロポチトリの負けを祈りさえした。
でも、朝は来た。
あの日、朝は来たのだ。
息を吐く。吐息さえ冷たくなっている。けれど、マリナリはただ待った。
静かだった。ときどきぱしゃんと船べりに水音がはねる。ちちち、と甲高い鳥の声がした。水の匂いが鼻に痛い。
理屈ではなく、ただアギラールは断言した。朝は来る。その言葉を信じ切れたわけでもない。だが、すがるしかなかった。
風が吹いた。水の向こうから、陸へ。まるでその風を追うように空が徐々に色を取り戻していく。黒は藍へ。藍は青へ。
闇を追い出し、光が世界を満たしていく。熱を感じた。それは、ぬくもりだ。凍えきっていた指先がじんとしびれていく。
マリナリは息を止めていた。目を瞠る。
夜。朝。神々。テスカトリポカ。ウィツィロポチトリ。ケツァルコアトル。色々な単語が脳内を駆け巡った。鼓動が一層、早くなる。
「見ろ、ドニャ・マリーナ」
アギラールがマリナリの顎に手をかけ、東の果て、海の向こうへと顔を向けさせた。
「夜明けだ」
それはまるで、心臓のようだった。
赤く燃える心臓が、海の向こうから昇ってくる。やがてそれは命の熱を世界へと渡らせていく。空が色を変えた。世界が息づき始める。鳥の声がした。水の音がした。風の音がした。生き物の声がした。燃え上がる空が、眩く光りだす。
「ああ……」
思わず、声が出た。同時に涙もこぼれていた。安堵なのか、それ以外の何かなのか、マリナリは自分でも判らなかった。ただ、夜明けが来た事実だけがそこにあった。
「誰の犠牲もなくても、陽は平等に誰の頭上にも昇る」
――誰の犠牲もなくても。
アギラールのその言葉が、朝焼けの中でただ残り続けた。
◇
朝だった。雲ひとつ無く晴れ渡った春の空を映し、海もまた煌めいている。出航の準備に、人々はざわめいていた。指示を出す声、答える声、時々は怒声さえ聞こえてくる。遠く、タバスコの街の活気も潮風に乗って感じ取れた。
眼下では戦士たちが、忙しそうに荷を運んでいる。甲板の上、マリナリはじっとその光景を見つめていた。
「ドニャ・マリーナ。何をしている」
アギラールの声に、マリナリは振り返った。彼もまた準備をしていたのだろう。いくつか、大きな巻物を抱えていた。少し重そうだ。
吹き付ける潮風に煩わしそうに顔を顰め、アギラールは口を開く。
「ディアナが探していたぞ」
ディアナ、とはティルパの新しい名だ。なんでもないと答えようとして、ふとマリナリは違和感を覚えた。
「ねぇ、アギラール。訊いてもいいかしら」
「なんだ」
アギラールはあからさまに迷惑そうな顔をした。マリナリはその表情に気が付かないことにした。しれっと、続ける。
「ティルパはディアナ、だけなの? 何故私はドニャ・マリーナ? ドニャって何?」
問いかけにアギラールが少し顔をしかめた。
「コルテス殿の提案だ。お前は随分と自尊心の高い女のようだから、とな」
「どういう意味?」
「ドニャは敬称だ」
アギラールはあまり気に入っていないのか、少し不貞腐れた様子ではあった。そのまま、背を向けて歩き出す。マリナリは、その様子が何となくおかしかった。思わず口元が緩んでしまう。
「ねぇ、アギラール」
歩き去ろうとする背に呼びかける。
「私は私の意思で、貴方達についていくわ」
アギラールの足が止まった。金色の髪が揺れて振り返る。
「何の話だ?」
「貴方が言う自尊心の話よ。それに貴方が言ったのよ。もう奴隷ではないって。望むものは欲していいって」
風が吹く。潮の匂いが心地よかった。
とんっ、と一歩、足を前に踏み出す。甲板の木の冷たい感触が心地よい。
「だから私は、私の意思で貴方達についていくことを今決めたの。貴方達のものだからじゃない。私は知りたいのよ。今日朝が来たのは偶然なのかもしれない。異例な出来事なのかもしれない。本当に、誰の犠牲もなくても、朝は来るのか確かめたいの。貴方達に付いて行けば、判るのでしょう」
「――ああ」
マリナリは満足気に微笑んでみせた。
「それが、私の最初の望むもの。それから、名前ね」
ぐっと空に手を伸ばした。どこまでも高く青い。船出日和だった。その空を見上げながら、告げる。
「マリナリって名前、故郷の言葉で炭の草って意味なの」
「炭の草?」
空に手を伸ばしながら、アギラールに背を向けた。陸が見える。空、大地、それから、海。全てが繋がっていることが、今はなんとなく不思議で楽しかった。
「生まれが良くないんですって。贖罪の意味もあるらしいわ。だからね、正直あまり好いてはいなかったの。でもね、マリーナ? そんな風に勝手に名付けられたのも気に入らないわ」
「我儘だな」
「ええ。我儘になることにするの」
不思議と、心が弾んでいるのをマリナリは感じていた。ぐっと、空に向かって伸ばしていた手を拳に握った。何かを、手に出来た気がした。振り返る。
「――マリンチェ」
「マリンチェ?」
「私の故郷の言葉で、ドニャ・マリーナはそうなるのよ。マリンチェ。素敵だと思わない?」
潮風が、黒髪を揺らしていく。
「私は今日からマリンチェになる。そして、私は私の意思で貴方達についていく。そう決めたのよ」
船員が声を張り上げはじめた。カーン、カーンと甲高い鐘の音が鳴り響き、船が港を離れ始める。
アギラールは少しの間あっけにとられたかのように呆然としていたが、ややあってから相好を崩した。
「いいだろう。――マリンチェ」
頷く。
「出航だ」
一の葦の年、春。
奴隷の娘マリナリは――否、マリンチェは、甲板の上で大きく笑った。