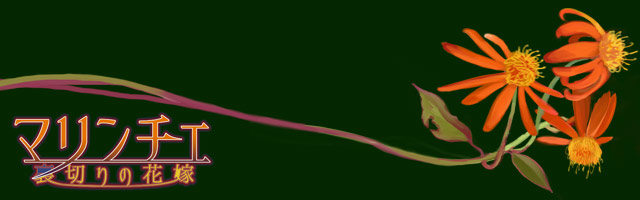Chapter3. 犠牲と覚悟 - 3
コルテスはいったんここで足場を固めてから先へ進むと決めたようだった。サン・フアン・デ・ウルア島から陸地はすぐそこだ。上陸し、そこにも野営地を広げ始めた。
それから幾日か過ぎた頃、異変があった。
二十名ほどの現地の民が、コルテス軍を訪ねてきたのだ。ところが、現地の民の銘々に騒ぐ言葉がマリンチェにすら一言も判らなかった。ざわめく陣中で、マリンチェは友のディアナ――かつてのティルパ――が首を傾げるのを見た。
「あれ、マヤ語じゃないね」
「ナワトル語でもないわよ。どこの言葉かしら」
「たぶんトトナカー」
「ディアナ知ってるの?」
「昔ちょっとだけあのへんに売られたことあるよ。言葉覚えるほど長くはいなかったんだけど。このもうちょっと奥のほうの土地だと思うけど」
ディアナの言葉に、マリンチェは短く頷いた。困りながら、とりあえずナワトル語で、マヤ語かナワトル語を話せる人物はいないかと問うた。一人だけ、前に出てきた。眉の太い、いかつい顔立ちの青年だった。
「ナワトル語なら、少し判る。トトナカ語は駄目か」
「助かるわ。こっちには一人も、トトナカ語を話せる人物はいない。貴方達はどこの人? 何の目的で来たのか教えてちょうだい」
「私たちはこの奥にあるセンポアランの街からきた。この隊の長と話がしたいと、我らの首長がおっしゃっている」
マリンチェはすぐにアギラールを通じてコルテスに告げた。コルテスは迷わず会うことを選んだようだった。通訳としてマリンチェとアギラール、記録係としてベルナル・ディアス。そして、ペドロ。コルテスが選んだのはこの四人だった。アロンソは留守を任されていた。
「アロンソは置いていくのに、ペドロは連れて行くのね」
マリンチェの言葉に、アギラールが小さく笑った。
「どちらも、深くコルテス殿に信頼されている。傍に置いておくべきか、留守を任せるべきか。ここはアロンソ殿が留守を任すのに適任だとお思いになったのだろう」
センポアランへの道のりはそう厳しくはなかった。一両日ほどの行進でその街にたどり着いた。
センポアランは綺麗な街だった。街は区画ごとに分けられ、色とりどりの花が植えられている。
アギラールが感嘆の声を漏らした。
「美しい街だな」
「センポアランはこれでも田舎よ。テノチティトランはもっとすごいわ」
「行ったことがあるのか」
「昔、少しの間住んでいたわ」
詳しく語るつもりもなかった。アギラールも特にそれ以上訊いては来なかった。
区画の中には神殿もあった。儀式は行われていなかったが、黒黒とした血の染みはあった。ペドロは唾棄こそしなかったものの、あからさまに嫌悪感を示していた。首長の家は奥にあった。そこでマリンチェたちを出迎えたのは大柄な男だった。
センポアランの首長はトトナカ語しか話さなかった。結局会談は、最初に現れたぎこちないながらもナワトル語を話すあの使者――オルコネア、と名乗った――マリンチェ、アギラール、と間に幾人も挟む格好で進められた。
「……これ、意味ちゃんと間違えなく通じるかどうか不安よ、私は。こっちのひと、ナワトル語ぎこちないし」
「私もだ」
アギラールも多少困惑していたが、なんとか会談は進められた。ただし、非常に時は要したため、終わる頃にはマリンチェもアギラールもぐったりしていた。
センポアランの首長はただ、助けを求めに来ていただけだった。
センポアランはアステカから一応は独立していたが、それでもアステカの重い租税からは逃れられていなかった。金、トウモロコシ、カカオ、奴隷。ありとあらゆるものを、租税として持っていかれると嘆いていたのだ。訳しながら、マリンチェは胸の奥でずきずきと古傷が痛むのを覚えた。
コルテスはあくまで私は友好と貿易のためにこの地に来たのであって、モクテスマ殿と敵対しようとは欠片も思っていない、と告げた。その上で、虐げられているものを放っておくのは、我らの神が許さない、とも言った。迷った末、マリンチェはそれはそのまま訳した。帰ってきた神ケツァルコアトルの名を持ちださなくとも大丈夫そうだと判断したからだ。実際、センポアランの首長は貴方方の神は心がお広くあられる、と言っただけだった。
「力になれるかどうかは判らない。だが、友となろう」
会談は、コルテスのこの一言と抱擁で幕を下ろした。すぐに宴が始まり、コルテス達一軍は歓迎された。振舞われたプルケ酒を、しかしコルテスはあまり好まなかったようだ。
夜が更けはじめた頃、マリンチェはまたその宴から席を外した。すぐにアギラールもついてきた。
「大丈夫か」
「……何がよ。何でついてくるの」
「気になった」
端的に答え、アギラールはマリンチェの隣に並んできた。街の人々は、得体のしれない来訪者を影から伺っているようだった。ちらちらと感じる視線を振り払うように、マリンチェは足を進めた。しかし、途中で諦めた。適当に歩き、広場の隅に腰を下ろした。
「綺麗な街だ」
アギラールが隣に座りながら呟いた。ちらりと横目で見てから、マリンチェは溜息を吐いた。
「何で私に構うの。鬱陶しいわ」
「お前にはエスパニャ語を教えなければならん。コルテス殿が気にかけろと仰せだしな」
「ああそう」
実直すぎるアギラールに、マリンチェは嘆息しかでなかった。アギラールは少し声を潜めた。
「何かあっただろう」
「ないわよ、別に」
「では、訊き方を変える。何故モクテスマ殿は嫌われている? これだけの土地を治める王なのだろう? しかしここの首長もタバスコの首長も、マリンチェ、お前もあまりいい印象は持っていないようだ」
「それは」
少し、言いよどんだ。他の視線も気にはなったが、ふと、マヤ語なら判らないはずだと気が付いた。些細な事が安堵のひとつとなる。
「――私の故郷も、ここと同じだったの」
「故郷」
「ええ。パイナラという小さな街だった。父は首長だったわ」
アギラールが怪訝な顔をした。
「何故、その娘がタバスコで奴隷など」
「さあね」
答える義理はない。マリンチェは軽くいなして、顔を空へ向けた。澄んだ空気が肺を満たしていく。
「小さな街だった。だけど、好きだったわ。豊かな土地だったの。トウモロコシも、豆も、果実もたくさん実ったわ。陽射しはきつかったけれど、ここと同じに海からの風が入ってきていた。だけど、そうね、豊かだったのがいけなかったのよ。とても大きな税を課せられていたの」
その頃マリンチェはテノチティトランに留学していた。時折帰郷する度、父の顔が痩けていっていたのを嫌でも覚えているのだ。それでも父はマリンチェをテノチティトランへ送り出した。華やかなりしアステカの都で勉学を嗜むことこそ、名家の子女としての努めだといっていた。
くしゃり、と頭をなでる父の大きな手を思い出し、マリンチェはそっと唇を噛み締めた。
「父は苦しんでいたわ。とても民思いの首長だったのに、いいえ、だったからこそ、モクテスマの課す税と、街を機能させるのとの間で苦しんでいた」
「そうか。それでモクテスマ殿が」
「嫌いよ。口に出して言うとひどく叱られたけれどね」
細く長く、息を吐いた。そうすることで、胸のつかえを少し解こうとした。
「ここはパイナラと同じなのよ。そしてたぶん、こんな思いをしているのはここだけでもパイナラだけでもない。アステカは大きな国よ。だけど大きいからこそきっと綻びもある」
アギラールは短く頷いた。
その時だった。二人の男が走り寄ってきて鋭い口調で何かを言った。
「――!」
「――、――!」
トトナカ語だ。話す内容は判らない。だが、その口振りはただごとではなかった。男たちの顔に覚えはある。首長の傍に仕えていた者たちだ。マリンチェとアギラールは一瞬顔を見合わせる。
「――!」
男たちがまた何か叫んだ。身振り手振りで、傍の建物の陰に誘導してくる。ふと、気付いた。先ほどまであった好奇の視線が全て途絶えている。感じる気配は怯えのそれだった。何が起きたのか、それはすぐに知れた。街の入口の方から大仰な格好をした行列が現れたのだ。
先頭に掲げられた旗を見てマリンチェは息を呑んだ。
(モクテスマの税徴収人……!)
それから幾日か過ぎた頃、異変があった。
二十名ほどの現地の民が、コルテス軍を訪ねてきたのだ。ところが、現地の民の銘々に騒ぐ言葉がマリンチェにすら一言も判らなかった。ざわめく陣中で、マリンチェは友のディアナ――かつてのティルパ――が首を傾げるのを見た。
「あれ、マヤ語じゃないね」
「ナワトル語でもないわよ。どこの言葉かしら」
「たぶんトトナカー」
「ディアナ知ってるの?」
「昔ちょっとだけあのへんに売られたことあるよ。言葉覚えるほど長くはいなかったんだけど。このもうちょっと奥のほうの土地だと思うけど」
ディアナの言葉に、マリンチェは短く頷いた。困りながら、とりあえずナワトル語で、マヤ語かナワトル語を話せる人物はいないかと問うた。一人だけ、前に出てきた。眉の太い、いかつい顔立ちの青年だった。
「ナワトル語なら、少し判る。トトナカ語は駄目か」
「助かるわ。こっちには一人も、トトナカ語を話せる人物はいない。貴方達はどこの人? 何の目的で来たのか教えてちょうだい」
「私たちはこの奥にあるセンポアランの街からきた。この隊の長と話がしたいと、我らの首長がおっしゃっている」
マリンチェはすぐにアギラールを通じてコルテスに告げた。コルテスは迷わず会うことを選んだようだった。通訳としてマリンチェとアギラール、記録係としてベルナル・ディアス。そして、ペドロ。コルテスが選んだのはこの四人だった。アロンソは留守を任されていた。
「アロンソは置いていくのに、ペドロは連れて行くのね」
マリンチェの言葉に、アギラールが小さく笑った。
「どちらも、深くコルテス殿に信頼されている。傍に置いておくべきか、留守を任せるべきか。ここはアロンソ殿が留守を任すのに適任だとお思いになったのだろう」
センポアランへの道のりはそう厳しくはなかった。一両日ほどの行進でその街にたどり着いた。
センポアランは綺麗な街だった。街は区画ごとに分けられ、色とりどりの花が植えられている。
アギラールが感嘆の声を漏らした。
「美しい街だな」
「センポアランはこれでも田舎よ。テノチティトランはもっとすごいわ」
「行ったことがあるのか」
「昔、少しの間住んでいたわ」
詳しく語るつもりもなかった。アギラールも特にそれ以上訊いては来なかった。
区画の中には神殿もあった。儀式は行われていなかったが、黒黒とした血の染みはあった。ペドロは唾棄こそしなかったものの、あからさまに嫌悪感を示していた。首長の家は奥にあった。そこでマリンチェたちを出迎えたのは大柄な男だった。
センポアランの首長はトトナカ語しか話さなかった。結局会談は、最初に現れたぎこちないながらもナワトル語を話すあの使者――オルコネア、と名乗った――マリンチェ、アギラール、と間に幾人も挟む格好で進められた。
「……これ、意味ちゃんと間違えなく通じるかどうか不安よ、私は。こっちのひと、ナワトル語ぎこちないし」
「私もだ」
アギラールも多少困惑していたが、なんとか会談は進められた。ただし、非常に時は要したため、終わる頃にはマリンチェもアギラールもぐったりしていた。
センポアランの首長はただ、助けを求めに来ていただけだった。
センポアランはアステカから一応は独立していたが、それでもアステカの重い租税からは逃れられていなかった。金、トウモロコシ、カカオ、奴隷。ありとあらゆるものを、租税として持っていかれると嘆いていたのだ。訳しながら、マリンチェは胸の奥でずきずきと古傷が痛むのを覚えた。
コルテスはあくまで私は友好と貿易のためにこの地に来たのであって、モクテスマ殿と敵対しようとは欠片も思っていない、と告げた。その上で、虐げられているものを放っておくのは、我らの神が許さない、とも言った。迷った末、マリンチェはそれはそのまま訳した。帰ってきた神ケツァルコアトルの名を持ちださなくとも大丈夫そうだと判断したからだ。実際、センポアランの首長は貴方方の神は心がお広くあられる、と言っただけだった。
「力になれるかどうかは判らない。だが、友となろう」
会談は、コルテスのこの一言と抱擁で幕を下ろした。すぐに宴が始まり、コルテス達一軍は歓迎された。振舞われたプルケ酒を、しかしコルテスはあまり好まなかったようだ。
夜が更けはじめた頃、マリンチェはまたその宴から席を外した。すぐにアギラールもついてきた。
「大丈夫か」
「……何がよ。何でついてくるの」
「気になった」
端的に答え、アギラールはマリンチェの隣に並んできた。街の人々は、得体のしれない来訪者を影から伺っているようだった。ちらちらと感じる視線を振り払うように、マリンチェは足を進めた。しかし、途中で諦めた。適当に歩き、広場の隅に腰を下ろした。
「綺麗な街だ」
アギラールが隣に座りながら呟いた。ちらりと横目で見てから、マリンチェは溜息を吐いた。
「何で私に構うの。鬱陶しいわ」
「お前にはエスパニャ語を教えなければならん。コルテス殿が気にかけろと仰せだしな」
「ああそう」
実直すぎるアギラールに、マリンチェは嘆息しかでなかった。アギラールは少し声を潜めた。
「何かあっただろう」
「ないわよ、別に」
「では、訊き方を変える。何故モクテスマ殿は嫌われている? これだけの土地を治める王なのだろう? しかしここの首長もタバスコの首長も、マリンチェ、お前もあまりいい印象は持っていないようだ」
「それは」
少し、言いよどんだ。他の視線も気にはなったが、ふと、マヤ語なら判らないはずだと気が付いた。些細な事が安堵のひとつとなる。
「――私の故郷も、ここと同じだったの」
「故郷」
「ええ。パイナラという小さな街だった。父は首長だったわ」
アギラールが怪訝な顔をした。
「何故、その娘がタバスコで奴隷など」
「さあね」
答える義理はない。マリンチェは軽くいなして、顔を空へ向けた。澄んだ空気が肺を満たしていく。
「小さな街だった。だけど、好きだったわ。豊かな土地だったの。トウモロコシも、豆も、果実もたくさん実ったわ。陽射しはきつかったけれど、ここと同じに海からの風が入ってきていた。だけど、そうね、豊かだったのがいけなかったのよ。とても大きな税を課せられていたの」
その頃マリンチェはテノチティトランに留学していた。時折帰郷する度、父の顔が痩けていっていたのを嫌でも覚えているのだ。それでも父はマリンチェをテノチティトランへ送り出した。華やかなりしアステカの都で勉学を嗜むことこそ、名家の子女としての努めだといっていた。
くしゃり、と頭をなでる父の大きな手を思い出し、マリンチェはそっと唇を噛み締めた。
「父は苦しんでいたわ。とても民思いの首長だったのに、いいえ、だったからこそ、モクテスマの課す税と、街を機能させるのとの間で苦しんでいた」
「そうか。それでモクテスマ殿が」
「嫌いよ。口に出して言うとひどく叱られたけれどね」
細く長く、息を吐いた。そうすることで、胸のつかえを少し解こうとした。
「ここはパイナラと同じなのよ。そしてたぶん、こんな思いをしているのはここだけでもパイナラだけでもない。アステカは大きな国よ。だけど大きいからこそきっと綻びもある」
アギラールは短く頷いた。
その時だった。二人の男が走り寄ってきて鋭い口調で何かを言った。
「――!」
「――、――!」
トトナカ語だ。話す内容は判らない。だが、その口振りはただごとではなかった。男たちの顔に覚えはある。首長の傍に仕えていた者たちだ。マリンチェとアギラールは一瞬顔を見合わせる。
「――!」
男たちがまた何か叫んだ。身振り手振りで、傍の建物の陰に誘導してくる。ふと、気付いた。先ほどまであった好奇の視線が全て途絶えている。感じる気配は怯えのそれだった。何が起きたのか、それはすぐに知れた。街の入口の方から大仰な格好をした行列が現れたのだ。
先頭に掲げられた旗を見てマリンチェは息を呑んだ。
(モクテスマの税徴収人……!)