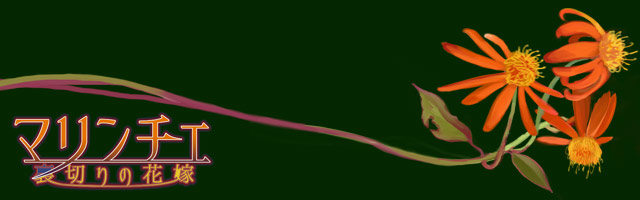Chapter4. 〈白い顔〉の戦士 - 2
◇
急襲は、山手からきた。想定外の大軍だった。
センポアラン、エスパニャ共同軍は二手に分かれて迎え打った。挟んで追い込む作戦だったが、現れた隊は散り散りになってそれを交わした。センポアラン、エスパニャともに昨夜のことがあってか息は合っていたが、地の利は相手にあったようだ、足場の悪い山岳地帯に、何よりエスパニャ軍は不慣れだった。左に回ったセンポアラ軍との息が徐々にずれていく。戦場そのものからは一歩引いた場所で見ていたマリンチェにはそれがよく判った。右の軍がはっきりと遅れている。
怒声や咆哮が轟く。この接近戦ではエスパニャ軍の大砲というらしいあの武器もあてにはならなかった。馬も、この寒さであまり俊敏には動けないようで押され気味だった。
「四千はいますね」
ふと、記録をとっていたベルナル・ディアスがマリンチェの横で呟いた。思わず、マリンチェは目を丸くした。
「そんなにいるの、これ」
マリンチェにはただ人の塊、としか表現しようがなかったが、さすがに軍について記録をとり続けていた男は違ったようだ。難しい顔をしたまま、軽く頷いた。
「五千は行かないでしょう。だが、こちらの倍はいる」
「大丈夫なの」
「武器が違います。近すぎて大砲は役に立ってはいないようですが、小銃などがうまく効いています。数そのままの戦力差ではない。あと……これは、不思議ですが。どうも、あちらは加減をされているように見える」
「加減?」
言いながら、マリンチェははっと理解した。認識の違いだ。
「手加減しているんじゃないわ。あれは正式な〈戦争〉をしているだけ」
「どう言うことだ」
――と、アギラールが問いかけてきた。
マリンチェたちのような、街々で献上された女子供と、彼らのような聖職者――オルメード神父もだ――、そして記録係としてのベルナル・ディアス、造船技師のマルティン・ロペス、センポアランの首長と通訳のオルコネアといった一部の人間は、戦場から離れた場所にいた。細かくは判らないが、離れているからこそ全体の戦況はよく見えた。
「彼らは〈花の戦争〉しか知らないな」
ふと、オルコネアがナワトル語で言った。マリンチェは頷き、「トラスカラと見て間違いなさそうね?」と、確認した。オルコネアは無造作に首肯した。マリンチェは怪訝な顔をしているアギラールたちに口早に説明した。
「トラスカラはモクテスマの治めるアステカ帝国と定期的に〈花の戦争〉をしていたはずよ。彼らにとっての戦争は、あくまでも対アステカの〈花の戦争〉なのね。人を殺すための戦争じゃない」
「殺めるためではない戦争?」
「生贄に捧げるために捕虜を得る。それが〈花の戦争〉よ。殺してしまっては意味が無いのよ。だから、加減しているようにみえるのでしょうね。でもそれは手加減ではないわ。貴方達にとっての戦争が人を殺めるためのもので、彼らにとっての――メヒコにとっての戦争はそうでない。それだけよ」
殺めるためでない戦争。その言葉に、エスパニャ人は考えこむように黙りこんでしまった。しかし、アギラールがすぐに吐き捨てるように結局は贄として殺されるのなら同じだ、と言った。
日が暮れる前に、トラスカラの大軍は撤退した。センポアラン、エスパニャ共同軍は、死人こそほぼ出ていなかったがそれでも負傷者も出たし、何より疲弊していた。コルテスはその場での野営は認めなかった。疲弊した軍を進ませ、すぐ近くの小さな街に入った。トラスカラの域内の街だけあって多少の抵抗はあったが、兵士となるような若手の男が少なくすぐに街の首長は一晩だけという約束でコルテスたちを受け入れた。コルテスは、若手はあのトラスカラ軍に収集されているはずだ、と語った。実際マリンチェが街人に話を聴きだしたところ、想定通りの答えだった。疲弊した軍を無理に進軍させたのはこの確証がコルテスにあったのだろう。実際、野営より随分と気が安らぐのは事実だ。
「約束を違えるつもりはない。ここは一晩だけだ。明朝、奴らが来る前にここを出る」
夜。マリンチェとアギラール、オルコネアの通訳組と、ペドロたちエスパニャとセンポアラン双方から数人の兵士だけで会議が行われた。
「この街を戦場にはしないということね」
少しほっとして、マリンチェは頷いた。
「マリンチェ。オルコネア。街の民と話をしたな? お前らの感想を聞かせてほしい」
マリンチェはオルコネアと向き合い、軽く肩を竦めてから話しだした。
「そうね。まずこの辺りはもうナワトル語の領域よ。私とオルコネアは話せるけれど、アギラールは無理ね」
「ああ。マヤ語は通じなかった」
「ええ。言い換えればアステカの領域とも言える。だけど、アステカよりトラスカラのほうがこの街の人に好かれているわ。だからこそトラスカラの軍に若手を差し出したのでしょうね」
「上手く機能しているようだな」
「ええ。〈花の戦争〉でも戦績は五分といったところみたいね。アステカの租税に関してもまずトラスカラが表に出て交渉しているそうよ。この辺りの街は全体的にそうみたい。だからありがたがっている」
「私が聞いたのも同じだ。トラスカラは、それに加えてこの辺り一帯の物資の輸送も取り仕切っている」
オルコネアが口を挟んだ。マリンチェはそれをエスパニャ語に訳して告げた。
「そうか。判った。次に戦についてだ。ペドロ、どうだ」
「はい。とにかく、数が多い。接近戦では不利になるでしょう。ただ、彼らは致命傷は与えてこない。マリンチェの言うところでは、それが彼らの戦争だということですが」
ペドロはちっ、と舌打ちした。相変わらず偏屈で神経質な男だ、とマリンチェは胸中で毒づいた。
「甘い、としか思えません。そこをついていくのがいいでしょう。あとは、連携さえ上手く取れれば良いのですが」
「そうだな、そこは俺も気になった。――おい、お前はどうだ?」
その場に招集されていた、センポアランの兵にコルテスが訊ねる。オルコネアの通訳によって、彼の言葉がナワトル語になり、それをマリンチェは代弁した。
「彼らも戦争といえば〈花の戦争〉なのよね。エスパニャのやり方に戸惑いがあるみたい。後はエスパニャ軍と離れているのと、言葉が判らないから、センポアランはセンポアランで進むしかないみたい」
「ずれの正体か。まあ仕方ない。どうにかしたいところだが」
一同は黙り込んだ。が、すぐにマリンチェは思いついて口を開いた。
「ねぇ。接近戦より距離を置きたいのよね。なら少し離れた場所に司令塔を置くことは出来ないの?」
「ありだな。指揮官をそれぞれの軍から出して、旗か何かで本隊に知らせればいい。通訳はお前たちに任せる。そしてそちらに大砲も置けば使えるな」
「殺すの?」
問いかけた声が、自分でも弱々しく聞こえてマリンチェは顔をしかめた。コルテスが苦笑した。
「無益な殺傷をするつもりはないさ」
翌日の戦は先日の場所で行われた。三隊に分かれ、配置された。センポアラン軍が山側を、反対側にエスパニャ軍を、そして、大砲などの大型装備をもった指令隊が離れた場所に。作戦は思った以上に上手くいった。それぞれの指揮官が絶妙な指示をだすのを、オルコネアがトトナカ語からナワトル語へ訳し、マリンチェはそれをマヤ語でアギラールに告げた。最初のうちはエスパニャ語にしようと必死になっていたが、まだ慣れないだろうとアギラールが手を貸してくれたので助かった。ナワトル語からマヤ語へなら、すぐに出来た。
大砲はうまく効いた。旗で味方の隊を誘導し、開いたところへ打った。人そのものを狙いはしなかったが、トラスカラの軍は蜘蛛の子を散らすように逃げた。そしてこの頃になると、エスパニャ軍も立ち回りに慣れが見え始めた。それは戦況にそのまま影響が出始める。日が暮れる頃になると、明らかにセンポアラン・エスパニャ共同軍が押していた。しかし、もう夜が来る。テスカトリポカの息吹を感じ始め、マリンチェは白い息とともにコルテスに問うた。
「夜に戦はしないわ。どうするの?」
「夜は寝るのか? 随分律儀で呑気な戦争ごっこだな」
コルテスのせせら笑うような言葉に、さすがにマリンチェも少し腹がたった。
「これがアステカの〈花の戦争〉よ。ごっこではないわ。文化が違うだけ」
コルテスは鼻で笑った。そしてそのまま、「押せ」と指示を出した。マリンチェは思わずコルテスに詰め寄りかける。しかし、すぐにアギラールの手が遮った。
「マリンチェ。あとで話をしよう。今は」
マヤ語だった。今この場でマヤ語で告げてくることがなんとなく卑怯に思えて、しかし逃げ出すわけにもいかず、マリンチェは渋々「押せって言ってるわ」とナワトル語で吐き捨てた。オルコネアも多少の戸惑いは見せたが、トトナカ語に訳したようだった。旗が大きく振られる。戦場に、マリンチェは背を向けた。
「逃げるか」
「ふざけないで……!」
「まあ、別に止めはせんがな。お前は何を望む、マリンチェ。ここを超えねば、お前の『朝』はこねぇぞ」
ぎりっと、奥歯が鳴った。マリンチェは数瞬迷い、そして振り返った。アギラールの複雑そうな顔が視界に入ったが、見ないふりをした。戦場をただ、睨みつけた。
◇
急襲は、山手からきた。想定外の大軍だった。
センポアラン、エスパニャ共同軍は二手に分かれて迎え打った。挟んで追い込む作戦だったが、現れた隊は散り散りになってそれを交わした。センポアラン、エスパニャともに昨夜のことがあってか息は合っていたが、地の利は相手にあったようだ、足場の悪い山岳地帯に、何よりエスパニャ軍は不慣れだった。左に回ったセンポアラ軍との息が徐々にずれていく。戦場そのものからは一歩引いた場所で見ていたマリンチェにはそれがよく判った。右の軍がはっきりと遅れている。
怒声や咆哮が轟く。この接近戦ではエスパニャ軍の大砲というらしいあの武器もあてにはならなかった。馬も、この寒さであまり俊敏には動けないようで押され気味だった。
「四千はいますね」
ふと、記録をとっていたベルナル・ディアスがマリンチェの横で呟いた。思わず、マリンチェは目を丸くした。
「そんなにいるの、これ」
マリンチェにはただ人の塊、としか表現しようがなかったが、さすがに軍について記録をとり続けていた男は違ったようだ。難しい顔をしたまま、軽く頷いた。
「五千は行かないでしょう。だが、こちらの倍はいる」
「大丈夫なの」
「武器が違います。近すぎて大砲は役に立ってはいないようですが、小銃などがうまく効いています。数そのままの戦力差ではない。あと……これは、不思議ですが。どうも、あちらは加減をされているように見える」
「加減?」
言いながら、マリンチェははっと理解した。認識の違いだ。
「手加減しているんじゃないわ。あれは正式な〈戦争〉をしているだけ」
「どう言うことだ」
――と、アギラールが問いかけてきた。
マリンチェたちのような、街々で献上された女子供と、彼らのような聖職者――オルメード神父もだ――、そして記録係としてのベルナル・ディアス、造船技師のマルティン・ロペス、センポアランの首長と通訳のオルコネアといった一部の人間は、戦場から離れた場所にいた。細かくは判らないが、離れているからこそ全体の戦況はよく見えた。
「彼らは〈花の戦争〉しか知らないな」
ふと、オルコネアがナワトル語で言った。マリンチェは頷き、「トラスカラと見て間違いなさそうね?」と、確認した。オルコネアは無造作に首肯した。マリンチェは怪訝な顔をしているアギラールたちに口早に説明した。
「トラスカラはモクテスマの治めるアステカ帝国と定期的に〈花の戦争〉をしていたはずよ。彼らにとっての戦争は、あくまでも対アステカの〈花の戦争〉なのね。人を殺すための戦争じゃない」
「殺めるためではない戦争?」
「生贄に捧げるために捕虜を得る。それが〈花の戦争〉よ。殺してしまっては意味が無いのよ。だから、加減しているようにみえるのでしょうね。でもそれは手加減ではないわ。貴方達にとっての戦争が人を殺めるためのもので、彼らにとっての――メヒコにとっての戦争はそうでない。それだけよ」
殺めるためでない戦争。その言葉に、エスパニャ人は考えこむように黙りこんでしまった。しかし、アギラールがすぐに吐き捨てるように結局は贄として殺されるのなら同じだ、と言った。
日が暮れる前に、トラスカラの大軍は撤退した。センポアラン、エスパニャ共同軍は、死人こそほぼ出ていなかったがそれでも負傷者も出たし、何より疲弊していた。コルテスはその場での野営は認めなかった。疲弊した軍を進ませ、すぐ近くの小さな街に入った。トラスカラの域内の街だけあって多少の抵抗はあったが、兵士となるような若手の男が少なくすぐに街の首長は一晩だけという約束でコルテスたちを受け入れた。コルテスは、若手はあのトラスカラ軍に収集されているはずだ、と語った。実際マリンチェが街人に話を聴きだしたところ、想定通りの答えだった。疲弊した軍を無理に進軍させたのはこの確証がコルテスにあったのだろう。実際、野営より随分と気が安らぐのは事実だ。
「約束を違えるつもりはない。ここは一晩だけだ。明朝、奴らが来る前にここを出る」
夜。マリンチェとアギラール、オルコネアの通訳組と、ペドロたちエスパニャとセンポアラン双方から数人の兵士だけで会議が行われた。
「この街を戦場にはしないということね」
少しほっとして、マリンチェは頷いた。
「マリンチェ。オルコネア。街の民と話をしたな? お前らの感想を聞かせてほしい」
マリンチェはオルコネアと向き合い、軽く肩を竦めてから話しだした。
「そうね。まずこの辺りはもうナワトル語の領域よ。私とオルコネアは話せるけれど、アギラールは無理ね」
「ああ。マヤ語は通じなかった」
「ええ。言い換えればアステカの領域とも言える。だけど、アステカよりトラスカラのほうがこの街の人に好かれているわ。だからこそトラスカラの軍に若手を差し出したのでしょうね」
「上手く機能しているようだな」
「ええ。〈花の戦争〉でも戦績は五分といったところみたいね。アステカの租税に関してもまずトラスカラが表に出て交渉しているそうよ。この辺りの街は全体的にそうみたい。だからありがたがっている」
「私が聞いたのも同じだ。トラスカラは、それに加えてこの辺り一帯の物資の輸送も取り仕切っている」
オルコネアが口を挟んだ。マリンチェはそれをエスパニャ語に訳して告げた。
「そうか。判った。次に戦についてだ。ペドロ、どうだ」
「はい。とにかく、数が多い。接近戦では不利になるでしょう。ただ、彼らは致命傷は与えてこない。マリンチェの言うところでは、それが彼らの戦争だということですが」
ペドロはちっ、と舌打ちした。相変わらず偏屈で神経質な男だ、とマリンチェは胸中で毒づいた。
「甘い、としか思えません。そこをついていくのがいいでしょう。あとは、連携さえ上手く取れれば良いのですが」
「そうだな、そこは俺も気になった。――おい、お前はどうだ?」
その場に招集されていた、センポアランの兵にコルテスが訊ねる。オルコネアの通訳によって、彼の言葉がナワトル語になり、それをマリンチェは代弁した。
「彼らも戦争といえば〈花の戦争〉なのよね。エスパニャのやり方に戸惑いがあるみたい。後はエスパニャ軍と離れているのと、言葉が判らないから、センポアランはセンポアランで進むしかないみたい」
「ずれの正体か。まあ仕方ない。どうにかしたいところだが」
一同は黙り込んだ。が、すぐにマリンチェは思いついて口を開いた。
「ねぇ。接近戦より距離を置きたいのよね。なら少し離れた場所に司令塔を置くことは出来ないの?」
「ありだな。指揮官をそれぞれの軍から出して、旗か何かで本隊に知らせればいい。通訳はお前たちに任せる。そしてそちらに大砲も置けば使えるな」
「殺すの?」
問いかけた声が、自分でも弱々しく聞こえてマリンチェは顔をしかめた。コルテスが苦笑した。
「無益な殺傷をするつもりはないさ」
翌日の戦は先日の場所で行われた。三隊に分かれ、配置された。センポアラン軍が山側を、反対側にエスパニャ軍を、そして、大砲などの大型装備をもった指令隊が離れた場所に。作戦は思った以上に上手くいった。それぞれの指揮官が絶妙な指示をだすのを、オルコネアがトトナカ語からナワトル語へ訳し、マリンチェはそれをマヤ語でアギラールに告げた。最初のうちはエスパニャ語にしようと必死になっていたが、まだ慣れないだろうとアギラールが手を貸してくれたので助かった。ナワトル語からマヤ語へなら、すぐに出来た。
大砲はうまく効いた。旗で味方の隊を誘導し、開いたところへ打った。人そのものを狙いはしなかったが、トラスカラの軍は蜘蛛の子を散らすように逃げた。そしてこの頃になると、エスパニャ軍も立ち回りに慣れが見え始めた。それは戦況にそのまま影響が出始める。日が暮れる頃になると、明らかにセンポアラン・エスパニャ共同軍が押していた。しかし、もう夜が来る。テスカトリポカの息吹を感じ始め、マリンチェは白い息とともにコルテスに問うた。
「夜に戦はしないわ。どうするの?」
「夜は寝るのか? 随分律儀で呑気な戦争ごっこだな」
コルテスのせせら笑うような言葉に、さすがにマリンチェも少し腹がたった。
「これがアステカの〈花の戦争〉よ。ごっこではないわ。文化が違うだけ」
コルテスは鼻で笑った。そしてそのまま、「押せ」と指示を出した。マリンチェは思わずコルテスに詰め寄りかける。しかし、すぐにアギラールの手が遮った。
「マリンチェ。あとで話をしよう。今は」
マヤ語だった。今この場でマヤ語で告げてくることがなんとなく卑怯に思えて、しかし逃げ出すわけにもいかず、マリンチェは渋々「押せって言ってるわ」とナワトル語で吐き捨てた。オルコネアも多少の戸惑いは見せたが、トトナカ語に訳したようだった。旗が大きく振られる。戦場に、マリンチェは背を向けた。
「逃げるか」
「ふざけないで……!」
「まあ、別に止めはせんがな。お前は何を望む、マリンチェ。ここを超えねば、お前の『朝』はこねぇぞ」
ぎりっと、奥歯が鳴った。マリンチェは数瞬迷い、そして振り返った。アギラールの複雑そうな顔が視界に入ったが、見ないふりをした。戦場をただ、睨みつけた。
◇