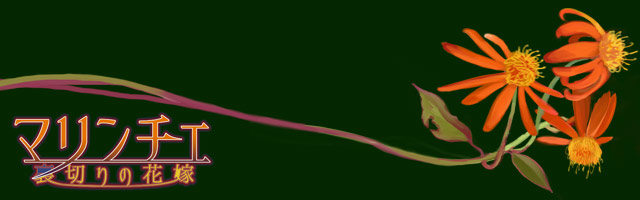Chapter4. 〈白い顔〉の戦士 - 5
◇
「やめろ! 距離を置け!」
コルテスが声を張り上げた。同時に、ゲレロは傍にいた同じような格好をした男に何かを告げた。男が声を張り上げる。同じように、戦士たちに距離を置くように呼びかけたようだった。
戦場が、静まる。
センポアランとエスパニャの指揮官だけが、戦旗を振った。あちらにも一時撤退の指示を出したようだった。
「――よう、ゲレロ。何事だ、これは?」
「あんた方の邪魔をしに参りましたよ、コルテス殿」
「そりゃあ傑作だ。あんときせっかく迎えに行ったのに断ったかと思えばこの有様か」
「ええ。人生とは妙なものですな」
互いに笑いながら軽口を叩きあっている。だが、ゲレロはアギラールに剣を向けたままで、コルテスはそのゲレロの背後に立っている。
「コルテス殿、ちぃと我儘を聞いてくれねぇかな」
「言ってみろ」
「アギラールと一騎打ちをさせてほしい」
――友が何を望んでいるのか、アギラールには判らなかった。
「何を……!」
「お好きにどうぞ?」
「コルテス殿!?」
コルテスはただ笑うだけだった。
「……ねぇ」
ふと、マヤ語が混じった。マリンチェだ。複雑そうな顔で、ゲレロをまっすぐ見つめている。
「あなたはエスパニャの人なの? どうしてマヤの格好をして、こんなところに来ているの。どうしてアギラールに剣を向けているの」
「――俺はエスパニャの生まれだが、妻はマヤの女だ。そして今は、マヤの人間としてここにいる」
ゲレロはマリンチェにほほえみながら答えた。
「俺は逆にあんたに聞きたいけどな。メヒコ娘がなんでコルテス軍にいるのか、って。いろいろあるんだろ?」
「……ええ、そうね。あなたもいろいろある、ってことね?」
「まあな。俺はこの地をエスパニャに染めたくない。それだけさ」
ゲレロがふっと短く息を吐いた。
「さっき、お前に剣を流されて気がついた。お前、剣を学んだな」
脳裏に、アロンソ・ヘルナンデス・プエルトカレーロの姿がよぎった。
「ま、そんな深く考えんなや。昔はよくやりあって遊んだろ?」
それは木切れで、だ。そう言い返したかったが、何故か声が出なかった。
「シコテンカトル――ああ、こっちの男な。こいつが俺らの指揮官で、トラスカラの戦士だ。マヤからは俺と数人だけが来ている。だが、シコテンカトルは俺を評価してくれている。この場での立ち回りも理解してくれている。俺が倒れれば、シコンテンカトル率いるトラスカラ軍は全軍、そちらに下る」
それは覚悟だった。友の覚悟に、アギラールは答えるしかないと悟った。
「どうにも、ならないんだな」
「ああ。悪いな」
吹き付ける寒風が目に痛い。しかし、火照った顔を冷やしていくのはありがたかった。泣きたいわけではない。そんなこと、無意味だと判っている。だからこそアギラールは考えるのをやめた。
「あ……あああああああ!」
聲が迸った。走りだした足先が痺れる。
そして、アギラールの振りかざした剣はかつての友へと肉薄した。
◇
マリンチェには悲鳴に聞こえた。アギラールの上げる声は、ただの悲鳴だった。悲鳴とともに剣がかざされ、はじかれあう。
何故。胸中で繰り返し浮かぶその言葉を、マリンチェは今はただ飲み込んだ。見届けなければならない。
戦や動きのことはマリンチェにはよく判らない。ただなんとなく、アギラールの動きにアロンソを思い出した。誰も動かない。何も話さない。ただ二人だけが幾度か交差し、短く声を上げあっている。奇妙な刻が暫く続いた。
先に体勢を崩したのはアギラールだった。息を切らしはじめ、動きも鈍った。もとより彼は戦士ではないのだから当然と言えた。それでも幾度か切り結んだ後――ふっと、体勢を崩した。大地に膝を突く。
「アギラール!」
思わず声を上げていた。前に出かけたマリンチェを遮ったのはコルテスの太い腕だった。
「心配するな」
コルテスは低い声で言った。
マヤの戦士が飛びかかる。
「あれに剣を叩き込んだのは」
アギラールが転がって一撃を何とか避けた。一瞬の間だった。マヤの戦士の剣は大地に突きたった。
「アロンソ・ヘルナデス・プエルトカレーロ」
マヤの戦士が振り返る。アギラールはすでに剣を構えて立っていた。
「――希代の戦士だ」
アギラールのつきだした剣はまっすぐ、マヤの戦士の胸を貫いた。
◇
冷たい夜だった。久しぶりに傾けた酒はこの辺りのもので、旨いとは思えなかったが酔うには十分だった。
「友人だったのね」
背後からの静かな声に、ふとアギラールの口元が緩んだ。情けないと自ら思えるような、自虐的な笑みだ。しかし、今更彼女に隠しようもない。アギラールは振り返らぬまま、月を見上げて告げた。
「大切な友だった。共に育ち、共に大人になった。同じ船で旅立ち、同じ日に嵐に合い、同じように囚われの身になった。だが、私はコルテス殿と合流し、あいつはそうはしなかった」
「彼はどうしてそっちを選んだの」
「マヤの女に惚れたんだ」
「そう」
相槌の声が直ぐ側で聞こえた。マリンチェはこちらを見ない。ただ同じように月を見上げながら、アギラールの隣に腰を下ろした。
ぱちぱちと、火の爆ぜる音がした。
「ゴンサーロ・ゲレロという」
「それが彼の名なのね」
「ああ」とアギラールは首肯した。
「友の名だ。覚えておいてくれ」
マリンチェは無言のまま小さく頷いてくれた。目を閉じる。浮かぶのは数々の思い出と、屈辱と恐怖にまみれ、絶望と泥の味を噛み締めたあの日々だ。絶望の中で生きてこられたのは、たしかな友が傍にいたからだ。いつかは、また、エスパニャの地に帰れると信じ、そして誓い合ったからだ。
しかし、契りは叶わなかった。言ってしまえば、ただそれだけとも言える。
「ゲレロは、マヤの女に惚れて女房にした。子供も、儲けてたはずだ」
「そう」
頷いたあと、マリンチェは少し躊躇うような口ぶりで言った。
「彼は裏切ったのね。祖国を」
「――そうだな」
「貴方は彼を愚かだと思う?」
問われ、アギラールは一瞬口ごもる。しかしすぐに答えは出た。短く、首を左右に振る。
「いや。思うところはあるが、人は簡単じゃない」
アギラールはマリンチェを見た。冴え渡る月光の中、マリンチェの瞳は夜よりなお鮮やかに輝いている。
マリンチェは、今まさに祖国を裏切ろうとしているのと同じだろう。このまま、自分たちについてくるとなればそうならざるを得ない。ゲレロの影が、マリンチェに重なって見えた。
「マリンチェ」
「何」
「抱きしめていいか」
口をついてでた言葉に、アギラール自身驚いた。マリンチェもまた、目を見開いている。
「なにそれ。許可を求めるの? 律儀ね」
「いや」
抱き寄せる。マリンチェは抗わないでくれた。
「予告しただけだ」
友を殺めた手で彼女を抱くことに抵抗がなかったわけではない。それでも、彼女はこの細い体で一人で立っている。国、宗教、意志、立場。様々なものと、向きあう強さを抱いている。その彼女を今は、抱きしめたいと思った。それだけだった。
月はただ、頭上にありつづけている。