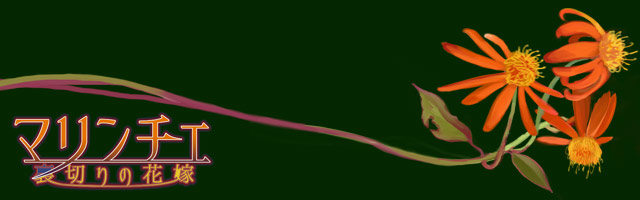Chapter6. テノチティトランの夜明け - 2
「……アギラールです」
いつもどおりのやりとりをして、アギラールは小さく笑った。振り返るとコルテスがいた。
「眠れませんでね」
「お前もか。はは、俺もだ。興奮して寝付けやしない」
コルテスらしくない、とは思った。だがそんなものだろうともまた思う。コルテスはアギラールの隣にどさりと腰を下ろした。
「やっとここまでか」
「ええ。テノチティトランです。キューバへのご報告は?」
「もうしてあるさ。勝手をするなと小うるさく書簡を送ってきておる」
小さく頷き返す。
「それでどうした。辛気くさい顔をして」
「少々、考え事を」
「なんだ?」
言うべきかどうか一瞬迷ったが、隠していたところでどうしようもないだろう。
「望みが判りません」
「望み?」
「ベルナル・ディアス殿に訊ねられました。望みは何か、と。考えてみれば確かにそうなのです。皆、望みをお持ちだ。マリンチェも、ベルナル・ディアス殿も、ゲレロだって目的があって現れた。その目的を私が消したのですが、消した私自身は望みが判らない」
「エスパニャに帰ることが望みではないのか」
「それはそうなのですが」
曖昧に苦笑してみせた。
「しかしそこの大きな部分は、マヤから逃げたかった、というだけです。もとよりエスパニャを出てサント・ドミンゴへ向かうつもりだったわけですからね」
「そういえばそうか」
「ここがそうなのだと言われれば、私はここで根を張って生きていってもいいわけです。ですから、私の望みとは何か、明確ではない」
コルテスが頷いて立ち上がった。
「いい機会だから話しておくか。俺はな、この国を買っている。テウディレを通じてモクテスマはどれだけの金を寄越してきたと思う。もう随分な量になった。めぼしい分はエスパニャに送ってはいるが、それでも手元に随分残っている。この国の財力をな、高く買っているんだ。ここを手に入れたい」
「――手に、入れる」
「ああ。まぁ、面倒なんでな。そう手荒な真似に出るつもりはない。――つっても信じねぇか? チョルーラでお前ら、すんげぇ顔で睨んでたもんな」
アギラールもまた、立ち上がった。星を見上げる。
「何故、あんな真似を?」
「なら、どうすれば良かった? 黙って襲撃を待てと? 俺はな、アギラール。ここに、俺を信じてついてきた者がいる限りそいつらを殺させはしない。指揮官としての努めだ。判るか。俺はお前らを守る。その為ならこの国の民を多く殺すだろうよ」
覚悟がおありになる。ベルナル・ディアスの言葉が蘇った。アギラールは何も言えなかった。コルテスは淡々と言葉を続ける。
「仕方がなかったとは言わん。俺は選んだ上でああした。それが悪いことだったとも思ってない。それにな」
コルテスはちらりと背後を振り返った。人影がないことを確かめるかのようだった。
「ここの宗教観が俺はどうも気に食わん。毎日毎日人の心臓を捧げ、それで何人の罪なき者が死んでいく。俺はここでアステカの民の多くを殺すだろう。だが、この馬鹿げた風習が未来永劫続くのなら、それを断ち切る必要がある。未来に生贄は、いらぬ」
「それは」
言う唇を一度舐めてから、アギラールは続けた。
「この国を滅ぼしたいと?」
「――人は宗教からでも変われる。俺はそう言っているだけだ。アギラール」
肩に手を置かれた。
「キリストの教えをお前が広めてもいい。オルメード神父とともにな。未来の生贄を、断つために」
それが望みにはなりはしないか。コルテスの言葉にアギラールはそっと目を伏せた。考えておきましょう。そう答えるのが精一杯だった。
◇
翌日から、また街の見学が始まった。同時に、モクテスマの許しを得て宮殿の中に礼拝堂を作る作業が始まった。マリンチェはどこか複雑そうな顔をしていた。彼女はまだ、キリストを信じきっているわけではないだろう。だが同時に己の信じてきた宗教観が危うくなっているのも確かだ。彼女は生贄という風習そのものをもはや嫌ってさえいるだろう。だが、例えそうだとしても自身の信じてきた宗教という文化を蔑ろにされているように感じているのかもしれない。
その間にも毎日、人身御供の儀式は行われた。マリンチェはそんな時ふらりと姿を消すようになった。話を聞いてみると、モクテスマの実娘と仲良くなったようで、彼女と話をしているという。そうして、マリンチェは自身の感情を保っているように思えた。
そんな折、小さな騒動が起きた。礼拝堂工事の最中、大工がある部屋の扉が塞がれた痕跡を見つけたのだ。コルテスが開けたところ、中には金や銀、数多の宝石、羽飾りと大量の宝物が見つかった。元は父王アシャヤカトルの宮殿だ。こういったものがあってもさして不思議ではないだろう。モクテスマはエスパニャ軍を迎え入れるための準備としてこの扉を塞いだのかもしれなかった。エスパニャ軍は揺れた。これだけの金を目の当たりにすれば人はそうならざるを得なかったのかもしれない。奪え、モクテスマを殺せばいい、そんな声すら出るようになった。コルテスはそれを言った者たちを叱責したが、噂は広がる一方だった。
そんな時、今後のための会議の最中、遅れていたベルナル・ディアスが血相を変えて飛び込んできた。
「コルテス殿!」
「どうした」
「ベラクルスから書簡が届きました」
ベルナル・ディアスがその書簡を読み上げ始めると同時に、会議中の部屋の空気が一変した。マリンチェも顔を青ざめさせている。苦虫をかみつぶしたような顔で聞いていたコルテスは、読み上げが終わると同時に立ち上がった。
「契機だな」
唇を歪ませている。それは笑みのようでいて、ただ怒りを無理やり沈めたための顔のようにも見えた。
「マリンチェ、大仕事だ。ペドロ、アギラール、シコテンカトル、三十名ほど腕の立つものを今すぐ集めろ。ベルナル・ディアスはセンポアランに急使を出せ。いいか、これは身を斬られた上で掴んだ機だと思え!」
ベラクルスからの書簡の内容はこうだった。
海岸地方に駐屯するメヒコの民――センポアラン以外だろうが、詳しいことは書いていなかった――がベラクルスを急襲し、痛手を負ったとのことだった。アロンソも充分戦ったようだが、部下の数人が死んだと記されていた。センポアランにすぐにベラクルスへ向かうように指示を出した。そしてコルテスは集められた戦士たちと通訳のマリンチェを従え、モクテスマの宮殿〈蛇の家〉へ向かった。
「我が友が殺された」
マリンチェの口を通じて、コルテスは開口一番そう告げた。とても悔しげな響きだった。
アギラールはそれがコルテスの本音だと理解していた。あの夜、彼は仲間を死なせないと告げたばかりだった。それが自らの手の及ばない場所で覆されたとすれば、悔しさは判る。
「俺はセンポアランであんたの税徴収人が捕まった時、なんとか口利きをして二人だけではあったがあんたのもとに返したはずだ。それはあんたも友だと思っていたからだ。少なくとも、友になり得ると思っていたからだ。まさか、こんな形で裏切られるとはな」
「我が指示を出したわけではない。大変申し訳なく思うが」
「あんたは王だろう。王であるあんたが末端まで指示を行き渡らせていないのは、それだけで罪だ。上に立つものが無能なのは、罪なんだ」
これにはモクテスマは何も言い返せなかったようだ。拳を握りただ静かに視線を落とした。
――小さい男だと、アギラールには思えた。とてもこれだけの大きさを誇るテノチティトランを、しいてはアステカ帝国を統べる王には見えなかった。
「首が、送られたな」
ふと、静かにコルテスが呟いた。マリンチェは知らなかったのだろう。びくりと体を震わせて、それでもなんとか通訳した。モクテスマは否定しなかった。
「俺の友の首が、あんたのところに送ってこられたはずだ。書簡の中にそう記されていた」
すっとモクテスマが右手を上げた。従者が、布に包まれた首を持って現れた。布をはがすと、苦悶の顔を浮かべたエスパニャ兵がそこにあった。コルテスはその首を大事に抱き、そっとペドロに手渡した。
「ヨス。ご苦労だった」
その者の顔は、アギラールも覚えていた。ヨス・ロセーリョ。アロンソを強く慕っていた男だった。それほど腕は立たない男だったが、従順で明るく、冗談もよく言う愉快な男だった。
「ヨスの首がここに送られたということは、あんたは少なくともこの事態を知っていたはずだ。そしてこの首を送った者は、あんたがこの首を喜ぶとでも思ったのだろう? それは裏切り行為になる」
すっと、コルテスが息をすった。朗々と響く声で、告げた。
「我らへの裏切りの代償として、貴殿は父王アシャヤカトルの宮殿へと入られよ!」
――それは王の権威の失墜を意味する。さすがにこれにはモクテスマも必死に抵抗した。だが、ほとんど脅迫とも取れる言葉が重ねられ始めると、モクテスマも従わざるを得なくなった。モクテスマが力なく頷いた瞬間、エスパニャの兵たちから歓声が沸き上がった。しかしコルテスはそれをすっと手で制し、アギラールに視線を寄越した。
「おい。お前も何か、ないか?」
「良いのですね」
「ああ」
アギラールはきゅっと唇を結んだ。今度は何を訳させられるのかという顔をしているマリンチェに向かって軽く肩を竦めてみせた。
「もう一つ。願いがあります。モクテスマ殿」
「……なんだ」
「生贄の儀式を一切、やめていただきたい」
――マリンチェの声が震えた。そっと、アギラールは彼女の背を叩いた。
「それは出来ぬ。そんなことをすれば神々のお怒りが地に落ち、この世は永久の夜になるだろう」
「なりません。ここにおられる方が何者であるかは、貴方が一番良くご存知でしょう。コルテス殿はその無意味な儀式を毛嫌いしておられる。それに、朝は必ず来ます。我らの神も、それは確実に保証してくださるでしょう」
「貴方方の神などというものを信じろと」
「そう言っています。モクテスマ殿。貴方に拒否権はないはずです。即刻、貴方の声が届くすべての地に報せを届けるのです。そしてこのテノチティトランでも。一切の生贄などという無益な殺戮を、やめるのです」
その日のうちに、モクテスマの使者はアステカ中へと走っていった。各地で首長たちは驚きと戸惑いを持つことだろう。だが、従うしかないはずだった。その日、華やかなりしアステカの首都テノチティトランは静まり返った。人々は扉を固く閉じ、息を潜めた。しかし、それでも噂は静かに染み渡った。王が〈白い顔〉の人間に囚われた、という噂だった。
今日は、特別な日になる。アギラールは確信した。ベルナル・ディアスに目をやる。
「書き留めておいでですか」
「無論」
「一五一九年、十一月十四日、ですね」
「ああ。今日は――歴史になる」
ベルナル・ディアスがにやりと、笑った。
いつもどおりのやりとりをして、アギラールは小さく笑った。振り返るとコルテスがいた。
「眠れませんでね」
「お前もか。はは、俺もだ。興奮して寝付けやしない」
コルテスらしくない、とは思った。だがそんなものだろうともまた思う。コルテスはアギラールの隣にどさりと腰を下ろした。
「やっとここまでか」
「ええ。テノチティトランです。キューバへのご報告は?」
「もうしてあるさ。勝手をするなと小うるさく書簡を送ってきておる」
小さく頷き返す。
「それでどうした。辛気くさい顔をして」
「少々、考え事を」
「なんだ?」
言うべきかどうか一瞬迷ったが、隠していたところでどうしようもないだろう。
「望みが判りません」
「望み?」
「ベルナル・ディアス殿に訊ねられました。望みは何か、と。考えてみれば確かにそうなのです。皆、望みをお持ちだ。マリンチェも、ベルナル・ディアス殿も、ゲレロだって目的があって現れた。その目的を私が消したのですが、消した私自身は望みが判らない」
「エスパニャに帰ることが望みではないのか」
「それはそうなのですが」
曖昧に苦笑してみせた。
「しかしそこの大きな部分は、マヤから逃げたかった、というだけです。もとよりエスパニャを出てサント・ドミンゴへ向かうつもりだったわけですからね」
「そういえばそうか」
「ここがそうなのだと言われれば、私はここで根を張って生きていってもいいわけです。ですから、私の望みとは何か、明確ではない」
コルテスが頷いて立ち上がった。
「いい機会だから話しておくか。俺はな、この国を買っている。テウディレを通じてモクテスマはどれだけの金を寄越してきたと思う。もう随分な量になった。めぼしい分はエスパニャに送ってはいるが、それでも手元に随分残っている。この国の財力をな、高く買っているんだ。ここを手に入れたい」
「――手に、入れる」
「ああ。まぁ、面倒なんでな。そう手荒な真似に出るつもりはない。――つっても信じねぇか? チョルーラでお前ら、すんげぇ顔で睨んでたもんな」
アギラールもまた、立ち上がった。星を見上げる。
「何故、あんな真似を?」
「なら、どうすれば良かった? 黙って襲撃を待てと? 俺はな、アギラール。ここに、俺を信じてついてきた者がいる限りそいつらを殺させはしない。指揮官としての努めだ。判るか。俺はお前らを守る。その為ならこの国の民を多く殺すだろうよ」
覚悟がおありになる。ベルナル・ディアスの言葉が蘇った。アギラールは何も言えなかった。コルテスは淡々と言葉を続ける。
「仕方がなかったとは言わん。俺は選んだ上でああした。それが悪いことだったとも思ってない。それにな」
コルテスはちらりと背後を振り返った。人影がないことを確かめるかのようだった。
「ここの宗教観が俺はどうも気に食わん。毎日毎日人の心臓を捧げ、それで何人の罪なき者が死んでいく。俺はここでアステカの民の多くを殺すだろう。だが、この馬鹿げた風習が未来永劫続くのなら、それを断ち切る必要がある。未来に生贄は、いらぬ」
「それは」
言う唇を一度舐めてから、アギラールは続けた。
「この国を滅ぼしたいと?」
「――人は宗教からでも変われる。俺はそう言っているだけだ。アギラール」
肩に手を置かれた。
「キリストの教えをお前が広めてもいい。オルメード神父とともにな。未来の生贄を、断つために」
それが望みにはなりはしないか。コルテスの言葉にアギラールはそっと目を伏せた。考えておきましょう。そう答えるのが精一杯だった。
◇
翌日から、また街の見学が始まった。同時に、モクテスマの許しを得て宮殿の中に礼拝堂を作る作業が始まった。マリンチェはどこか複雑そうな顔をしていた。彼女はまだ、キリストを信じきっているわけではないだろう。だが同時に己の信じてきた宗教観が危うくなっているのも確かだ。彼女は生贄という風習そのものをもはや嫌ってさえいるだろう。だが、例えそうだとしても自身の信じてきた宗教という文化を蔑ろにされているように感じているのかもしれない。
その間にも毎日、人身御供の儀式は行われた。マリンチェはそんな時ふらりと姿を消すようになった。話を聞いてみると、モクテスマの実娘と仲良くなったようで、彼女と話をしているという。そうして、マリンチェは自身の感情を保っているように思えた。
そんな折、小さな騒動が起きた。礼拝堂工事の最中、大工がある部屋の扉が塞がれた痕跡を見つけたのだ。コルテスが開けたところ、中には金や銀、数多の宝石、羽飾りと大量の宝物が見つかった。元は父王アシャヤカトルの宮殿だ。こういったものがあってもさして不思議ではないだろう。モクテスマはエスパニャ軍を迎え入れるための準備としてこの扉を塞いだのかもしれなかった。エスパニャ軍は揺れた。これだけの金を目の当たりにすれば人はそうならざるを得なかったのかもしれない。奪え、モクテスマを殺せばいい、そんな声すら出るようになった。コルテスはそれを言った者たちを叱責したが、噂は広がる一方だった。
そんな時、今後のための会議の最中、遅れていたベルナル・ディアスが血相を変えて飛び込んできた。
「コルテス殿!」
「どうした」
「ベラクルスから書簡が届きました」
ベルナル・ディアスがその書簡を読み上げ始めると同時に、会議中の部屋の空気が一変した。マリンチェも顔を青ざめさせている。苦虫をかみつぶしたような顔で聞いていたコルテスは、読み上げが終わると同時に立ち上がった。
「契機だな」
唇を歪ませている。それは笑みのようでいて、ただ怒りを無理やり沈めたための顔のようにも見えた。
「マリンチェ、大仕事だ。ペドロ、アギラール、シコテンカトル、三十名ほど腕の立つものを今すぐ集めろ。ベルナル・ディアスはセンポアランに急使を出せ。いいか、これは身を斬られた上で掴んだ機だと思え!」
ベラクルスからの書簡の内容はこうだった。
海岸地方に駐屯するメヒコの民――センポアラン以外だろうが、詳しいことは書いていなかった――がベラクルスを急襲し、痛手を負ったとのことだった。アロンソも充分戦ったようだが、部下の数人が死んだと記されていた。センポアランにすぐにベラクルスへ向かうように指示を出した。そしてコルテスは集められた戦士たちと通訳のマリンチェを従え、モクテスマの宮殿〈蛇の家〉へ向かった。
「我が友が殺された」
マリンチェの口を通じて、コルテスは開口一番そう告げた。とても悔しげな響きだった。
アギラールはそれがコルテスの本音だと理解していた。あの夜、彼は仲間を死なせないと告げたばかりだった。それが自らの手の及ばない場所で覆されたとすれば、悔しさは判る。
「俺はセンポアランであんたの税徴収人が捕まった時、なんとか口利きをして二人だけではあったがあんたのもとに返したはずだ。それはあんたも友だと思っていたからだ。少なくとも、友になり得ると思っていたからだ。まさか、こんな形で裏切られるとはな」
「我が指示を出したわけではない。大変申し訳なく思うが」
「あんたは王だろう。王であるあんたが末端まで指示を行き渡らせていないのは、それだけで罪だ。上に立つものが無能なのは、罪なんだ」
これにはモクテスマは何も言い返せなかったようだ。拳を握りただ静かに視線を落とした。
――小さい男だと、アギラールには思えた。とてもこれだけの大きさを誇るテノチティトランを、しいてはアステカ帝国を統べる王には見えなかった。
「首が、送られたな」
ふと、静かにコルテスが呟いた。マリンチェは知らなかったのだろう。びくりと体を震わせて、それでもなんとか通訳した。モクテスマは否定しなかった。
「俺の友の首が、あんたのところに送ってこられたはずだ。書簡の中にそう記されていた」
すっとモクテスマが右手を上げた。従者が、布に包まれた首を持って現れた。布をはがすと、苦悶の顔を浮かべたエスパニャ兵がそこにあった。コルテスはその首を大事に抱き、そっとペドロに手渡した。
「ヨス。ご苦労だった」
その者の顔は、アギラールも覚えていた。ヨス・ロセーリョ。アロンソを強く慕っていた男だった。それほど腕は立たない男だったが、従順で明るく、冗談もよく言う愉快な男だった。
「ヨスの首がここに送られたということは、あんたは少なくともこの事態を知っていたはずだ。そしてこの首を送った者は、あんたがこの首を喜ぶとでも思ったのだろう? それは裏切り行為になる」
すっと、コルテスが息をすった。朗々と響く声で、告げた。
「我らへの裏切りの代償として、貴殿は父王アシャヤカトルの宮殿へと入られよ!」
――それは王の権威の失墜を意味する。さすがにこれにはモクテスマも必死に抵抗した。だが、ほとんど脅迫とも取れる言葉が重ねられ始めると、モクテスマも従わざるを得なくなった。モクテスマが力なく頷いた瞬間、エスパニャの兵たちから歓声が沸き上がった。しかしコルテスはそれをすっと手で制し、アギラールに視線を寄越した。
「おい。お前も何か、ないか?」
「良いのですね」
「ああ」
アギラールはきゅっと唇を結んだ。今度は何を訳させられるのかという顔をしているマリンチェに向かって軽く肩を竦めてみせた。
「もう一つ。願いがあります。モクテスマ殿」
「……なんだ」
「生贄の儀式を一切、やめていただきたい」
――マリンチェの声が震えた。そっと、アギラールは彼女の背を叩いた。
「それは出来ぬ。そんなことをすれば神々のお怒りが地に落ち、この世は永久の夜になるだろう」
「なりません。ここにおられる方が何者であるかは、貴方が一番良くご存知でしょう。コルテス殿はその無意味な儀式を毛嫌いしておられる。それに、朝は必ず来ます。我らの神も、それは確実に保証してくださるでしょう」
「貴方方の神などというものを信じろと」
「そう言っています。モクテスマ殿。貴方に拒否権はないはずです。即刻、貴方の声が届くすべての地に報せを届けるのです。そしてこのテノチティトランでも。一切の生贄などという無益な殺戮を、やめるのです」
その日のうちに、モクテスマの使者はアステカ中へと走っていった。各地で首長たちは驚きと戸惑いを持つことだろう。だが、従うしかないはずだった。その日、華やかなりしアステカの首都テノチティトランは静まり返った。人々は扉を固く閉じ、息を潜めた。しかし、それでも噂は静かに染み渡った。王が〈白い顔〉の人間に囚われた、という噂だった。
今日は、特別な日になる。アギラールは確信した。ベルナル・ディアスに目をやる。
「書き留めておいでですか」
「無論」
「一五一九年、十一月十四日、ですね」
「ああ。今日は――歴史になる」
ベルナル・ディアスがにやりと、笑った。