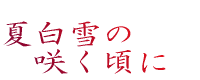
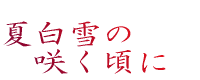
◆
年に一度だけ、ぼくはお父さんたちに連れられて橘のおじさんの家へ行く。
花穂ちゃんに逢える。
ぼくはそれがうれしくて、おじさんの家が見えてきた瞬間、お父さんとお母さんを置いて走り出していた。
「圭一、走ると転ぶぞ」
「転ばないよー」
お父さんの声に、ぼくはそう叫び返した。
走る。走る。走る。ちょっとだけ、ぜえぜえって息が上がってきた。でもぼくは、止まらなかった。
おじさんの家の門をかってに開けて、庭に走っていく。
おじさん家の庭は、シロツメクサがたくさん咲いていた。庭から見上げられるところにある窓は、花穂ちゃんの部屋の窓なんだ。
花穂ちゃんは、シロツメクサがすっごく好きだ。
あ、違った。なつしらゆき、だったかな。花穂ちゃんは、そう呼ぶ。
「花穂ちゃん」
ちょっとだけ息をおちつかせて、ぼくは窓に向かって叫んだ。
「花穂ちゃあん」
少し待つと、窓が開けられて女の子が顔を出した。ふわふわの髪の毛の女の子。花穂ちゃんだ。
花穂ちゃんはぼくを見て、ぱあっとうれしそうに笑った。
「圭ちゃん」
花穂ちゃんはぼくを見つけるとすぐにくるりと窓から遠ざかっていって、すこしするとぱたぱたと足音を立てて庭に出てきた。
「圭ちゃん。いらっしゃい」
少し小さくて高い声で、花穂ちゃんが笑った。
「うん。こんにちは」
答えながらぼくはわくわくで飛びはねたくなっていた。
だって、これはいつもと同じだから。だから、これからまた花穂ちゃんと過ごせるんだって思ったから。
花穂ちゃんとぼくは、いつも一緒に遊んだ。おじさんの家にいる二週間だけは。
花穂ちゃんはぼくより二つ年上だったけど、小さいからぼくとあんまり変わらないみたいだった。お父さんが言うには、花穂ちゃんは病弱、なんだって。すぐに風邪とかひいちゃうから、あんまりお外で遊べないし、体だって小さいんだって。あんまり長いことお外では遊べないけれど、でもこの時期は少しくらいだったら外で遊べる。まだあんまり、暑くなりすぎていない時期だし、寒くもないからだって。花穂ちゃんは、夏白雪が目印なんだって教えてくれた。夏白雪が咲く間は、ちょっとだけお外にいる時間が長くなるって。
もうすぐ夏白雪が枯れちゃうかなって季節に、圭ちゃんは来るのよ。
花穂ちゃんはそう言ってた。
夏白雪の庭で、花穂ちゃんはぼくにゆびわを作ってくれた。
「はい。圭ちゃん、あげるね」
「ゆびわ?」
「うん。そうだよ。あのねぇ」
花穂ちゃんはちょっと恥ずかしそうに笑って、こそこそ話をするみたいにぼくの耳に口を寄せてきた。
「圭ちゃん。花穂、ずっと圭ちゃんと一緒にいたいんだぁ」
花穂ちゃんはそういって、顔をちょっぴり赤くさせてえへへって笑った。ぼくも笑って、うん、って頷いた。
「うん。いいよ。ずっと一緒にいたい。ぼくも」
「ほんとう?」
「ほんとうだよ」
ぼくの言葉に、花穂ちゃんはまたうれしそうに笑った。花穂ちゃんはないしょだよ、って言ってゆびわのことを教えてくれた。結婚ゆびわなんだって。交換し合ったら、結婚できるんだよって花穂ちゃんは言った。
だからぼくらはそれをやった。
だって、一緒にいたかったから。大人になっても、ずっと一緒にいたかったから。
花穂ちゃんの作ってくれた二つの夏白雪のゆびわを、ぼくらは交換しあった。
ぼくの持ってるゆびわを花穂ちゃんの手に。
花穂ちゃんの持ってるゆびわをぼくの手に。
そうしたら、花穂ちゃんはとってもきれいに笑ってくれた。
だからぼくはすごくうれしくて。
ああ、花穂ちゃんのこと大好きだな――って、そう思ったんだ。
◆
「圭ちゃん」
ああ、そうか。これは。
「うん。記憶だよ。圭ちゃん」
そうだね。ねぇ、花穂。
「なぁに、圭ちゃん」
この後に、何があったのかな。
「覚えてないの?」
うん。そうみたいだ。ごめん。
「ううん。いいよ。だって圭ちゃんじゃないもんね」
僕は圭一だよ、花穂。
「うん、そうだね」
教えてくれる?
「いいよ。あのねぇ、結婚式からちょっとあとなの。圭ちゃんがねぇ、十歳になったとき」
白い光が、悪戯っぽく微笑んだ。
くるり。
くるり。
時計の針が、少しだけ進む――
◆
その年のことは、何故だろう、僕はあまり詳しく覚えていない。
昭和十七年。僕が十歳だったときのことだ。
確か、橘の叔父さんが大東亜戦争に出兵したのは覚えている。だけど、それ以外のことが不思議と霧がかっていて記憶が薄れているのだ。秋の肌寒い日の早朝、景色をけぶらせるあの幾重にも重なったような白い霧に似ている。少しだけ肌寒くて湿っていて、呼吸をするのが辛い。そんな霧だ。それが記憶という景色を隠すように重なり合っていて、肌寒さを伝えてくるほどだ。しかも早朝にかかる霧と違い、空気を温める太陽が出て来ないから、一向にその霧がはれる事もない。幾重にも幾重にも重なって、やがてその向こうの本当の事を、本当の景色を溶かしてしまいそうな、そんな霧だ。そんな霧が僕の記憶を邪魔していて、霧の向こうの本当の事はあまり見えない。その霧は厄介なことに、ずっと続いている。
ああ、でも。
霧の幕を少しだけ剥がして覗き込めば、判る事もある。
あの日花穂は泣いていたのだ。
夜中、僕を浅い眠りから引きずり出したのは、花穂の啜り泣きだったんだ。
いつの間に部屋を抜け出したんだろう。
花穂は真夜中の夏白雪の中で、橘の叔父さんが花穂に残して行った懐中時計を握り締めて、泣いていた。
「花穂?」
花穂は泣きじゃくっていた。僕の服のすそを掴んできて泣いた。しきりに、お父様、と繰り返していた。夢でも、見たのだろう。
橘の叔父が大東亜戦争で戦死したことを知るのは、それから随分後のことだから、この時点では判りようがないはずだった。だがもしかしたら、花穂は何かを感じ取ったのかもしれない。まだ酷くなる直前だったこの年に、花穂は何かを感じ取っていたのかもしれない。眠れない夜に不意に襲われる、漠然とした不安感、喪失感、堪らないほどの焦燥感――そういったものに通じる何かを、花穂はこの時感じていたのかもしれない。実際、このあとすぐに戦争は酷くなり、僕はこの家へと疎開することになったのだから、花穂が何かを感じたとしても不思議ではないのだ。
でも僕にとって、それは大した事じゃなかった。
理由じゃない。
大切なのは理由じゃなくて、ただひとつ。
花穂が泣いている。
その事実だった。
花穂の涙は、苦しかった。くっと胸が締め付けられて息が出来なくなりそうな感覚を僕に与えてくるから、花穂の涙は苦しい。だから、見たくなかったし、花穂に泣いてほしくなかった。涙を流す花穂の横顔は確かにとても綺麗だけれど、それ以上に痛いから。
「花穂、花穂」
花穂は答えてこなくて、ただ泣いていた。
胸が痛んだ。
どうしたらいいのだろう。
どうすれば花穂の涙を止められるのだろう。
花穂をこの苦しみから、どうすれば救い出せるのだろう。
幼いながらに、僕は必死に頭をめぐらせた。考えに考えて、そして視線を下に落としたときにそれは入り込んできたのだ。
夏白雪。
シロツメクサの花が。
その白が。その純白が。闇一色だった僕の視界を一瞬にして白に塗り替えてきた。
夏白雪。
シロツメクサの花が。
その香りが。その甘い香りが。僕の鼻腔を満たして肺に入り込んできた。
ああ――
そうだ。この花があったんだ――と。
僕は思い出した。そして笑って見せた。この花がある限り、花穂の大好きな夏白雪の花が咲いている限り、花穂はきっと笑ってくれる。漠然とした不安感や焦燥感、喪失感、そういったものにも涙を流さないでいてくれるはずだ。とても綺麗で、だけどとても痛い横顔を作らないでくれるはずだ。だって僕らはこの花に誓ったから。だから。
闇。
溢れかえるほどの星明りだけが花穂の瞳に浮かぶ涙を照らし出していた。
満面に咲き誇る夏白雪の中で、僕は花穂の肩を強く抱いた。花穂の柔らかい栗毛の髪は、甘い花の香りがする。
震える花穂のぬくもりを腕の中に確かに感じながら、僕は泣きじゃくる花穂に囁いた。
「花穂」
耳元で名を呼ぶと、花穂の体はびくんと震え、縋るような瞳を僕に向けてくる。
「花穂、ごっこあそびをしよう」
僕の言葉に、花穂は涙にぬれた瞳で疑問符を投げかけてきた。
きょとんと見上げてくる花穂の手の中に蹲っていた懐中時計を取りあげる。
金色の、懐中時計。
――なつかしい。
そう。これが僕をここへ導いてくれた――
「ごっこ、あそび……?」
「そう、ごっこあそび。時間をとめようね、花穂」
僕の言葉に、花穂は震える声で訊いて来る。「どうするの」――?
「こうするの」
懐中時計の硝子を開く。露になった文字盤に、その時計の針に、僕は手をかけた。
時計の針をひとまわし。
ひとまわし。
ひとまわし。
逆さにまわして。
「一回り。これで花穂はひとつ時間をさかのぼる」
「……?」
「君は少しずつ、戻っていくんだ。花穂」
くるり。くるり。くるり。
「僕が一番大好きだった君にね」
くるり。くるり。くるり。
花穂はもう何も言わなかった。
くるり。くるり。くるり。
時を戻そう。
僕らが一番、お互いを大切に思いあっていたあの日へ。君が六つで、僕がまだ四つだったあの頃へ。
そしてそこで時を止めよう。
哀しみが二度と訪れないように。痛みが君を襲わないように。
そう。これはそういう、「ごっこあそび」――