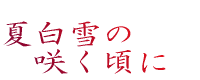
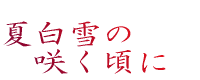
◆
「思い出した?」
うん。思い出したよ、花穂。
「これが魔法の正体だよ」
そうだったね。
「圭ちゃん、花穂を守ってくれたのね」
だって君が泣いていたから。
「うん。あのねぇ、花穂ねぇ、圭ちゃんのこと大好きよ」
僕もだよ。花穂が大好きだ。
「うん。ありがとう」
ねぇ、花穂。
「なぁに、圭ちゃん」
白猫はどうなったんだっけ?
「猫さん?」
うん。猫さん。
「花穂が拾った猫さんね」
そうだっけ?
「圭ちゃん、また忘れてる?」
ごめん、花穂。
「いいよ。だったら、また魔法をかけようよ、圭ちゃん」
そうだね。そうすれば思い出せる。
そう。僕らには魔法がある。
君の持っている、懐中時計の針に指をかけ。
くるり。
くるりと逆さに廻す。
「うん、そうだよ。圭ちゃん」
時計の針がくるくる廻り
明日の足音掻き消して
昨日がも一度今日になる
そんな魔法を教えよう
――そんな魔法を、教えよう――
◆
その日がいつだったのか、僕は正確に覚えている。
そう。昭和二十一年七月二十一日。あの日、僕らは猫を拾ったんだったね。
「ねぇ、圭ちゃん」
夏白雪で冠を作っていた花穂が、不意に手を止めて顔を挙げた。その瞳には、少し不安げな色が浮かんでいる。
「なに、花穂?」
「東京帰っちゃうって、ほんと?」
小鳥のような無垢な仕草で、花穂は首を傾げて訊ねてくる。ぼくより二つ年上の十六歳なのに、とてもじゃないがそうは見えない仕草で。僕はその花穂の頭を軽く撫でてやる。いつものように。
「うん。一度戻らなきゃいけないからさ」
「花穂、やだな。寂しいよ」
青空の下に似合わないしゅんとした表情で花穂が肩を落とした。手に持っている夏白雪の作りかけの花冠が、僅かに力が入った花穂の手によって形を崩している。
「大丈夫だよ、花穂。また必ず戻ってくるよ」
「ほんと?」
「うん、必ず。夏白雪が咲いている間にまた戻ってくる。花穂を迎えに来るよ」
夏白雪――花穂がそう呼ぶシロツメクサの花をさして笑うと、花穂も安心したように微笑んだ。その笑顔が好きだ。
花穂は幼い。
あの日の魔法のせいで、花穂はまだ六つの幼子のままだ。だから僕が、守らなきゃいけない。
「約束だよ、ね、圭ちゃん」
「判ってるよ」
「えへへ」
はにかむように微笑んでいた花穂が、ふっとその顔に疑問符を浮かべた。
「花穂?」
「圭ちゃん、しー、だよ」
しー、と唇に指を当て、花穂はすっと瞼をおろす。その幼い横顔が微笑ましくて、僕は素直に口を閉じた。
十六になった花穂の横顔は、けれど僕があの日にかけた魔法のおかげで、六つのままだ。
とても良い天気だった。
大東亜戦争は敗北という結果で終結し、天皇陛下は人間だと宣言し、少しずつ我が国は変わろうとしているのかも知れない。ただ、僕にとってはそれは大したことではなく、有難いのはこうして空襲に怯える事もなく花穂と外で過ごせる日が戻ってきた、というその事だけだった。
東京よりもこの土地に吹く風は涼しい。とはいえ、そろそろ夏白雪が枯れだす季節だから寒いわけでもない。それが丁度心地良かった。高く青い空に、溶け出した牛乳のような雲が伸びている。風が草木を揺らす音が聞こえた。
「あ」
花穂が声を漏らして瞳を開ける。
「圭ちゃん、聴こえた?」
「ん?」
花穂は頬を膨らませて拗ねた表情を見せてくる。
「猫さんの声っ」
「猫?」
「聴こえたの、どこかにいるよ。ねぇ、圭ちゃん圭ちゃん。猫さん探そうよ」
編み上げた花冠を頭に乗せて、花穂が立ち上がる。くいと僕の腕を引っ張るその仕草が愛しくて笑みが浮かんだ。
こんな風に――こんな風に、花穂が昔のまま笑ってくれるのが嬉しかった。痛みや苦しみ、汚れなどは花穂には似合わない。世の中の総てが汚れに澱んだとしても、花穂のこの無邪気で無垢な笑みだけは澱みに染まる事は無い筈だ。染まってはいけないのだから。この笑みを、僕は守り通さなければならない。あの夜魔法をかけたように。君の美しさだけは、守り通さなければならない。
「ねぇ、圭ちゃんってばぁ」
「判った、判ったよ花穂」
執拗に腕を引っ張ってくる花穂に笑いかけて僕も立ち上がった。花穂がはにかむ。僕らは共に庭を探し始めた。花穂には確かに猫の声が聞こえるらしい。時折四つんばいになって茂みの中を覗き込む花穂の後ろをついていった。
「あっ、いた!」
暫く庭を探し回った後、花穂が声を上げた。
「いたよいたよ、圭ちゃん猫さん」
茂みに顔を突っ込んでいた花穂は、振り返って僕に言う。花穂の髪にくっ付いていた葉を取ってやりながら、僕も覗き込んだ。
――いた。
白い猫だ。
左目は黄金で、右目は青い。野良のわりに毛並みは悪くなかった。ただ、非常に痩せてはいたが。
「猫さん」
花穂が甘えた声で猫に手を伸ばす。白猫も、にゃあ、にゃあと花穂に良く似た甘えた声で鳴いた。可愛い猫だった。
白猫を花穂が抱きかかえる。猫は一瞬びくりと体を震わせたが、花穂に敵意が無いことを感じ取ったのだろう、すぐに甘えるように頬を摺り寄せる。花穂が嬉しそうに目を細めるのを見て、僕は自然と浮かんでくる微笑を感じていた。
「えへへ、可愛いね、猫さん。ねぇねぇ、圭ちゃん猫さん好き?」
「うーん。嫌いではないよ」
「えー。好き? ねぇ、好き?」
「そうだね、好きだよ」
そう言うと、花穂は満足そうに笑った。その笑顔が愛しかった。
花穂の腕の中でにゃあにゃあと甘えた声で鳴く猫の喉を、花穂が撫でる。
その猫の爪が――ふいっと花穂の頬を掠めた。
「いたっ……」
それは、僕が思うに猫はただ甘えただけだったのだろう。ほんの悪戯じみた甘えだったのだろう。だけど僕にはそう考える余裕はなかった。
花穂が、傷ついた。
その情報が脳裏をよぎった時、僕は花穂の腕の中の白猫を叩き落していた。
――うにゃうんっ!
抗議なのか悲鳴なのか、そんな声を上げて猫は夏白雪の中に落ちる。しかし猫という生物は存外器用で、夏白雪の中へ足から着地した。
「圭ちゃんっ」
花穂が驚いたような声を上げる。思わず蹴り付けようとしていた僕から猫を庇うように、しゃがみ込んで猫を抱きかかえた。
花穂の髪のふわりと甘い匂いと同時に、違和感が香ってきた。
「圭ちゃん駄目だよ。そんなことしちゃ、駄目」
猫を抱きかかえ。
咎める様な瞳で。
僕を見つめる花穂の姿に。
その花穂の姿に。
僕はどうしようもない違和感を――覚えてしまった。
「花穂……?」
「だって、痛いでしょ? そういうことしたら駄目なんだよ」
「花穂」
僕の呼び声に、何かしらの変化があったかというと僕自身には判らない。だがその瞬間、確かに花穂の顔色が変わった。
咎めるように見上げていた瞳はさっと色を変えて、拗ねるようなそれになった。
十六の顔色はすうっと溶けて、時を止めたあの六つの顔色になる。夏白雪の花冠がよく似合う、あの幼い顔へ。
「圭ちゃん、だめよー。猫さん痛いよー?」
甘えるような、拗ねるような、そんな声で花穂が僕に言ってくる。
その言葉を聴いた瞬間、僕は総てを悟ってしまった。
ああ――そうか。
花穂の魔法は、解けていたんだ。
いつからだろう。判らないけれど。それとも、最初から魔法なんか、掛かっていなかったのだろうか。
花穂は僕を騙していたのだろうか。騙して、からかっていたのだろうか。天使のような、あの無垢な笑顔を作って――?
例えようのない澱みが、僕の中から沸きあがってくるようだった。
それは騙されていたと言う事に対する怒りだったのだろうか。憎悪だったのだろうか。それとも、それ以外の何かだったのだろうか。判らない。だけどその澱みは確かに血液を伝って僕の全身を支配していこうとしていた。いけない。このままだと、澱みが花穂を包んでしまう。花穂に澱みは似合わないから、僕が守らなくてはいけないのに。ああ、でも、そんな必要自体がないのだろうか。だって花穂は僕を騙していたのだから。
僕を騙していたのだから!
「圭……ちゃん」
不安げな、伺うような声が聞こえた。伺うような。そんなのは、花穂には似合わないのに。
僕は知らずに閉じていた瞼を上げて、ゆっくりと微笑を作った。
「花穂。猫、好きなんだね」
僕の言葉に何を感じたのだろう。花穂はふぅっと表情を六つの幼子のそれに変えて、にっこりと笑ってきた。
「うん。猫さん大好き。でもねでもね」
「……うん?」
「花穂、圭ちゃんのほうが大好きだなぁ」
白猫が、花穂の足元でにゃあと鳴いた。
花穂は立ち上がり、僕の顔を見上げて微笑んでいる。幼子の笑みを作って。――作って。
「圭ちゃん圭ちゃん。花穂とずっと一緒にいてくれる?」
夏白雪の花冠を頭に乗せたまま、花穂が笑う。
幼い子供のような笑顔で。
十六歳の顔立ちのまま、幼すぎる笑みを向けてくる。
僕は花穂の頭の上に咲く夏白雪を見つめて、呟いた。
「いいよ。花穂がずっと、いい子でいたならね」
ずっと――ずぅっと。
言い捨てて、かするように花穂の頭を撫でて、夏白雪を踏み潰して僕は歩き出す。
「圭ちゃん……! 花穂、ずっといい子でいる! いい子でいるよ! だから……、だから、おこらな――」
「花穂」
すがるような花穂の声に、僕は低く名前を呼んだ。
花穂がひっと息を呑むのが聞こえた。
だめだよ、花穂。
君は僕の言葉の裏側を察しちゃいけない。
君は頭が弱くて子供なんだから。察しちゃいけないんだよ、花穂。
「花穂」
もう一度だけ名前を呼んで振り返った。
花穂は夏白雪の冠を頭に乗せたまま、幼子の笑顔で首を傾げた。
「どうしたの圭ちゃん。お顔、こわぁい」
「――何でもないよ」
いい子だね、花穂。
いい子だね、花穂。
ああ、どうして。君はこんなにも無垢で汚れもなく美しいのに、そのままであり続けてくれないのだろう。僕の中の澱みは、どうしてこれほどまでに全身を支配していくのだろう。
それは君が愛しいからだろうか。どうしようもなく愛しいからだろうか。
君の夏白雪のように真っ白な笑みを、僕はどうしても守りたいからだろうか。
僕は花穂の体を抱きしめた。
甘い花の香りがした。夏白雪の微かな香りと、花穂の髪の匂い。匂いは僅かしか漂っては来ないのに、何故だろう、僕はその香りに酔いそうだ。
花穂。
君を守るよ、花穂。
夏白雪のように純粋で、小鳥のように無垢な、君の笑みを。
硝子細工のように儚く脆い、君自身を。僕は、守り抜くよ、花穂。
だって君は美しいから。とてもとても、美しいから。
「圭ちゃ」
腕の中の花穂の声に反応したように、足元で猫が鳴く。甘えるように、乞うように、穢れた声で鳴いてくる。
ああ、そうか。
この猫のせいで、君の魔法は解けたんだろうか、花穂。
だったら。
この猫がいなければ、花穂の大切に思うもの総てをこの手で摘み取ってしまえば、花穂は美しいままであり続けるのだろうか。美しい無垢な笑みで、僕だけを見てくれるのだろうか。
それとも。
花穂さえをも、摘み取ってしまうことが出来れば――花穂は永遠に僕だけのものになるのだろうか。
にゃあ。にゃあ。と。
夏白雪の中で猫が鳴く。
僕は花穂をきつくきつく抱きしめながら、意識が白に染まっていくのを感じていた。
夏白雪の白が、意識を支配していくのを感じていた。
だめだ。
僕はその瞬間、確かに総てを理解していた。理解した。だからこそ意識は白に染まろうとしていたのだろうけれど、だからこそ僕は強く花穂の体を抱いていた。
離れたくなんてなかった。
離れたくなんてなかった。
花穂と。
花穂と。
花穂と。
――そして、夏白雪の純白が視界と意識を総て包み込んでいく。
僅かに残ったのは、にゃあという猫の声と、甘い花の香りだけで。
それもやがて、夏白雪の純白が奪い取っていった。