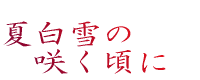
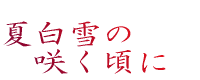
◆
目覚めると、僕はもうただの誠一だった。
「誠一」
「……じいちゃん」
薄暗い視界の中、心配げな顔のじいちゃんが僕を覗き込んでいた。
夜だった。何もなかった。あの酔いそうに甘い花穂の髪の香りも、柔らかい花穂の髪の手触りも、何もなかった。ただ金色の懐中時計だけが、もう動いていない時計だけが、僕の手の中にあった。
花穂の髪が手の中にないことが、ただ、寂しかった。
「大丈夫か、誠一。こんなところで寝てたら風邪を引くぞ」
「……うん」
そこはじいちゃんの家だった。だけどよく見渡してみれば、あの家と――橘の家ととても雰囲気が似ている。
ぼんやりとした意識のまま、デッキチェアの背もたれから身を起こした。僕の隣に立っているじいちゃんは、風呂上りのようで首からタオルをかけていた。
夢――だったのだろうか。
虫の鳴く音と風の通る音。それから、星明りと足元に咲く夏白雪の花。部屋から漏れ出て来るオレンジ色の光。
それはついさっきまで知っていたものとよく似ていて、だけど何かが確かに違った。
「誠一?」
じいちゃんが心配そうに僕の背中を撫でる。じいちゃん。早坂圭一。僕。早坂誠一。それは判る。けれど。
なんだかとても気持ちがふわふわしていた。背中にタンポポの綿毛が生えたみたいに、あるいは重力というものをすっかりどこかに置き忘れてきたみたいに、僕の心はふわふわと浮いていて地面を踏みしめていられないようだった。
ぼんやりとした意識の中でふと思い出す。この家のこと。退職後に、じいちゃんがいきなり買って母さんたちをびっくりさせていたことを。ああ、そうか。橘の手を離れたのだろうか、この家は。それから、じいちゃんが買ったのだろうか。花穂の思い出を。
「驚いたんだぞ。風呂から上がってきたら、誠一が懐中時計握ったまま寝てるんだからなぁ」
「じいちゃん」
「うん?」
苦笑するじいちゃんの声を遮って、僕は訊いた。
「この家って、古いの?」
質問の意味が判らなかったのか、それともあまりに唐突過ぎたのか、じいちゃんは一瞬目をぱちくりさせて、それから懐かしそうに目を細めて笑った。その笑い方は、懐中時計を見ていた時の笑顔と同じだった。
「古いな。随分古い。じいちゃんと同じくらいかなぁ。まぁ、改築とかはしてるがな」
「時間が止まってるから、この家にしたの?」
僕の言葉に、じいちゃんはすっと表情を消した。
「……誠一……?」
「ねぇ、じいちゃん」
表情が無くなって青白い顔になったじいちゃんを無視して、僕は呟いた。
闇夜の中、真っ白に健気に咲く、無垢な夏白雪の庭を一瞥して。
「花穂は、どこ?」
「ここにいるよ」
――甘い声がした。
ふわふわしていた心が、ゆっくりと温まるのを感じた。この気持ちは、安堵って奴なのかもしれない。
自然と浮かんだ笑みのまま、僕は声のする方向に目をやった。
庭先の花壇。
そこに、花穂はいた。
ふわふわの栗毛。幼い笑顔。柔らかそうなネグリジェのようなワンピース。あの時と何も変わらない、花穂の姿。
「……花、穂……」
じいちゃんが、僕の隣で擦れた声を漏らした。
花穂が、悪戯する子供のような笑顔でじいちゃんを見つめている。
「こんばんは、圭ちゃん」
「花穂……」
夢か何かと思っているのだろうか。まるでうわ言のようにじいちゃんは花穂の名前を繰り返している。
「うん。花穂だよ。圭ちゃん」
花穂は楽しそうにくすくすと笑っていた。じいちゃんは青褪めた顔のまま、花穂を凝視していた。
手の中の時計は、もう壊れて動かない。時を止めたまま、閉じ込めている。あの時のまま。
「どう、して……」
「だって圭ちゃん、花穂を迎えに来てくれるって約束したのに、来ないんだもん。花穂、ずっと、ずぅっと待ってたのよ?」
「それは」
じいちゃんが擦れた声で呟きながら頭を振った。
――それは、あの日君がいなくなったから。この世から、いなくなったから。
じいちゃんの言葉と僕の言葉は、不思議と同じタイミングで呟かれていた。
「うん。でも花穂、待ってたのに。圭ちゃん、花穂のこと嫌いになっちゃったの?」
しゅん、と花穂が肩を落として俯いた。悲しげな色の瞳に、じいちゃんは慌てたように強く左右に首を振っている。
――違う。君を愛していた。愛していたんだ、花穂。
壊れてしまうくらい、強く愛していたんだ。そう。圭一は確かに、花穂を愛していたんだ。自分を壊してしまうくらい強く。花穂を壊してしまうくらい深く。それは、僕自身がよく判ってる。
だけど、ずっと、ずっと愛し続けるにはあまりに時間は残酷で。魔法は、この家以外には働かなくて。
じいちゃんは結局、いつか花穂を忘れて――ううん。忘れたふりをして――他の女性と、つまり僕のばあちゃんと結婚して、子供を生んで、生きてきたんだ。だから今、僕がいる。
僕はじいちゃんに対して、どういう感情を抱けばいいのか判らなかった。
花穂の顔を悲しみに染めている原因を生み出したのは、確かにじいちゃんだけど、じいちゃんがいたから、僕は、花穂に、逢えた。
寂寥とした空気が、夏白雪の庭に満ちた。
じいちゃんと花穂は静かに見詰め合っている。僕はそんな二人を、ただ外から眺めている。
静かだった。
あの日の朝と同じように静かだった。ぴんと張り詰めた空気の中に邪魔な音は何もない。静寂の闇を破るように、やがてじいちゃんは大切な宝物を口にするようにゆっくりと、告げた。
「花穂」
「なぁに、圭ちゃん」
じいちゃんは、目を細めて花穂を見た。
鏡でも見ているだろうかという錯覚に、僕は一瞬陥る。その顔は、もうとっくに七十を過ぎたじいちゃんの顔じゃなかったから。年輪は確かに皺となって刻まれているはずなのに、じいちゃんの顔は僕と変わらないくらい若くて、少年のような穏やかさだった。
「愛してたよ」
君をずっと。とても深く。
――愛していたよ。
その言葉に、花穂は満足そうにはにかんで――
「うん。圭ちゃん。花穂もね、圭ちゃんのこと、大好きだよ」
――最後の言葉を残して、すぅっと夏白雪の色に染まって消えた。
夏白雪の庭に、もう白い光はない。
花穂の光は、もうない。
ただ静かに、淑やかに、星明りが降り注いでいるだけだった。
じいちゃんは暫く何も言わず、ただ、じっと、夏白雪の花の白さを目に焼き付けるように見つめていた。
「じいちゃん」
どれくらいそうしていたか、判らない。
随分時間がたった後、僕は懐中時計を握ったまま、じいちゃんに呟いた。
「人を好きになるのって、難しいね」
僕の言葉にじいちゃんは瞼を下ろした。
「そうだな」
大切で。
だから、守りたくて。守りたくて、壊してしまう。
人を好きになるのは、難しいことなんだって。
僕はその日、初めて知った。
夏白雪を見つめるじいちゃんの瞳には、うっすらと、星明りを照り返す雫が浮かんでいた。