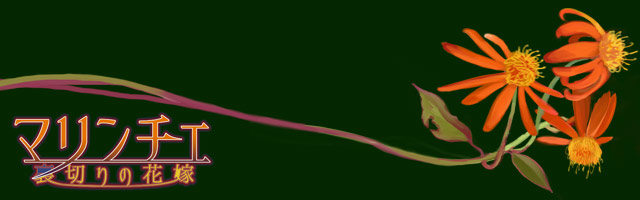Chapter1. 東の地より来たりしもの - 2
◇
奴隷には奴隷なりの情報網がある。人づてに聞いた敗戦の事実は、マリナリを困惑させた。
「負けたって。相手は何者なの。モクテスマではないのでしょう」
ティルパはくるくると巻く自分の髪をいじりながら、僅かに首を傾げた。
「きっとマリナリは信じないと思うわ。あのね、神様なんですって」
意味ありげに声を潜めるティルパに、マリナリは呆れた目を向けた。
「何を寝ぼけているの、ティルパ」
「あら。みんなそう言ってるのよ。寝ぼけているというのならあたしだけの話ではないわ。首長もだれも、寝ぼけていることになっちゃう。ねぇ、マリナリ。貴女だって聞いたことはあるでしょう? ――『帰ってくる神様』のお話」
マリナリは思わず眉根を寄せた。ティルパは好奇心が強く、それ故に奴隷にしては雑多な知識を持っている。だが、マリナリとは違う。マリナリは今でこそ奴隷の身だが、幼い頃はきちんと勉学を嗜んでいた。だからこそ、ティルパの曖昧な言葉が強い意味を持った。
「そうか。今年は……」
「何か知ってるの?」
「一の葦の年。ケツァルコアトルが帰ってくるとされている年よ」
「んーっと、帰ってくる神様のこと?」
「そう」
マリナリは自然と止まっていた手を動かし始めた。ティルパも慌てて同じ動作をする。
トウモロコシを粉にしているのだ。朝は粗末な粥だったが、昼には香ばしいトルティヤが頂けるだろう。
「神々に追い出されたケツァルコアトルは、平和の神様だそうよ。そして神は追い出されるときに言ったらしいわ。また戻ってくる、って。東の地から戻ってきて、世界を統治するって。その予言が、今年」
言い終わる前に、ティルパは丸い目をきらきらと輝かせた。
「じゃあ、昨夜の戦相手って、やっぱり神様なのね」
「どうかしら」
マリナリはふん、と鼻をならした。
「平和を望む神が、夜討ちなんて卑怯な戦をやるとは思えないわ」
朝の仕事を一通り終えた頃、マリナリとティルパは首長から呼び出しを受けた。他にも十数人の女奴隷が同時に呼び出され、何事かとマリナリがいぶかしんだ時、ようやく首長は口を開いた。
「おまえたちも知っていると思うが、我々は昨晩戦に負けた。先ほどまで近隣の首長たちと会合を行っていたのだが、そこでの決定事項を通達する」
苦い声だ。
「これは〈花の戦争〉ではない。だが、戦である以上礼儀はある。負けた我々は、彼らに捧げ物をすることを決めた。金製の装飾具などと――お前たちだ」
マリナリもティルパも、他の奴隷たちもさして驚きはしなかった。奴隷とは得てしてそういうもので、自分たちの身分も心得ている。いつ何時、明日の儀式の生け贄として指名されたとしてもおかしくはないのだ。
マリナリたちは身を清め、香を焚いた。いつも与えられているものよりは幾分かましな衣装を着て、昼を迎えた。
相手側は野営をしているようだった。ぞろぞろとそこに赴くと、最初は少々の緊張感が辺りに立ち込め、すぐに和解の空気に変わった。
首長が前に出て口上を延べる。ややあってからマリナリたちを振り返った。皆一様に視線を下げながら前に出る。
「顔を上げなさい」
マヤ語だった。顔を上げると、そこに男がいた。
白い顔だった。なるほど、とマリナリは胸中で独りごちた。ケツァルコアトルは確かに白い顔の神と言われている。その顔立ちは精悍だった。この辺りのメヒコ人などにはみられないような、汚らしいまばらな髭が顔を覆っている。値踏みするような眼差しに、反射的に嫌悪感を覚えた。その瞳も、光の具合によって色が変わって定まらない。
身につけているのは、見たこともない衣装だった。とにかく、硬そうだという印象だ。ぎらぎらとしていて、洒落っ気も何もない。重そうで、粗暴な気配が漂っている。
「――」
男が何かを言ったようだった。だが、低い声音で呟かれた言葉はこの辺りで使われているマヤ語でも、マリナリの故郷で使われていたナワトル語でもなかった。聞き覚えのない響きでは、意味もとれない。
ふと視線を逸らし、マリナリはすぐに目を見開くことになった。
(あの男……!)
昨晩遭遇した男が側にいた。驚愕しながらも、納得する。先ほどのマヤ語は、あの男の声だったようだ。どうやらこの一団でマヤ語を話せるのはあの男だけのようだ。髭の男と二、三、言葉を交わした後、彼はこちらを見た。男も気がついたのか、一瞬顔をしかめる。
「昨日の奴隷か。コルテス殿がお前を気に入ったようだ。傍に来い」
「コルテス? それがあの髭の名前?」
「そうだ。エルナン・コルテス殿。我が隊の指揮をされている」
「ひとつ訊いてもいいかしら」
「なんだ」
「彼はケツァルコアトルなの?」
マリナリの率直な問いかけに、隣でティルパが目を丸くした。
「ケツァル……? なんだそれは」
「違うのね。なら、どうでもいいわ」
深く説明してやる理由もない。マリナリはそこで言葉を切り、一団に目を滑らせた。全体として、黒髪の者が多いようだった。時々、赤や茶色が混じっていた。肌の色は白い者ばかりだ。背丈はまちまちだが、皆たくましい腕をしている。
ただ、数人少しばかり雰囲気の違う者がいた。マリナリはそっと、目の前の男を見上げた。たとえば、この男だ。戦人というには線が細い印象を受けた。かといって、弱々しい雰囲気でもない。服装も皆とは少し違っている。黒を基調とした、裾がずるりと長い服。どことなく神聖な雰囲気さえもある。
そして、その雰囲気の違う者たちの中でさえこの男は際だっていた。何せ、金色の髪はこの男だけだったのだ。
(人間よね? 不思議ね)
青い瞳に、陽色の髪。そして白い肌。今にも空に溶けて消えてしまうのではないかと思えた。
マリナリが物思いに耽っているうちに、ぐいと顎を捕まれた。
「な――んっ」
目前にいたのは、あの髭の男――コルテスだった。そして彼はそのまま、マリナリに口付けたのだ。一瞬ではあったが、確かに唇に残った感触に、マリナリは全力で抗った。突き飛ばし、身をはがした。同時に、右手を降りあげる。
――パンッ!
派手に響いた音が、一瞬辺りを沈黙へと追いやった。
男はにやり、と口の端に笑みを刻んでいる。
「マ、マリナリ」
後ろでティルパの声がした。友の心配そうな声を背に浴びながら、マリナリはコルテスを見据えたまま、告げた。
「私は奴隷のマリナリ。確かに今、首長により貴方に受け渡された。貴方のものになった。けれど私は商売女ではないわ。奴隷には奴隷なりの生き方もある。もし商売女になれというのなら、私はここで私の心臓を神に捧げてやるわ」
凛と言葉が響く。殺されるかも知れないとは思った。奴隷という身分が判っていないわけではない。時に商売女たちよりも酷く、意思などないように慰め者にされることもある。だが、マリナリは嫌だった。生まれてから十七年。奴隷になってから数年。自分が望むように事態が動いたことなどほとんどなかったように思う。だが、どんな時でも自分の心と体だけは自分のものだった。すべてを失い奴隷になった時でさえ、心と体は失わなかった。だからこそ、マリナリは拒絶する。
心を殺して生きるくらいならば、死を選ぶ。
それは命を粗末に考えているわけではない。ただ単純に、マリナリの心はマリナリの命そのものと同価値というだけだ。
暫く誰も声を上げなかった。そして――
弾けるように笑い声があがった。コルテスが大口を開けて笑っだのだ。さすがにこの反応にはマリナリも驚いた。
コルテスはひとしきり笑った後、隣の金色の髪の男に何かを話しかけた。マリナリには判らない言葉を幾度か交わした後、またあの、にやりと太い笑みだけをマリナリに向けてから踵を返した。野営の陣へと向かっていく。
「コルテス殿の温情に感謝するんだな」
立ち去っていく背中を見ているマリナリに声がかかった。マヤ語だ。
「感謝なんてするわけないでしょう」
「口の減らない女だ。……コルテス殿は面白い女だと笑っていたがな」
そんな評価など望んでいない。鼻を鳴らすマリナリに、彼は短く嘆息した。
「夜が来る前に隊を引き上げ一度船に戻る。それまでは、自由にしていてもいいとのお達しだ」
奴隷には奴隷なりの情報網がある。人づてに聞いた敗戦の事実は、マリナリを困惑させた。
「負けたって。相手は何者なの。モクテスマではないのでしょう」
ティルパはくるくると巻く自分の髪をいじりながら、僅かに首を傾げた。
「きっとマリナリは信じないと思うわ。あのね、神様なんですって」
意味ありげに声を潜めるティルパに、マリナリは呆れた目を向けた。
「何を寝ぼけているの、ティルパ」
「あら。みんなそう言ってるのよ。寝ぼけているというのならあたしだけの話ではないわ。首長もだれも、寝ぼけていることになっちゃう。ねぇ、マリナリ。貴女だって聞いたことはあるでしょう? ――『帰ってくる神様』のお話」
マリナリは思わず眉根を寄せた。ティルパは好奇心が強く、それ故に奴隷にしては雑多な知識を持っている。だが、マリナリとは違う。マリナリは今でこそ奴隷の身だが、幼い頃はきちんと勉学を嗜んでいた。だからこそ、ティルパの曖昧な言葉が強い意味を持った。
「そうか。今年は……」
「何か知ってるの?」
「一の葦の年。ケツァルコアトルが帰ってくるとされている年よ」
「んーっと、帰ってくる神様のこと?」
「そう」
マリナリは自然と止まっていた手を動かし始めた。ティルパも慌てて同じ動作をする。
トウモロコシを粉にしているのだ。朝は粗末な粥だったが、昼には香ばしいトルティヤが頂けるだろう。
「神々に追い出されたケツァルコアトルは、平和の神様だそうよ。そして神は追い出されるときに言ったらしいわ。また戻ってくる、って。東の地から戻ってきて、世界を統治するって。その予言が、今年」
言い終わる前に、ティルパは丸い目をきらきらと輝かせた。
「じゃあ、昨夜の戦相手って、やっぱり神様なのね」
「どうかしら」
マリナリはふん、と鼻をならした。
「平和を望む神が、夜討ちなんて卑怯な戦をやるとは思えないわ」
朝の仕事を一通り終えた頃、マリナリとティルパは首長から呼び出しを受けた。他にも十数人の女奴隷が同時に呼び出され、何事かとマリナリがいぶかしんだ時、ようやく首長は口を開いた。
「おまえたちも知っていると思うが、我々は昨晩戦に負けた。先ほどまで近隣の首長たちと会合を行っていたのだが、そこでの決定事項を通達する」
苦い声だ。
「これは〈花の戦争〉ではない。だが、戦である以上礼儀はある。負けた我々は、彼らに捧げ物をすることを決めた。金製の装飾具などと――お前たちだ」
マリナリもティルパも、他の奴隷たちもさして驚きはしなかった。奴隷とは得てしてそういうもので、自分たちの身分も心得ている。いつ何時、明日の儀式の生け贄として指名されたとしてもおかしくはないのだ。
マリナリたちは身を清め、香を焚いた。いつも与えられているものよりは幾分かましな衣装を着て、昼を迎えた。
相手側は野営をしているようだった。ぞろぞろとそこに赴くと、最初は少々の緊張感が辺りに立ち込め、すぐに和解の空気に変わった。
首長が前に出て口上を延べる。ややあってからマリナリたちを振り返った。皆一様に視線を下げながら前に出る。
「顔を上げなさい」
マヤ語だった。顔を上げると、そこに男がいた。
白い顔だった。なるほど、とマリナリは胸中で独りごちた。ケツァルコアトルは確かに白い顔の神と言われている。その顔立ちは精悍だった。この辺りのメヒコ人などにはみられないような、汚らしいまばらな髭が顔を覆っている。値踏みするような眼差しに、反射的に嫌悪感を覚えた。その瞳も、光の具合によって色が変わって定まらない。
身につけているのは、見たこともない衣装だった。とにかく、硬そうだという印象だ。ぎらぎらとしていて、洒落っ気も何もない。重そうで、粗暴な気配が漂っている。
「――」
男が何かを言ったようだった。だが、低い声音で呟かれた言葉はこの辺りで使われているマヤ語でも、マリナリの故郷で使われていたナワトル語でもなかった。聞き覚えのない響きでは、意味もとれない。
ふと視線を逸らし、マリナリはすぐに目を見開くことになった。
(あの男……!)
昨晩遭遇した男が側にいた。驚愕しながらも、納得する。先ほどのマヤ語は、あの男の声だったようだ。どうやらこの一団でマヤ語を話せるのはあの男だけのようだ。髭の男と二、三、言葉を交わした後、彼はこちらを見た。男も気がついたのか、一瞬顔をしかめる。
「昨日の奴隷か。コルテス殿がお前を気に入ったようだ。傍に来い」
「コルテス? それがあの髭の名前?」
「そうだ。エルナン・コルテス殿。我が隊の指揮をされている」
「ひとつ訊いてもいいかしら」
「なんだ」
「彼はケツァルコアトルなの?」
マリナリの率直な問いかけに、隣でティルパが目を丸くした。
「ケツァル……? なんだそれは」
「違うのね。なら、どうでもいいわ」
深く説明してやる理由もない。マリナリはそこで言葉を切り、一団に目を滑らせた。全体として、黒髪の者が多いようだった。時々、赤や茶色が混じっていた。肌の色は白い者ばかりだ。背丈はまちまちだが、皆たくましい腕をしている。
ただ、数人少しばかり雰囲気の違う者がいた。マリナリはそっと、目の前の男を見上げた。たとえば、この男だ。戦人というには線が細い印象を受けた。かといって、弱々しい雰囲気でもない。服装も皆とは少し違っている。黒を基調とした、裾がずるりと長い服。どことなく神聖な雰囲気さえもある。
そして、その雰囲気の違う者たちの中でさえこの男は際だっていた。何せ、金色の髪はこの男だけだったのだ。
(人間よね? 不思議ね)
青い瞳に、陽色の髪。そして白い肌。今にも空に溶けて消えてしまうのではないかと思えた。
マリナリが物思いに耽っているうちに、ぐいと顎を捕まれた。
「な――んっ」
目前にいたのは、あの髭の男――コルテスだった。そして彼はそのまま、マリナリに口付けたのだ。一瞬ではあったが、確かに唇に残った感触に、マリナリは全力で抗った。突き飛ばし、身をはがした。同時に、右手を降りあげる。
――パンッ!
派手に響いた音が、一瞬辺りを沈黙へと追いやった。
男はにやり、と口の端に笑みを刻んでいる。
「マ、マリナリ」
後ろでティルパの声がした。友の心配そうな声を背に浴びながら、マリナリはコルテスを見据えたまま、告げた。
「私は奴隷のマリナリ。確かに今、首長により貴方に受け渡された。貴方のものになった。けれど私は商売女ではないわ。奴隷には奴隷なりの生き方もある。もし商売女になれというのなら、私はここで私の心臓を神に捧げてやるわ」
凛と言葉が響く。殺されるかも知れないとは思った。奴隷という身分が判っていないわけではない。時に商売女たちよりも酷く、意思などないように慰め者にされることもある。だが、マリナリは嫌だった。生まれてから十七年。奴隷になってから数年。自分が望むように事態が動いたことなどほとんどなかったように思う。だが、どんな時でも自分の心と体だけは自分のものだった。すべてを失い奴隷になった時でさえ、心と体は失わなかった。だからこそ、マリナリは拒絶する。
心を殺して生きるくらいならば、死を選ぶ。
それは命を粗末に考えているわけではない。ただ単純に、マリナリの心はマリナリの命そのものと同価値というだけだ。
暫く誰も声を上げなかった。そして――
弾けるように笑い声があがった。コルテスが大口を開けて笑っだのだ。さすがにこの反応にはマリナリも驚いた。
コルテスはひとしきり笑った後、隣の金色の髪の男に何かを話しかけた。マリナリには判らない言葉を幾度か交わした後、またあの、にやりと太い笑みだけをマリナリに向けてから踵を返した。野営の陣へと向かっていく。
「コルテス殿の温情に感謝するんだな」
立ち去っていく背中を見ているマリナリに声がかかった。マヤ語だ。
「感謝なんてするわけないでしょう」
「口の減らない女だ。……コルテス殿は面白い女だと笑っていたがな」
そんな評価など望んでいない。鼻を鳴らすマリナリに、彼は短く嘆息した。
「夜が来る前に隊を引き上げ一度船に戻る。それまでは、自由にしていてもいいとのお達しだ」