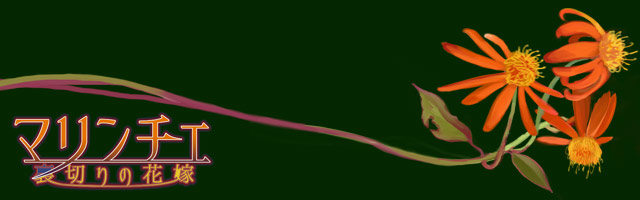Chapter3. 犠牲と覚悟 - 1
モクテスマは〈蛇の家〉と呼ばれる建物の中で、使者の報せを聽いていた。
予兆は随分前からあった。
最初は焔だった。矢のような焔は首都テノチティトランの上空を東へ駆けていった。〈支配者の家〉と呼ばれた大神殿は原因不明で焼け落ちた。昼間には星が落ちた。星は昼の空を落ちていき、その最中に鈴の音の合唱が聞こえた。
市民の間の噂では、夜ごとテノチティトランでは泣き女が現れ、喚くという。それも、民の終わりや破滅を告げながら、だ。
そう言った様々な不吉と呼ばれる兆しの中持たされた報せが〈白い顔〉の来訪だった。
昏い感情が渦巻いている。アステカの民はもともと、この地にあったわけではない。移住してきた民だ。元々この地におわした神が、帰ってきたとしたら。そしてこの地を統治するとすれば。
このテノチティトラン――しいてはアステカ帝国は滅ぶだろう。
神か。それともただの異人か。
歓迎か。拒絶か。
ふたつの選択の前で、アステカの帝王モクテスマ二世は決めかねていた。
◇
マリンチェのことを見込んでか、コルテスはマリンチェにエスパニャ語を学ぶようにと告げた。師はアギラールだ。マリンチェにとってエスパニャの言葉を学ぶのは苦痛ではなかった。もとより、マリンチェは勉学が好きであった。奴隷としてタバスコに送られる前は、一時期ではあったが華やかなりしアステカの都、テノチティトランで勉学に励んでいたこともある。そしてなにより、エスパニャの言葉のくるりと舌の上で回るような独特な音が好きだった。アギラールはアールの音と言っている。
目の前では不思議な線が綴られていく。アギラールが言うにはこれは文字だそうだ。
「変な形ね」
マリンチェの言葉に、ペンを走らせていた初老の男性は少し困ったように微笑んだ。ベルナル・ディアス。コルテス軍の歩兵のひとりだが、もっぱら記録を取るのを仕事としているらしい。ただ、話しかけたところで彼はマヤ語を理解しないので会話にはならない。しかしながら、文字が綴られていくのを見るのが楽しく、マリンチェは良く彼の作業を見ていた。
「またベルナル・ディアス殿に絡んでるのか」
苦笑と共に声がかけられる。アギラールだ。
「絡んでないわよ別に。見てただけ」
「そうか。ところでマリンチェ、少し来て欲しい」
アギラールの言葉に、マリンチェは目を瞬かせた。言われるがままついていくと、甲板の上はざわめいていた。誰何の声に怒号、不安げな響きも混じっている。ただ事ではないとマリンチェは眉をひそめた。
「何事なの」
「小舟が近づいてきている」
アギラールが短く答えた。マリンチェは反射的に駆けだした。身を乗り出して見やる。すぐそばに小舟は来ていた。乗っているのはふたり。格好から見るに、メヒコの民のようだった。
「――は誰だ!」
一瞬、聴き間違いかと思った。だがすぐに気付く。マヤ語ではない。もちろん、エスパニャの言葉でもない。アギラールもそれは判っていたのだろう。
「ナワトル語だわ」
「判るのか、マリンチェ」
「私の故郷の言葉よ」
アギラールが短く頷いた。最初から、マリンチェが判るかもしれないと踏んで連れてきたのだろう。
「なんと言っている」
「この軍の隊長は誰だって。お目通しを願いたいって」
マリンチェがマヤ語に訳したものを、今度はアギラールがエスパニャ語に訳してコルテスに告げた。いつの間にか甲板に来ていたコルテスはアギラールの言葉に一つ静かに頷いた。
来訪者は丁重にもてなされた。ただそれは、あくまで見た目だけだとマリンチェはすぐに気付いた。何かあればすぐに切り捨てられる位置に、アロンソが静かに微笑んだまま立っている。穏やかな彼がかなりの剣の使い手だと言うことを今のマリンチェは知っていた。
来訪者はモクテスマの使いでテウディレと名乗った。テウディレは絵描きを携えていた。絵描きはテウディレが会談している間もずっと筆を走らせていた。
「しかして貴殿は我らに何用かね」
コルテスの言葉をアギラールがマヤ語に、そのマヤ語をマリンチェがナワトル語に訳すことで会談は進められた。
「それはこちらの問いたいことと同じです。何故こちらにいらした。貴方方は何者か。我が王はその確認のために私をよこしました」
「我らはキューバのベラスケス提督の命により、貴殿等との貿易と友好をはかるために来た」
アギラールが訳したコルテスの言葉を、マリンチェはナワトル語に訳さなかった。少し、逡巡する。アギラールが眉をひそめた。
「どうした」
「そのまま言っていいと思う? 彼はモクテスマの使いよ。こっちの出方をうかがっているけれど、それ以上に自分の出方を考えあぐねていると思う」
「なぜそう思う」
「モクテスマ二世は臆病者で有名なのよ。この答え一つで、戦争になるか否かが決まりかねないわよ」
「ふむ」
アギラールは頷いて、エスパニャ語でコルテスに何かを話した。少ししてからマリンチェに告げた。
「お前の好きにして見ろ、とのことだ」
「何それ。そんなんでいいの」
多少呆れながらも、マリンチェは少し考えてからナワトル語でこう言った。
「我ら〈白い顔〉の一団は東の地より、貴殿等と友好を結ぶためにやってきた」
嘘ではない。だが、そのままでもない言葉を告げた。どちらともとれる曖昧な言葉は、マリンチェの思惑通り働いたらしい。テウディレは黙ったまま、何かを考え込んだ。そして、その日は去っていった。またすぐに来ると言って、だが。
「ご苦労だった。マリンチェ」
「貴方もね、アギラール。あれで良かったの?」
「コルテス殿がお前に任せるとおっしゃったのだから構わないだろう」
アギラールが涼しい顔で言う。それから、少し微笑んだ。
「助かった。ナワトル語、というのだな」
「ええ。アステカはナワトル語が殆どよ。タバスコのあたりはマヤ語だけど、ここから先はナワトル語が殆どだと思うわ」
「違う可能性も?」
「サン・フアン・デ・ウルア島の奥の方は別の言語の民族もいたと思うけど、詳しくはないわ」
アギラールが頷いた。
「どちらにせよ、お前がいないと話にならんと言うわけだな、マリンチェ」
「かもね。あと、私がエスパニャ語をものにするまでは、貴方も」
「判っている。頼りにしている、マリンチェ」
――頼りにしている。
その言葉に、マリンチェはぱちくりと瞬きをした。それは、必要とされているということだ。自分を必要とされている。それは、どれくらいぶりの実感だろうか。
胸の奥でくすぶった感情を押し込め、マリンチェは小さく頷いた。
予兆は随分前からあった。
最初は焔だった。矢のような焔は首都テノチティトランの上空を東へ駆けていった。〈支配者の家〉と呼ばれた大神殿は原因不明で焼け落ちた。昼間には星が落ちた。星は昼の空を落ちていき、その最中に鈴の音の合唱が聞こえた。
市民の間の噂では、夜ごとテノチティトランでは泣き女が現れ、喚くという。それも、民の終わりや破滅を告げながら、だ。
そう言った様々な不吉と呼ばれる兆しの中持たされた報せが〈白い顔〉の来訪だった。
昏い感情が渦巻いている。アステカの民はもともと、この地にあったわけではない。移住してきた民だ。元々この地におわした神が、帰ってきたとしたら。そしてこの地を統治するとすれば。
このテノチティトラン――しいてはアステカ帝国は滅ぶだろう。
神か。それともただの異人か。
歓迎か。拒絶か。
ふたつの選択の前で、アステカの帝王モクテスマ二世は決めかねていた。
◇
マリンチェのことを見込んでか、コルテスはマリンチェにエスパニャ語を学ぶようにと告げた。師はアギラールだ。マリンチェにとってエスパニャの言葉を学ぶのは苦痛ではなかった。もとより、マリンチェは勉学が好きであった。奴隷としてタバスコに送られる前は、一時期ではあったが華やかなりしアステカの都、テノチティトランで勉学に励んでいたこともある。そしてなにより、エスパニャの言葉のくるりと舌の上で回るような独特な音が好きだった。アギラールはアールの音と言っている。
目の前では不思議な線が綴られていく。アギラールが言うにはこれは文字だそうだ。
「変な形ね」
マリンチェの言葉に、ペンを走らせていた初老の男性は少し困ったように微笑んだ。ベルナル・ディアス。コルテス軍の歩兵のひとりだが、もっぱら記録を取るのを仕事としているらしい。ただ、話しかけたところで彼はマヤ語を理解しないので会話にはならない。しかしながら、文字が綴られていくのを見るのが楽しく、マリンチェは良く彼の作業を見ていた。
「またベルナル・ディアス殿に絡んでるのか」
苦笑と共に声がかけられる。アギラールだ。
「絡んでないわよ別に。見てただけ」
「そうか。ところでマリンチェ、少し来て欲しい」
アギラールの言葉に、マリンチェは目を瞬かせた。言われるがままついていくと、甲板の上はざわめいていた。誰何の声に怒号、不安げな響きも混じっている。ただ事ではないとマリンチェは眉をひそめた。
「何事なの」
「小舟が近づいてきている」
アギラールが短く答えた。マリンチェは反射的に駆けだした。身を乗り出して見やる。すぐそばに小舟は来ていた。乗っているのはふたり。格好から見るに、メヒコの民のようだった。
「――は誰だ!」
一瞬、聴き間違いかと思った。だがすぐに気付く。マヤ語ではない。もちろん、エスパニャの言葉でもない。アギラールもそれは判っていたのだろう。
「ナワトル語だわ」
「判るのか、マリンチェ」
「私の故郷の言葉よ」
アギラールが短く頷いた。最初から、マリンチェが判るかもしれないと踏んで連れてきたのだろう。
「なんと言っている」
「この軍の隊長は誰だって。お目通しを願いたいって」
マリンチェがマヤ語に訳したものを、今度はアギラールがエスパニャ語に訳してコルテスに告げた。いつの間にか甲板に来ていたコルテスはアギラールの言葉に一つ静かに頷いた。
来訪者は丁重にもてなされた。ただそれは、あくまで見た目だけだとマリンチェはすぐに気付いた。何かあればすぐに切り捨てられる位置に、アロンソが静かに微笑んだまま立っている。穏やかな彼がかなりの剣の使い手だと言うことを今のマリンチェは知っていた。
来訪者はモクテスマの使いでテウディレと名乗った。テウディレは絵描きを携えていた。絵描きはテウディレが会談している間もずっと筆を走らせていた。
「しかして貴殿は我らに何用かね」
コルテスの言葉をアギラールがマヤ語に、そのマヤ語をマリンチェがナワトル語に訳すことで会談は進められた。
「それはこちらの問いたいことと同じです。何故こちらにいらした。貴方方は何者か。我が王はその確認のために私をよこしました」
「我らはキューバのベラスケス提督の命により、貴殿等との貿易と友好をはかるために来た」
アギラールが訳したコルテスの言葉を、マリンチェはナワトル語に訳さなかった。少し、逡巡する。アギラールが眉をひそめた。
「どうした」
「そのまま言っていいと思う? 彼はモクテスマの使いよ。こっちの出方をうかがっているけれど、それ以上に自分の出方を考えあぐねていると思う」
「なぜそう思う」
「モクテスマ二世は臆病者で有名なのよ。この答え一つで、戦争になるか否かが決まりかねないわよ」
「ふむ」
アギラールは頷いて、エスパニャ語でコルテスに何かを話した。少ししてからマリンチェに告げた。
「お前の好きにして見ろ、とのことだ」
「何それ。そんなんでいいの」
多少呆れながらも、マリンチェは少し考えてからナワトル語でこう言った。
「我ら〈白い顔〉の一団は東の地より、貴殿等と友好を結ぶためにやってきた」
嘘ではない。だが、そのままでもない言葉を告げた。どちらともとれる曖昧な言葉は、マリンチェの思惑通り働いたらしい。テウディレは黙ったまま、何かを考え込んだ。そして、その日は去っていった。またすぐに来ると言って、だが。
「ご苦労だった。マリンチェ」
「貴方もね、アギラール。あれで良かったの?」
「コルテス殿がお前に任せるとおっしゃったのだから構わないだろう」
アギラールが涼しい顔で言う。それから、少し微笑んだ。
「助かった。ナワトル語、というのだな」
「ええ。アステカはナワトル語が殆どよ。タバスコのあたりはマヤ語だけど、ここから先はナワトル語が殆どだと思うわ」
「違う可能性も?」
「サン・フアン・デ・ウルア島の奥の方は別の言語の民族もいたと思うけど、詳しくはないわ」
アギラールが頷いた。
「どちらにせよ、お前がいないと話にならんと言うわけだな、マリンチェ」
「かもね。あと、私がエスパニャ語をものにするまでは、貴方も」
「判っている。頼りにしている、マリンチェ」
――頼りにしている。
その言葉に、マリンチェはぱちくりと瞬きをした。それは、必要とされているということだ。自分を必要とされている。それは、どれくらいぶりの実感だろうか。
胸の奥でくすぶった感情を押し込め、マリンチェは小さく頷いた。