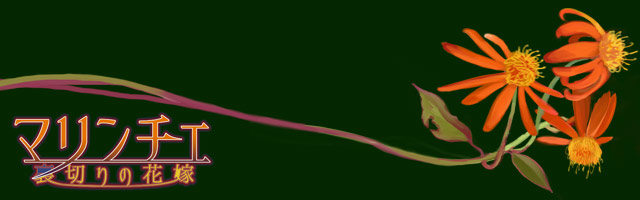Chapter4. 〈白い顔〉の戦士 - 3
戦況が一段落した。トラスカラ軍が撤退したのだ。その日はそのまま、その場での野営となった。篝火が赤々と焚かれ、酒はないがいったんの勝利を兵士たちは喜び合った。その騒ぎの中、含みのある笑みを向けてくるコルテスがどうにも気に入らなくてマリンチェは席をたった。篝火を少し頂いて、人気のないところへ行こうとした。だが、アギラールがついてきた。夕方の『話』とやらだろう。追い返すかどうするか迷って、マリンチェは諦めた。意外と頑固だと、さすがにもう知っていたからだ。こういう輩は反発すればするだけ面倒くさい。少し歩いて、視界が開けた場所に出た。崖のようだった。冴えた月が、眼下の薄雲を照り返している。叩きつけるような風が冷たい。けれど今のマリンチェにはありがたかった。寒さに震える指先が、この震えは怒りのためではないと告げてくれている。崖の下へ足を放り出すように、マリンチェは腰を下ろした。アギラールが何も言わずに隣りに座った。暫く、そのままだった。山脈を抜ける風は笛のように聞こえた。自然の旋律に身を任せて少しした頃、アギラールがそっと口を開いた。
「辛いか」
マヤ語だった。今この場でマヤ語なのは、万が一誰かに聞かれたとしても理解できるものが少ない言語を選んだためか、それとも彼なりの歩み寄りなのか。マリンチェには判らなかったが、どちらにせよありがたかった。
「――いや、悪い。聞くまでもないな。戦相手は、お前の同郷の者だ」
「こうなることを理解していなかったわけではないのよ」
ふっと、唇に自嘲の笑みが浮かぶのをマリンチェは感じた。
「モクテスマはテノチティトランに来るなと言っている。それを無視して進んでいくのよ。どこかで妨害は入るでしょう。トラスカラは……まぁ、正直想定外だったけれど」
「他の街々のように受け入れてくれると?」
「そうね。期待してたわ」
愚かだったと、理解した。
「でも、そうね。モクテスマ以前の問題よ。貴方達は〈白い顔〉の一団だもの」
「異物か」
「人間にも見えなかったわよ、最初。それが来たとして受け入れるところばかりなわけがなかった。気付かないはずがない。私は多分、気付いていて気付かないふりをしていた」
タバスコだって、戦をしたのだ。当然のことと言えた。それに気付かざるを得なかったのが今だった、それだけにすぎなかった。
マリンチェはすっと手を空へ掲げた。栗色の肌が、月光の白い輝きに彩られる。生きている。そう感じる。
「あの日、甲板の上で決めたはずなのよ。この手で何かを求めていいのなら、私は誰の犠牲もない朝が本当にすべての地に訪れるかどうかを確かめたい。その事実を知ることを求めたいって。何かを求めるなら、それ相応の犠牲は払わなければならないのよ」
自分の口から漏れる言葉が、まるで言い訳のように聞こえた。事実、言葉は震えていた。
「それはただの理想だな」
アギラールがぽつり、と漏らした。唇を噛み、マリンチェはアギラールを睨みつけてみる。
「怒るな。非難しているわけではない。そんな理想は、だれだって理解しているんだ。だが、受け入れられる奴などいない」
アギラールはすうと目を細めた。ふっと、その陽色の前髪が揺れる。
「むしろ、求めてしまうな。こういうことが欲しい。そうしたら、称賛が得られるのではないか。自分は鎖から解かれるのではないか」
「……よく、判らないわ。それは貴方の意見?」
「実体験だ」
アギラールは軽く肩をすくめた。
「くだらん昔話をするが、いいか?」
「ご勝手に」
「私は貰われ子でな。生みの両親は知らん。おそらく異国のものだっただろうとは思う。髪の色も目の色も、皆と違うだろう?」
マリンチェは一瞬驚いて声が出なかった。目をぱちくりと瞬かせ、アギラールの青い瞳を覗きこんだ。
「貴方の国でも、その色は珍しいのね?」
「ああ。全くいないわけではないが、少ないな。捨てられていたのを拾われ、育ててもらった。恩返しがしたかった。両親の慈悲にも、両親の慈悲の元になった、神にも」
「貴方が貴方の神に仕えているのは、その理由?」
「俗世的だがな。ただ、もっと直接的に、両親に恩返しがしたかった。富んだ家ではなかったからな。何かあるごとに、私は積極的に前に出て行った。八年前、この地の探索のために、とある場所を拠点にしようという動きがあった時もだ。その場所の教会のために人が集われた。私は真っ先に手を上げて、拠点となる街へ向かった。しかしその船が嵐で難破した。――その後は、いつか話したとおりだ」
マヤの民族に捕まった。いつぞや聞いた話を、マリンチェは思い返しながら短く頷いた。
「私は欲していたんだ。金も、名誉も。そうすることで恩返しが出来ると、さらに欲していた。あの地で囚われた時に、だが、お前のように考えることは出来なかった。欲求には、対価が支払われる。そんなことは考えられなかった。ただひたすらに、何故、と繰り返していた」
「それは……」
「愚かだった。だがな、マリンチェ。お前はそこに自分で気付いて、理解している。それはすごい」
アギラールの笑みは、いつもどこか不器用に見えた。
「――けれど、理想だ。マリンチェ。逃げても、いいんだ」
頭を殴られた気がして、マリンチェは息を呑んだ。
「――何を馬鹿なことを言ってるのよ」
「馬鹿か? 固執することはない、と言っているんだ。言葉は、刃物と同じ痛みを持つ。お前は言葉で同郷の者に刃を向けている。それが辛いのなら、今一度立ち返って考えてみるがいい。お前の望みは、それに勝るものか? そうでないなら――」
「勝るわ」
アギラールの言葉を遮り、マリンチェは告げた。
「私は貴方達に、トゥクスアウラを救われた。それは、私を救われたのと同じなのよ。彼は大切な友だから。その救われた事実の裏を知りたい。それは、何にも勝る要求よ」
「友か」
「ええ。友よ。友の命は、私の命と同価値よ」
アギラールが、ふわりと笑った。珍しくぎこちなさのない、素直な笑みだ。なんとなく気恥ずかしくなって視線を逸らした時、パキリ、と小さな音がした。
アギラールが反射的に立ち上がった。マリンチェも慌てて立ち上がる。敵か、密偵か、あるいは味方の誰か――コルテスかディアナか――だがどちらにせよ、今のこの状況を見られたくなかった。暗闇の中に篝火を向け、アギラールが誰何の声を上げた。
気配は、背後の木々の中からだった。戸惑うように気配は揺れ、そして、一人の男が現れた。
一瞬、トラスカラ軍の密偵かと思った。その身に着けている衣装は、アステカのジャガーの戦士と良く似ていた。だが、決定的にひとつ、違いがあった。
その戦士は〈白い顔〉だった。
化粧はメヒコのものだったが、どう見ても〈白い顔〉だった。マリンチェが状況を理解できずにいるうちに、アギラールが搾り出すような声を漏らした。
「ゲレ……ロ」
アギラールの声に、〈白い顔〉のメヒコの戦士はどこか淋しげな笑みを浮かべた。
「やはりお前たちか。アギラール。久しいな」
――メヒコの衣装を身につけた〈白い顔〉の戦士は、エスパニャ語で、そう告げた。
「辛いか」
マヤ語だった。今この場でマヤ語なのは、万が一誰かに聞かれたとしても理解できるものが少ない言語を選んだためか、それとも彼なりの歩み寄りなのか。マリンチェには判らなかったが、どちらにせよありがたかった。
「――いや、悪い。聞くまでもないな。戦相手は、お前の同郷の者だ」
「こうなることを理解していなかったわけではないのよ」
ふっと、唇に自嘲の笑みが浮かぶのをマリンチェは感じた。
「モクテスマはテノチティトランに来るなと言っている。それを無視して進んでいくのよ。どこかで妨害は入るでしょう。トラスカラは……まぁ、正直想定外だったけれど」
「他の街々のように受け入れてくれると?」
「そうね。期待してたわ」
愚かだったと、理解した。
「でも、そうね。モクテスマ以前の問題よ。貴方達は〈白い顔〉の一団だもの」
「異物か」
「人間にも見えなかったわよ、最初。それが来たとして受け入れるところばかりなわけがなかった。気付かないはずがない。私は多分、気付いていて気付かないふりをしていた」
タバスコだって、戦をしたのだ。当然のことと言えた。それに気付かざるを得なかったのが今だった、それだけにすぎなかった。
マリンチェはすっと手を空へ掲げた。栗色の肌が、月光の白い輝きに彩られる。生きている。そう感じる。
「あの日、甲板の上で決めたはずなのよ。この手で何かを求めていいのなら、私は誰の犠牲もない朝が本当にすべての地に訪れるかどうかを確かめたい。その事実を知ることを求めたいって。何かを求めるなら、それ相応の犠牲は払わなければならないのよ」
自分の口から漏れる言葉が、まるで言い訳のように聞こえた。事実、言葉は震えていた。
「それはただの理想だな」
アギラールがぽつり、と漏らした。唇を噛み、マリンチェはアギラールを睨みつけてみる。
「怒るな。非難しているわけではない。そんな理想は、だれだって理解しているんだ。だが、受け入れられる奴などいない」
アギラールはすうと目を細めた。ふっと、その陽色の前髪が揺れる。
「むしろ、求めてしまうな。こういうことが欲しい。そうしたら、称賛が得られるのではないか。自分は鎖から解かれるのではないか」
「……よく、判らないわ。それは貴方の意見?」
「実体験だ」
アギラールは軽く肩をすくめた。
「くだらん昔話をするが、いいか?」
「ご勝手に」
「私は貰われ子でな。生みの両親は知らん。おそらく異国のものだっただろうとは思う。髪の色も目の色も、皆と違うだろう?」
マリンチェは一瞬驚いて声が出なかった。目をぱちくりと瞬かせ、アギラールの青い瞳を覗きこんだ。
「貴方の国でも、その色は珍しいのね?」
「ああ。全くいないわけではないが、少ないな。捨てられていたのを拾われ、育ててもらった。恩返しがしたかった。両親の慈悲にも、両親の慈悲の元になった、神にも」
「貴方が貴方の神に仕えているのは、その理由?」
「俗世的だがな。ただ、もっと直接的に、両親に恩返しがしたかった。富んだ家ではなかったからな。何かあるごとに、私は積極的に前に出て行った。八年前、この地の探索のために、とある場所を拠点にしようという動きがあった時もだ。その場所の教会のために人が集われた。私は真っ先に手を上げて、拠点となる街へ向かった。しかしその船が嵐で難破した。――その後は、いつか話したとおりだ」
マヤの民族に捕まった。いつぞや聞いた話を、マリンチェは思い返しながら短く頷いた。
「私は欲していたんだ。金も、名誉も。そうすることで恩返しが出来ると、さらに欲していた。あの地で囚われた時に、だが、お前のように考えることは出来なかった。欲求には、対価が支払われる。そんなことは考えられなかった。ただひたすらに、何故、と繰り返していた」
「それは……」
「愚かだった。だがな、マリンチェ。お前はそこに自分で気付いて、理解している。それはすごい」
アギラールの笑みは、いつもどこか不器用に見えた。
「――けれど、理想だ。マリンチェ。逃げても、いいんだ」
頭を殴られた気がして、マリンチェは息を呑んだ。
「――何を馬鹿なことを言ってるのよ」
「馬鹿か? 固執することはない、と言っているんだ。言葉は、刃物と同じ痛みを持つ。お前は言葉で同郷の者に刃を向けている。それが辛いのなら、今一度立ち返って考えてみるがいい。お前の望みは、それに勝るものか? そうでないなら――」
「勝るわ」
アギラールの言葉を遮り、マリンチェは告げた。
「私は貴方達に、トゥクスアウラを救われた。それは、私を救われたのと同じなのよ。彼は大切な友だから。その救われた事実の裏を知りたい。それは、何にも勝る要求よ」
「友か」
「ええ。友よ。友の命は、私の命と同価値よ」
アギラールが、ふわりと笑った。珍しくぎこちなさのない、素直な笑みだ。なんとなく気恥ずかしくなって視線を逸らした時、パキリ、と小さな音がした。
アギラールが反射的に立ち上がった。マリンチェも慌てて立ち上がる。敵か、密偵か、あるいは味方の誰か――コルテスかディアナか――だがどちらにせよ、今のこの状況を見られたくなかった。暗闇の中に篝火を向け、アギラールが誰何の声を上げた。
気配は、背後の木々の中からだった。戸惑うように気配は揺れ、そして、一人の男が現れた。
一瞬、トラスカラ軍の密偵かと思った。その身に着けている衣装は、アステカのジャガーの戦士と良く似ていた。だが、決定的にひとつ、違いがあった。
その戦士は〈白い顔〉だった。
化粧はメヒコのものだったが、どう見ても〈白い顔〉だった。マリンチェが状況を理解できずにいるうちに、アギラールが搾り出すような声を漏らした。
「ゲレ……ロ」
アギラールの声に、〈白い顔〉のメヒコの戦士はどこか淋しげな笑みを浮かべた。
「やはりお前たちか。アギラール。久しいな」
――メヒコの衣装を身につけた〈白い顔〉の戦士は、エスパニャ語で、そう告げた。