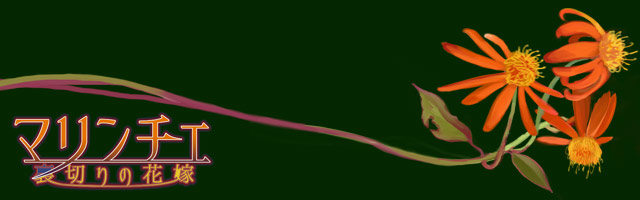Chapter5. チョルーラの惨劇 - 3
◇
上ずりそうになる声を何とか抑えこんで、マリンチェはとにかく身のまわりの物をまとめると彼女に告げた。少しの問答のあと、必ず来て欲しいと幾度も繰り返して、彼女はようやく去った。静まり返った部屋の中で、マリンチェは自身の体が震えていることに気が付いた。
――似ていた。それはもう、否定する要素すらなく、感じていた。魂が似ている。彼女は言った。それが本当かまでは判らない。けれど、考えも、立場も、年も、きっと近いものがある。
考える。震える指先を握りこみながら、思う。例えば。パイナラの街に、あの生まれ育った街に〈白い顔〉の一団が来ていたら。その中に、自分とよく似たメヒコの女が一人いたとしたら。自分はどういった行動をとるだろうか。判りきっている。同じように、訪ねて行ったに違いない。後で父に叱られようと、助けたいと思ったなら動かないはずがなかった。
彼女は、マリンチェ自身だった。少しだけ立場の違う、マリンチェ自身だった。そして彼女はきっと疑う余地すらなく思っていたのだ。自分に良く似たあの人が騙されている、と。
部屋が静まり返っていた。自らの浅い呼吸の音が耳障りだった。落ち着け。胸中で告げる。
明日の朝には戦場になると彼女は言った。もしそれが本当だとしたら、モクテスマの作戦があるのだとしたら、伝えなければいけない。アギラールにか、コルテスにか。伝えなければ、伝えて、対策を取らなければこの軍はひとたまりもないだろう。アステカと強い同盟を結んでいるならばジャガーの戦士などといった強い戦士が出てきてもおかしくはない。アステカの戦士は一流だ。無防備な状態で周りから攻められればひとたまりもない。そうなれば、仲間――ディアナだってどうなるか判らない。
でも、その情報は。
メヒコの女として、彼女が齎したものだ。
魂が似ている女同士として、彼女が教えてくれたものだ。
それを、エスパニャ軍に告げるのか。それは――
それは、彼女への裏切りだ。
目の前が暗く沈む。頭が熱を持っていた。立ち上がる。どうしたらいい。どうすればいい。何が正しい。何が正解なのか。判らないまま、胸中で問答を繰り返す。
ふらり、と足が部屋の外へ向いた。
一歩踏み出すごとに心臓が軋むように痛んだ。視界がぐるぐると揺れている感覚があった。それでもなんとか歩みを進めていく。気付くとマリンチェは、アギラールに与えられている部屋の前にいた。呼びかけるべきだと思ったが声が出ない。少ししてから、部屋の中から「誰か居るのか」と声がかかった。答えられずにいると、アギラールが顔を覗かせた。すぐにその碧眼が瞠られる。
「マリンチェ、どうした。具合でも悪いのか」
「あ……」
「顔色が悪い。どうし――」
アギラールの手が肩に触れた。アギラールは表情を険しくした。
「震えている。寒いのか。熱でもあるのか。医師のところへ行こう」
「ちが」
否定の声は最後まで出なかった。見上げる顔は〈白い〉異人のそれだ。そのはずなのに彼女の顔が重なった。
――必ず来て欲しい、必ず
――メヒコの女が虐げられているのを、同じメヒコの女がどうして見逃せると思うの
――貴女を見たとき、思ったの。魂が似ているって
くれぐれもアステカを――メヒコを裏切りませぬよう
不意に脳裏に、いつぞやのクイトラルピトックの声までも蘇った。
視野が揺れた。溢れ出す雫をマリンチェは止められなかった。頬を滑り落ちていく。
「――マリンチェ」
気がつくとマリンチェはアギラールの腕の中にいた。いつの間にか、部屋の中に入っていたようだ。その中でアギラールが抱きしめてくれている。線の細い見た目とは裏腹の、硬く力強い腕で。
「どうした。何があった」
問いかける声はマヤ語だった。メヒコの言語だった。それはアギラールなりの気遣いだっただろう。だが、マリンチェにはそれが辛かった。
〈白い顔〉の彼の腕の中で、メヒコの言語で囁かれている。
言ってはいけない。メヒコの言葉が、自分の中で囁く。
言ってはいけない。言えば、彼女を裏切ることになる。けれどもう、マリンチェは十分にエスパニャ軍に馴染んでいた。
歯の根が合わない。カチカチと耳障りな音がする。食いしばり、マリンチェは顔を上げた。
〈白い顔〉の異人。陽の光の髪に、空の色の瞳。
「アギラール」
「ああ。どうした」
優しい声だった。言えば、同胞を裏切ることになる。血も流れるかもしれない。けれど、アギラールもコルテスも、このまま黙っていたならば死んでしまうかもしれないのだ。
それは、受け入れられなかった。
――あの日、あの朝焼けを見せてくれたのは、この人なのだから。
声が震える。決意とともに、マリンチェはエスパニャ語で告げた。マヤ語もナワトル語も、今は言葉として唇に登らせることが出来ない。
「戦の……準備をして。ここの人たちはモクテスマと通じ合っている。モクテスマは私たちを陥れようとしている」
「何」
「チョルーラは危険よ」
声が震えた。
「お願い、死なないで……」
抱擁する腕に力がこもった。痛いほど強く抱きしめられる。本当か、と訊ねているかのようだった。マリンチェはちいさく頷いた。
次の瞬間、アギラールが手を握ったまま走りだした。外に飛び出すとすぐ、コルテスと鉢合わせる。
「おう、どうした慌てて。なんだマリンチェ、腹でも下したか?」
マリンチェは首を振った。いつの間にか零れていた涙を手の甲で拭う。泣いてはならないと思った。泣く資格などないと理解していた。コルテスの顔を正面から見据えた。〈白い顔〉の異人は不遜な笑みを浮かべている。
「――戦の準備をして。ここの民はアステカと――モクテスマと通じてる。街の外も中も敵だらけと思っていいわ。そういう情報が手に入ったの。きっと嘘ではないわ」
「ほう?」
「もし攻撃が来たらすぐに対抗出来るようにしておくべきだわ」
「その必要はないな」
同時だった。小銃の音が夜空に轟いた。コルテスがはっと短く笑った。
「ペドロがもう動いている」
「どういう――!?」
マリンチェの声は喧噪にかき消された。コルテスもまた小銃を空へ向かって放ち、それを合図にしたかのようにエスパニャ軍があちこちから飛び出してきたからだった。馬に乗り駆け、家の戸を街路樹を花壇を破壊していく。
「コルテス殿これはどういうことです」
アギラールが強張った声で問いかけたが、コルテスは軽く肩をすくめただけだった。
「俺も別筋でそのような話を聞き出しただけだ。確信は持てなかったが、ペドロにとりあえず見せしめに首長を殺るように言ってあった。その銃声が一発。そして今のが二発目。合図を先に軍全体に渡らせておいた。短い時間しかなかったが上手くいったな」
「どういうことです!」
「銃声二発で、この街を全て敵だと判断しろと告げていただけだ」
頭を、殴られたかと思った。
「そんな。まだ戦は始まっていない! まだこの街には女性も子供もいるわ!」
マリンチェの抗議の声に、コルテスは冷ややかな目を向けた。
「戦の始めどきは襲われた時だけではない。こちらから仕掛けるときもまた、戦の始めどきだ」
コルテスが歩き出した。すれ違いざまにマリンチェの肩を叩く。
「確信がもて、戦の指示を出せたのはお前の情報あってこそだ、マリンチェ。ご苦労だった」