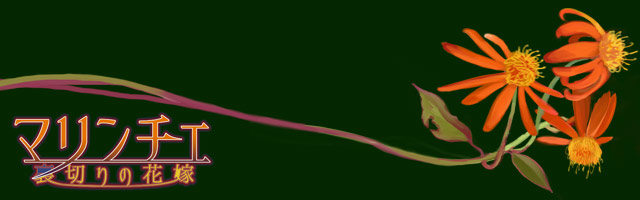Chapter6. テノチティトランの夜明け - 1
コルテスは馬から降りた。いつもどおり彼らしく、抱擁しようと歩み寄ったが、左右の男がそれを遮った。マリンチェは小声で囁いた。王は聖なる者ゆえ、触れることは叶わない、と。コルテスは少々不満気だったが短く頷いた。それから、自らの首にかけていた精巧なキラキラと煌く球で出来た首飾りをモクテスマに差し出した。モクテスマは自らの貝で出来た耳飾りを差し出した。
そして、彼も彼の従者も大地に口付けた。エスパニャ側の人間は驚いたが、マリンチェがそれがアステカ式の正式な挨拶であると告げるとコルテスもその動きに習った。コルテスという男はそういうところも柔軟だった。
「ようこそ。テノチティトランへ。我々は貴方方を歓迎いたします」
モクテスマの言葉に、コルテスは満足そうに一つ頷いた。
その後、モクテスマは自らコルテスたちを誘導し宮殿へと案内した。父王アシャヤカトルの宮殿は大きく、とても荘厳だった。マリンチェはさすがにたじろいだ。一辺境首長の娘として生まれ、奴隷として売られた身だ。さすがに宮殿など足を踏み入れたことはない。だが、ここで尻込みをしていても何にもならないとはよく判っていた。なんとか気を取り直して、通訳に徹した。モクテスマは大層な贈物をした後、こう切り出した。
「我らアステカの民は元来この地に根付いていたものではない。元々はケツァルコアトルという神となった王がいたのだ。遠い昔、ケツァルコアトルは生贄を望むテスカトリポカとの戦いに騙されて敗れ、この地を去った。だが彼は一の葦の年、東の地より再び帰り、征服すると告げていた。我らは」
一瞬、モクテスマは躊躇うように口を閉じ、そして続けた。
「我らは貴方方をその〈白い顔〉ケツァルコアトル神一行と考えておる。故に我らは貴方方を歓迎する」
――訳しながら、マリンチェはどうにもむず痒さを覚えて仕方なかった。最初は確かに、自身もそう考えた。だが随分と長い間共に過ごして来て彼らがどうあがいても人間でしかないことは十二分に理解していた。だがそれは、あくまで自分の考えだ。通訳としてそれは不要だった。ベルナル・ディアスが熱心に諸々を書き留めるのが見えたが、目を伏せることにした。
そこからの日々は怒涛のようだった。
モクテスマはとても恭順に見えた。だが同時に疲弊しているようにもマリンチェには見えた。モクテスマは市内の案内を自ら買ってでた。テノチティトランは大きく分けて四つの人が住まう区域と、中央市場や大神殿、宮殿群が並ぶ区域に分かれている。そしてテノチティトランとつながった北東には商業都市トラテロルコがあった。コルテスはトラテロルコの大市場に大変な関心を持ったようで、熱心にマリンチェやモクテスマ、その部下たちに質問をした。布、食べ物、装飾品、家財道具……ありとあらゆるものがトラテロルコには集い、流れていく。アギラールも、いたく感心したように息を漏らしていた。
「マリンチェ、すごいな。この街は」
「そりゃそうよ。テノチティトランだもの」
「お前はここで暮らしていたのか」
「ええ、昔ね」
頷く。と、不意にアギラールがそっと耳に口を寄せてきた。
「七日だ。先ほどコルテス殿が告げていた」
「――何?」
声を潜め、さらにエスパニャ語で言われてはモクテスマもその部下も判らないだろう。その状況でアギラールは続けた。
「お前の目的だ。あの生贄の儀式だ。本当なら今すぐに止めさせたいところだが、ここは随分と大きな街だ。オルメード神父たちからも慎重な意見が出ている。だが、七日。長くともそれまでにはコルテス殿はやめさせると仰っている」
ちらりとコルテスに目をやった。マリンチェの視線に気付いたコルテスはすぐにこちらの様子に気が付いたのだろう。とん、とん、と静かに自らの胸を打った。
信じろ。
そう言われている気がして、マリンチェは黙ったまま頷いた。
その後、トラテロルコの大神殿やテノチティトランの中央大神殿も見て回った。当然のごとく、神殿の壁は血で汚れ、人間の心臓が捧げられていた。ペドロは特にこういったものが嫌いなようで、アギラールやオルメード神父、コルテスにまでも諌められるほど嫌悪感をあらわにした。
その夜、マリンチェは宮殿の中で与えられた部屋に入ると同時にその場にくずおれた。とてつもない疲労感が一気に押し寄せてきたからだった。やや熱っぽい。歩きまわったこともあるだろうが、何より気疲れが大きいように感じた。横になるために布を敷いて身を横たえようとしたが、部屋がとても広く落ち着かなかった。少し悩んでから壁際に寄せてみると存外落ち着いたので、自分の小ささにマリンチェは少し苦笑した。
「おじゃましてもいいですか?」
既視感を覚えた。あのチョルーラの夜だ。反射的に飛び上がったマリンチェは、その声が小さな少女のものだと気が付いた。彼女とは違う。判っているはずなのに「どうぞ」と促す声が微かに震えた。
少ししてから、部屋に入ってきたのは声音通りの幼い少女だった。マリンチェより四、五歳ほどは下だろうか。大きく丸い目に、ふわふわとした黒髪が相まってとても愛らしい。その容貌に安堵感が生まれた。
「押しかけてしまいごめんなさい。あたしは、テクイチポともうします」
「テク――」
名をなぞりかけてマリンチェは絶句した。知った名だったからだ。少女はきょとんと首を傾げる。
「はい?」
「貴女、モクテスマ殿のご息女ですよね」
「あ、はい。ご存知でしたか」
にこりと微笑まれた。彼女は手にしていた杯を差し出した。
「不躾かとはおもいましたが、おつかれだとおもって。ショコラトルをお持ちしたのです」
「ショコラトルですって?」
マリンチェは驚いた。ショコラトルはカカオから作られる飲み物だ。ただしカカオ自体が非常に高価で、マリンチェ自身も故郷にいた頃に数回口にした程度の記憶しかなかった。受け取った杯からはぷんと刺激的な香りがした。口をつける。熱く芳しいショコラトルは体中に染み渡るようだった。ほっと息をつく。
「懐かしい。とても久しぶりに頂きました。わざわざお持ちいただいたなんて」
「口実ですの」
ふふふ、とテクイチポは笑った。
「マリンチェ様は女の方でいらっしゃったし、お年もそうはなれてはいないと見えたので。父にはいい顔はされませんでしたけれど、あたし、お話したかったのです」
ないしょですよ? とテクイチポが片目をつぶった。その仕草があまりに可愛らしくてマリンチェは警戒していた自分を忘れて笑い声をあげていた。その晩、テクイチポは遅くまでマリンチェと語り合って帰っていった。そのほとんどが好きな食べ物や好きな花のこと、最近見た夢の話、星のこと、好きな詩など他愛もないことばかりで、それがマリンチェにとっては嬉しくてたまらなかった。戦の話や神の話、戦況のことなど、そういったことに少し疲れているのだと感じた。
◇
望むもの。
ここのところ、アギラールはずっとそのことばかりを考えていた。あの日、ベルナル・ディアスの問いに答えられない自分を見つけたからだった。望むもの。それはなんだろうか。
コルテスについてきたのは、ただただ救いを欲していたからだ。マヤの生活はアギラールには耐え難い苦痛だった。聖書もなく、半裸で過ごし、ミサもない。奴隷として扱われてただただ重労働を課せられた。セノーテと呼ばれた泉に行き水を汲み、戻る。ただひたすらにその作業だけを繰り返したり、石を運んだり、時には生贄となる者達の身を清めたりといった作業までさせられた。言葉も判らない中、仲間たちは生贄としてセノーテに沈められ上がっては来なかった。次は自分の番かと怯えた。どうせなら、と自害を決意したこともあったが、自害するための道具すら得られなかった。ならばと食事を断ちもしたが生贄としていつでも出せるようにと、無理やり口にものを押し込められた。それは苦しいだけでなく、人としての扱いをされていないという事実がただひたすらに悔しかった。
そんな日々の中、同じ〈白い顔〉の生き物が現れたと噂がたった。そしてこちらの噂も届いたようだった。数日後にはエスパニャ語で綴られた手紙が届いた。八年ぶりに見たその文字に、ただ涙が零れた。無我夢中で手紙に指定されていた場所へ向かうと、あのコルテスが彼独特の皮肉めいた笑みを持って迎えてくれた。
そこからは怒涛だった。エスパニャに帰れるかと思いきや、コルテスは直ぐに帰る気はなかった。話を聞くとこの国との貿易を成功させたいという。すがるものもなく、それ自体に反対する意味も見いだせなかったので付き合うことになった。マリンチェに逢い、あの儀式を止めた。止められた。その時、何故だか自分さえも救われた気がしたのだ。
ぶるりと体が震えた。夜気が冷たい。羽織っていた外套の前をもう一度閉めると、アギラールは落ちていた視線を上げた。
寝静まったテノチティトランは、いたるところにある水路に月が映り込んで苦しいほどに美しい。父王アシャヤカトルの宮殿にある庭は、そんなテノチティトランの様子がよく見て取れた。
ある意味では自分の望みはマリンチェの望みと同じ場所にあると言えるかもしれない。声を大にして叫びたい。誰も死ななくていい。朝は来る。必ず。無益な血を流さなくてもいい。その声が過去にも届けば、あるいはあの時いなくなった仲間たちも帰ってくるかもしれない。
そこまで考えてからアギラールは苦笑した。首を振る。そんなのはありえない。万が一奇跡が起きて彼らが戻ってきたとしても、一番仲の良かったゲレロは戻っては来ない。彼を殺めたのは自らの手だ。そして彼は、この地域の人々の誤った宗教観のために亡くなったのではない。
ふと、背後から声がかかった。
「よう、部下一。何してんだ、こんな糞寒い所で」
そして、彼も彼の従者も大地に口付けた。エスパニャ側の人間は驚いたが、マリンチェがそれがアステカ式の正式な挨拶であると告げるとコルテスもその動きに習った。コルテスという男はそういうところも柔軟だった。
「ようこそ。テノチティトランへ。我々は貴方方を歓迎いたします」
モクテスマの言葉に、コルテスは満足そうに一つ頷いた。
その後、モクテスマは自らコルテスたちを誘導し宮殿へと案内した。父王アシャヤカトルの宮殿は大きく、とても荘厳だった。マリンチェはさすがにたじろいだ。一辺境首長の娘として生まれ、奴隷として売られた身だ。さすがに宮殿など足を踏み入れたことはない。だが、ここで尻込みをしていても何にもならないとはよく判っていた。なんとか気を取り直して、通訳に徹した。モクテスマは大層な贈物をした後、こう切り出した。
「我らアステカの民は元来この地に根付いていたものではない。元々はケツァルコアトルという神となった王がいたのだ。遠い昔、ケツァルコアトルは生贄を望むテスカトリポカとの戦いに騙されて敗れ、この地を去った。だが彼は一の葦の年、東の地より再び帰り、征服すると告げていた。我らは」
一瞬、モクテスマは躊躇うように口を閉じ、そして続けた。
「我らは貴方方をその〈白い顔〉ケツァルコアトル神一行と考えておる。故に我らは貴方方を歓迎する」
――訳しながら、マリンチェはどうにもむず痒さを覚えて仕方なかった。最初は確かに、自身もそう考えた。だが随分と長い間共に過ごして来て彼らがどうあがいても人間でしかないことは十二分に理解していた。だがそれは、あくまで自分の考えだ。通訳としてそれは不要だった。ベルナル・ディアスが熱心に諸々を書き留めるのが見えたが、目を伏せることにした。
そこからの日々は怒涛のようだった。
モクテスマはとても恭順に見えた。だが同時に疲弊しているようにもマリンチェには見えた。モクテスマは市内の案内を自ら買ってでた。テノチティトランは大きく分けて四つの人が住まう区域と、中央市場や大神殿、宮殿群が並ぶ区域に分かれている。そしてテノチティトランとつながった北東には商業都市トラテロルコがあった。コルテスはトラテロルコの大市場に大変な関心を持ったようで、熱心にマリンチェやモクテスマ、その部下たちに質問をした。布、食べ物、装飾品、家財道具……ありとあらゆるものがトラテロルコには集い、流れていく。アギラールも、いたく感心したように息を漏らしていた。
「マリンチェ、すごいな。この街は」
「そりゃそうよ。テノチティトランだもの」
「お前はここで暮らしていたのか」
「ええ、昔ね」
頷く。と、不意にアギラールがそっと耳に口を寄せてきた。
「七日だ。先ほどコルテス殿が告げていた」
「――何?」
声を潜め、さらにエスパニャ語で言われてはモクテスマもその部下も判らないだろう。その状況でアギラールは続けた。
「お前の目的だ。あの生贄の儀式だ。本当なら今すぐに止めさせたいところだが、ここは随分と大きな街だ。オルメード神父たちからも慎重な意見が出ている。だが、七日。長くともそれまでにはコルテス殿はやめさせると仰っている」
ちらりとコルテスに目をやった。マリンチェの視線に気付いたコルテスはすぐにこちらの様子に気が付いたのだろう。とん、とん、と静かに自らの胸を打った。
信じろ。
そう言われている気がして、マリンチェは黙ったまま頷いた。
その後、トラテロルコの大神殿やテノチティトランの中央大神殿も見て回った。当然のごとく、神殿の壁は血で汚れ、人間の心臓が捧げられていた。ペドロは特にこういったものが嫌いなようで、アギラールやオルメード神父、コルテスにまでも諌められるほど嫌悪感をあらわにした。
その夜、マリンチェは宮殿の中で与えられた部屋に入ると同時にその場にくずおれた。とてつもない疲労感が一気に押し寄せてきたからだった。やや熱っぽい。歩きまわったこともあるだろうが、何より気疲れが大きいように感じた。横になるために布を敷いて身を横たえようとしたが、部屋がとても広く落ち着かなかった。少し悩んでから壁際に寄せてみると存外落ち着いたので、自分の小ささにマリンチェは少し苦笑した。
「おじゃましてもいいですか?」
既視感を覚えた。あのチョルーラの夜だ。反射的に飛び上がったマリンチェは、その声が小さな少女のものだと気が付いた。彼女とは違う。判っているはずなのに「どうぞ」と促す声が微かに震えた。
少ししてから、部屋に入ってきたのは声音通りの幼い少女だった。マリンチェより四、五歳ほどは下だろうか。大きく丸い目に、ふわふわとした黒髪が相まってとても愛らしい。その容貌に安堵感が生まれた。
「押しかけてしまいごめんなさい。あたしは、テクイチポともうします」
「テク――」
名をなぞりかけてマリンチェは絶句した。知った名だったからだ。少女はきょとんと首を傾げる。
「はい?」
「貴女、モクテスマ殿のご息女ですよね」
「あ、はい。ご存知でしたか」
にこりと微笑まれた。彼女は手にしていた杯を差し出した。
「不躾かとはおもいましたが、おつかれだとおもって。ショコラトルをお持ちしたのです」
「ショコラトルですって?」
マリンチェは驚いた。ショコラトルはカカオから作られる飲み物だ。ただしカカオ自体が非常に高価で、マリンチェ自身も故郷にいた頃に数回口にした程度の記憶しかなかった。受け取った杯からはぷんと刺激的な香りがした。口をつける。熱く芳しいショコラトルは体中に染み渡るようだった。ほっと息をつく。
「懐かしい。とても久しぶりに頂きました。わざわざお持ちいただいたなんて」
「口実ですの」
ふふふ、とテクイチポは笑った。
「マリンチェ様は女の方でいらっしゃったし、お年もそうはなれてはいないと見えたので。父にはいい顔はされませんでしたけれど、あたし、お話したかったのです」
ないしょですよ? とテクイチポが片目をつぶった。その仕草があまりに可愛らしくてマリンチェは警戒していた自分を忘れて笑い声をあげていた。その晩、テクイチポは遅くまでマリンチェと語り合って帰っていった。そのほとんどが好きな食べ物や好きな花のこと、最近見た夢の話、星のこと、好きな詩など他愛もないことばかりで、それがマリンチェにとっては嬉しくてたまらなかった。戦の話や神の話、戦況のことなど、そういったことに少し疲れているのだと感じた。
◇
望むもの。
ここのところ、アギラールはずっとそのことばかりを考えていた。あの日、ベルナル・ディアスの問いに答えられない自分を見つけたからだった。望むもの。それはなんだろうか。
コルテスについてきたのは、ただただ救いを欲していたからだ。マヤの生活はアギラールには耐え難い苦痛だった。聖書もなく、半裸で過ごし、ミサもない。奴隷として扱われてただただ重労働を課せられた。セノーテと呼ばれた泉に行き水を汲み、戻る。ただひたすらにその作業だけを繰り返したり、石を運んだり、時には生贄となる者達の身を清めたりといった作業までさせられた。言葉も判らない中、仲間たちは生贄としてセノーテに沈められ上がっては来なかった。次は自分の番かと怯えた。どうせなら、と自害を決意したこともあったが、自害するための道具すら得られなかった。ならばと食事を断ちもしたが生贄としていつでも出せるようにと、無理やり口にものを押し込められた。それは苦しいだけでなく、人としての扱いをされていないという事実がただひたすらに悔しかった。
そんな日々の中、同じ〈白い顔〉の生き物が現れたと噂がたった。そしてこちらの噂も届いたようだった。数日後にはエスパニャ語で綴られた手紙が届いた。八年ぶりに見たその文字に、ただ涙が零れた。無我夢中で手紙に指定されていた場所へ向かうと、あのコルテスが彼独特の皮肉めいた笑みを持って迎えてくれた。
そこからは怒涛だった。エスパニャに帰れるかと思いきや、コルテスは直ぐに帰る気はなかった。話を聞くとこの国との貿易を成功させたいという。すがるものもなく、それ自体に反対する意味も見いだせなかったので付き合うことになった。マリンチェに逢い、あの儀式を止めた。止められた。その時、何故だか自分さえも救われた気がしたのだ。
ぶるりと体が震えた。夜気が冷たい。羽織っていた外套の前をもう一度閉めると、アギラールは落ちていた視線を上げた。
寝静まったテノチティトランは、いたるところにある水路に月が映り込んで苦しいほどに美しい。父王アシャヤカトルの宮殿にある庭は、そんなテノチティトランの様子がよく見て取れた。
ある意味では自分の望みはマリンチェの望みと同じ場所にあると言えるかもしれない。声を大にして叫びたい。誰も死ななくていい。朝は来る。必ず。無益な血を流さなくてもいい。その声が過去にも届けば、あるいはあの時いなくなった仲間たちも帰ってくるかもしれない。
そこまで考えてからアギラールは苦笑した。首を振る。そんなのはありえない。万が一奇跡が起きて彼らが戻ってきたとしても、一番仲の良かったゲレロは戻っては来ない。彼を殺めたのは自らの手だ。そして彼は、この地域の人々の誤った宗教観のために亡くなったのではない。
ふと、背後から声がかかった。
「よう、部下一。何してんだ、こんな糞寒い所で」