もう一度、君を迎えに来るよ、花穂。
そう、この季節に。
君の大好きな――
この、
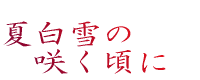
時計の針がくるくる廻り
明日の足音掻き消して
昨日がも一度今日になる
そんな魔法を教えよう
――そんな魔法を、教えよう――
それは、昭和十七年。僕は十歳。花穂が十二の頃だった。
「誠一か。いらっしゃい」
このじいちゃんの言葉から、毎年僕の夏は始まる。
じいちゃんは、シロツメクサの花が好きだ。
「じいちゃん、その時計もう動いてないよ」
「そうだなぁ」
「なんでそんなにじっと見てるの?」
「時間を見てるんだよ、誠一」
時間――って、なんだろう?
シロツメクサが笑うように風に揺れた。
「圭ちゃんだけ壊れないなんてずるいよ」
花穂が笑った。
向日葵のように無邪気に笑っていた。
「壊れないなんてずるいよ、一緒に壊れてよ」
そして僕は、僕であることを忘れた。
ああ――
想った。
ああ――なんと美しいのだろう――と。
抱いて、潰してしまいたい。抱いて、壊してしまいたい。
この一瞬を永遠にすることが出来るなら。
刹那を永久に変える事が出来るなら。
それは何にも変えがたい奇跡になるのに。
「花穂、ずっと良い子でいるのよ、圭ちゃん。
圭ちゃんのために、ずっと良い子のままでいるの」
「ずっとだよ。僕だけのものでいるね? 花穂」
「うん」
切り離された白猫の首に花穂は頬を摺り寄せた。
死んだのかな。
心のどこかがそう静かに問いかける。
死んだかい?
僕らはその日一日中、夏白雪の中で抱き合っていた。
だめだよ、花穂。
君は僕の言葉の裏側を察しちゃいけない。
君は頭が弱くて子供なんだから。察しちゃいけないんだよ、花穂。
君をずっと。とても深く。
――愛していたよ。
もう一度、君を迎えに来るよ、花穂。
そう、この季節に。
君の大好きな――
この、
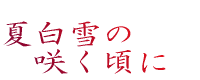
それは遠い日の、忌まわしく狂おしい愛の記憶。
止まった時と、壊れゆく美しさの物語り。
*なお当小説には、性的描写や残酷描写、暴力描写が含まれます。
苦手な方はご注意ください。
![]()