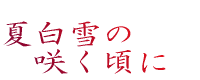
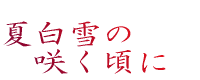
◆
朝焼けが綺麗だった。
幾つもの色を重ねた空は、けれどとても澄んでいて、太陽がまだ暖めきっていない空気は凛と涼しくて、朝という存在に誇りを与えているようにすら思える。
静かだった。
静寂という言葉がこれほど似合う時間を僕は知らない。
その中を、僕は歩いていた。朝露を煌かせている一面の夏白雪の中を、息を殺して歩いていた。僕がこれから何をしようとしているのか、何故こんな早い時間に庭に出ているのか、僕には判らなかった。だけど、目的はひとつだった。判っている。
あいつを、花穂から離す為に。
花穂はまだ眠っているはずだ。その間にやらなければ。花穂を守るために。花穂を僕だけのものにするために。
靴の裏で夏白雪が鳴いた。朝露の音と同時にくしゃりと折れた。耳を澄ませると、微かにあいつの声がした。
いる。
庭の隅にある薔薇の花壇のその狭間に、隠れるようにしてこちらを見ている。乞うように甘い鳴き声を響かせている。
唇に浮かぶ笑みを消すことが出来なかった。
「おいで」
しゃがみ込んで、声をかけた。手を伸ばすとまた、小さな甲高い鳴き声が聴こえた。木々の間に伸ばした指先に、ざらついた濡れた感触。
「おいで」
もう一度呼びかけると、今度はひょこりと顔が現れた。
白い猫だ。左右の目の色が違う、細身の白い猫。にゃあ、にゃあ、と無邪気に甘い声を届けてくる。
その猫を、僕は掴んだ。
左手に持っていた刃物を振り上げる。
殺さなくては。殺さなくては――
猫が悲鳴を上げた。僕は嘲笑った。煩く甲高い耳障りな悲鳴を閉じ込めるために、猫の口を押さえつけた。細い爪が精一杯の抵抗を示して僕の手の甲を引っ掻き回す。痛みはあまり感じない。それどころではないからだ。だって、殺さなくてはいけないから。
ひしゃげた悲鳴が聞こえた。これから何が行われるか、判るのだろうか。こんなに小さくてこんなに脆い存在でも。
青の瞳と黄金の目が見開かれた。
そして僕は、刃物を振り下ろした。
音らしい音は届かなかった。届いたのは手のひらに伝わる言いようのない感触だ。あるいは押さえつけた手の間からもれ出た猫の鳴き声だ。夏白雪に赤い液体が滴り落ちる。僕はもう一度白い体から刃物を引き抜いて、そして刺した。
鳴き声。手ごたえ。身を縮めて強張らせている猫。夏白雪に降りかかる赤いもの。また、鳴き声。手ごたえ。ひしゃげて歪んでいく猫の顔。夏白雪は紅に染まり行く。やがて鳴き声は聴こえなくなりひゅう、ひゅうと微かな空気の漏れる音がした。手ごたえも変りはじめる。
そう感じたとき、もう色違いの両の目は何も映してはいなかった。硝子球と同じ色をしていた。
死んだのかな。
心のどこかがそう静かに問いかける。
死んだかい?
白猫は色違いの目に空を反射させながら動きもしない。だけど、判らなかった。答えてくれなきゃ、判らない。
もう一度、白猫に刃物を振り下ろす。よく判らなかったから、確実に死んでもらおうと思った。しっぽは簡単に切り離すことが出来た。耳はもっと簡単に切れた。足は少し手ごたえが強すぎて、ごりごりとしていた。何とか一本切り離した。ここまでやれば死んだかな。どうかな。あんまり血が流れないから、よく判らない。僕の手も夏白雪も、もう真っ赤だったけれど、流れつくしたのかな。どうかな。死んだかい? 判らない。もっと確実にしなくてはいけない。今度は首を切り離そうか。そうすれば確実にきっと死ぬ。
首はなかなか大変だった。何度も刃物を引いた。毛がぱらぱらと落ちて、夏白雪をさらに白と赤とで色づける。
首と体はなかなか離れなかった。まだ生きているからだろうかと疑った。
何度も。
何度も。
何度も。
繰り返して。
どれくらい時がたったのかは判らなかったけれど。
何度も。
何度も。
何度も。
繰り返して。
ようやく首と体が離れようとしたときだった。
「圭ちゃんっ」
花穂の声が聞こえた。
ふう――と息を吐いて、僕は手を離した。
猫の体がぼとりと醜い音を立てて夏白雪の中に沈んだ。刃物も一緒に、花の中に沈む。猫の首だけは手に持ったままだった。
ああ、よかった。ようやく離れた。
これで死んだよね、花穂。
ゆっくりと振り返って微笑んだ。ねぇ、花穂。君は喜んでくれるよね。
君の為に、僕は殺してあげたよ。
そう言おうと思って――けれど、僕の視界の中に映り込んできた花穂は、花穂ではなかった。
全体的に日本人離れしている色素の薄い容姿。天然の栗色の髪。その長く美しい髪の一部分を編みこんでいる。
瞳も色素の薄い明るい茶色――黄土色のようにさえ見える。長いひとつ繋ぎの寝巻きのままだ。それらはすべて、確かに花穂であって、けれど花穂ではなかった。
瞳が違った。明るい茶色の瞳は、いつもの硝子球のような美しさじゃなくて、歪な肉の匂いを封じ込めてそこにあった。
――花穂?
「猫さん……っ」
花穂が裏返った声で叫んだ。
――花穂? これは花穂なのか?
だって花穂はこんな声で鳴きはしない。甘く柔らかい花のような声で僕に甘えるように鳴くのだ。それが花穂だとしたら、この裏返った耳障りな女の声は誰のものだ?
呆然としている僕の手から、花穂が猫の首を奪い取った。
どうして?
どうしてだい、花穂。何故そんな乱暴に僕の手を払う? 君はいつも、そんなことはしないのに。
花穂は夏白雪の中で、猫の首を抱いた。その手が震えていた。
「あ……あ、あ、あ……なん、てこと……」
誰だ、これは?
猫の首を抱き、その女ははらはらと涙を零す。誰だ、これは? だって花穂じゃない。花穂はこんな鳴き方はしない。泣きはしないのだ。いつも乞うように甘えるように僕に鳴くだけだ。それに花穂なら、喜んでくれるはずなのだ。だってこの猫は君を傷つけたから。でも君はこの猫が好きだろう? こうして首だけにすれば、君だけのものになるよ、花穂。花穂、君が僕だけのものであるように。
だから、喜ぶはずなのに。
花穂は、猫の首を抱いたまま僕を見上げてきた。その瞳は、涙で潤んでいた。
「圭ちゃん、おかしいよ……」
花穂の目はもう、硝子球じゃなかった。
涙に濡れた、十六歳の少女の瞳だった。
「圭ちゃんっ、花穂は――っ」
「違う」
僕はぽつりと呟いた。
「違う」
花穂が――ううん。花穂の形をした肉人形が不安げに顔を強張らせた。
猫を抱くその手にきゅっと力が篭る。
「君は花穂じゃない」
美しくない。
美しくなかった。こんな風に耳障りに泣き喚く肉人形は、花穂じゃない。花穂はいつも美しいのだ。
壊れやすく、繊細で、硝子細工のように脆く美しいのだ。
壊れない花穂は、花穂じゃない。
「僕の花穂をどこにやったんだっ」
目の前の花穂の姿をした肉人形の首を、僕は締め上げていた。
夏白雪が、足元で散った。
肉人形の意識が落ちるまで、僕はその手を離さなかった。
太陽が天頂に来る前に、花穂は一度目を覚ました。
目覚めた花穂は、いつも通り美しい硝子球の瞳をしていた。
僕は嬉しくて、それを保護したくて、もう一度そのまま時を止めたくて。
花穂の意識をもう一度奪った。
僕らはその日一日中、夏白雪の中で抱き合っていた。
◆
「ねぇ、圭ちゃん」
どうしたんだい、花穂。
「花穂ねぇ、圭ちゃんに思い出してもらいたいことがあるの」
なにをだい?
「はじめて圭ちゃんと花穂が、ずっと一緒の約束をした日のこと」
いつだったかな、それは。
「ずっとずぅっと前のことだよ」
ずっとずぅっと前のことか。
「うん、だからね」
判った。魔法があるね、僕らには。
白い光が楽しそうに笑った。
そう。僕らには魔法がある。
君の持っている、懐中時計の針に指をかけ。
くるり。
くるりと逆さに廻す。
「うん、そうだよ。圭ちゃん」
時計の針がくるくる廻り
明日の足音掻き消して
昨日がも一度今日になる
そんな魔法を教えよう
――そんな魔法を、教えよう――